今回は、パワハラの相談を受けたら上司がとるべき対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。パワハラ被害を受けたという相談では、まずは事実確認が大切なため、その注意点も紹介します。
ハラスメントに対する問題意識は高まり、社会問題化しています。上司、管理職の方のなかには、多くのパワハラ相談を受け、どう対応してよいか悩んでいる方も、少なくないでしょう。
 相談者
相談者ハラスメント相談にどう対応してよいのかわからない
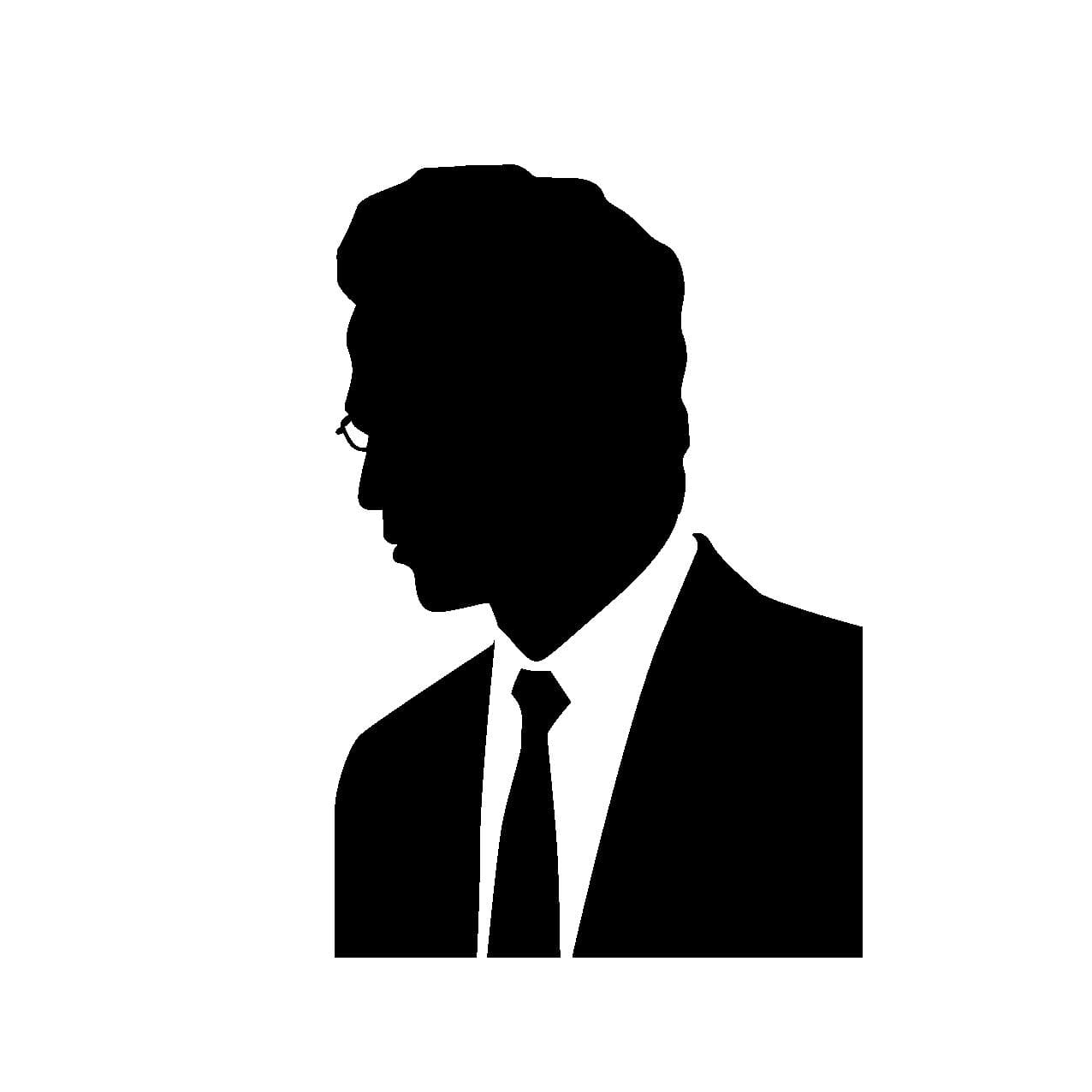 相談者
相談者仕事が多忙で放置していたら、責任があるといわれた
このような相談からも分かる通り、相談を受ける側には小さな問題でも、相談した被害者にとっては、人生を左右する大問題です。あなたへの相談が「最後の頼みの綱」という例もあり、どうしてよいかわからない、面倒だといった理由で放置すると、大事になることもあります。
ハラスメントの相談に適切に対処せず、放置をすれば、被害が拡大して「二次被害を招いた」として責任追及されるリスクもあります。上司ないし管理職の立場では、責任感ある対応が望まれます。
- パワハラを相談されたとき、上司、管理職としての責任を果たす
- パワハラの相談を受けたら、まずは丁寧な事実確認が大切
- パワハラの相談を受けたのに放置すると、損害賠償などの責任追及されるおそれあり
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
パワハラを相談されるケースとは

はじめに、パワハラの相談を受けるケースにどのような場面があるか、事例で解説します。
パワハラは、職場での地位など、優位性を利用したハラスメント(嫌がらせ)のことです。パワーハラスメントの略称であり、職場いじめと呼ばれることもあります。職場の人間関係からして逆らえない相手に、暴力をふるったり暴言を吐いたり、仲間はずれにしたりして苦痛を与え、職場にいづらくするといった行為は全て、違法なパワハラです。
パワハラが社会問題となり、人の上に立つ立場の人ほど、「パワハラの被害にあった」と相談を受けるケースは増加していますが、センシティブな問題なので慎重な対応を要します。
部下からパワハラの相談を受ける場合
一番多いのが、上司の立場で、部下からパワハラの相談を受けるケースです。
社長、役員や管理職といった、職場における上位の立場にあるとき、パワハラの被害相談に、誠意をもって向き合わなければなりません。
パワハラを相談されたのに適切に対処しなければ、あなたの対応のミスは、会社全体の責任となるおそれがあるからです。あなたが不適切な対応をしたことは、更に上の上司に相談が回ったり、裁判で会社の責任を追及されたとき、逆にあなた自身も管理責任を問われ、注意をされたり、処分の対象とされてしまったりする危険があります。
「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

同僚からパワハラを相談される場合
次に、同僚から、パワハラの相談される場合、つまり、「自分はパワハラにあっている」と打ち明けられるケースです。このような相談は、仕事上の関係というよりはむしろ、個人的な相談と考えるべき場面もあります。
ただ、個人的な相談だとしても、社内の関係には配慮して対応する必要があります。そのため、パワハラの相談を受けたという深刻なタイミングでは、たとえ同僚同士といえども、カジュアルになりすぎることなく、プライバシーに配慮して慎重に対応するのが大切です。
「会社のプライベート干渉の違法性」の解説

あなたがパワハラだと指摘される場合
一番深刻なのは、あなた自身がパワハラだと指摘されるケースです。つまり、「パワハラの相談だと思ったら、パワハラ加害者といわれたのは自分だった」という例です。
自分としては業務に必要な指導だと思っても、被害者側からパワハラと思われる例は少なくありません。上司は、部下が適切に業務遂行できるよう指導する権限があるものの、この権限は正当に行使されていなければならず、行き過ぎると、違法なパワハラになってしまいます。
どこまでが指導で、どこからがパワハラなのか、明確な線引きはなく、判断に迷うケースもあります。部下から指摘されて初めて気付くようなことのないよう、常日頃から、その行為の「目的」が正当化どうか、そして、目的に対して「手段」が相当かどうかを検討しておいてください。

「パワハラと指導の違い」の解説

パワハラの相談を受けたら、すべき対応
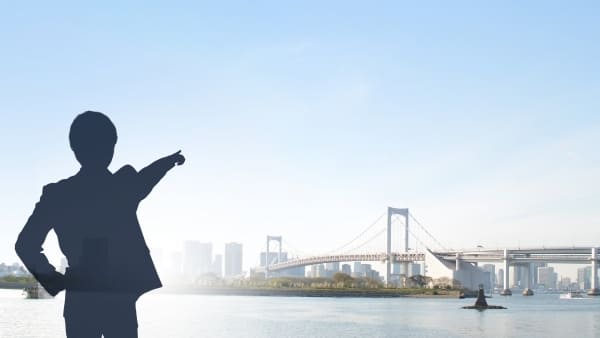
パワハラの相談を受けたときこそ、会社内のパワハラをなくすスタート地点。上司として、管理職としての責任を果たすためにも、しっかりと対応してください。
そこで、「パワハラの被害にあっている」という相談、報告を受けたとき、上司となる労働者がどう対処すべきか、相談への対応方法について、順に解説します。
パワハラ相談しづらい気持ちを理解する
パワハラの被害にあっていても、被害者側としてはなかなか人に相談しづらいものです。ハラスメント加害者との職場の上下関係、人間関係などもあり、なかなか他人には打ち明けられず、我慢しているうちにハラスメント被害が悪化するケースもあります。
「パワハラは相談しづらい」という気持ちを理解し、勇気を出して打ち明けた被害者には、誠意をもって対応するようにしてください。被害者の気持ちを理解して、次のような、パワハラを相談しづらい事情を理解して寄り添ってあげるようにしてください。
- パワハラの被害を知られると、低評価にならないか不安がある
- パワハラの相談をしたら、査定に影響してしまうのではないか
- 相談したら加害者に密告され、パワハラがひどくなるのではないか
- パワハラを相談した事実が、会社で不利益に扱われるのではないか
相談する側の不安、疑問を理解するのは、次に解説する「パワハラ相談を受けたときの事実確認の方法」でも大切です。
「パワハラが起こる理由」の解説

パワハラ被害者の安全を確保する
パワハラの相談を受けたら、被害者の安全を確保する必要があります。パワハラ被害を、これ以上継続させず、再発を防止したり、加害者からの報復を防いだりする努力が必要となります。
まだ相談を受けたタイミングでは、「本当にパワハラがあるのか」「パワハラの被害状況がどれほどなのか」、見当もつかないことも多いでしょう。それでもなお、パワハラ被害の相談をされた以上、無視してはならず、事実関係を洗い出し、対処しなければなりません。
このとき、最終的な解決までに一定の時間がかかると見越して、まずはパワハラがあったと想定して、被害者の安全が脅かされないよう、対策を講じておく必要があるのです。
「懲戒処分の決定までの期間」の解説

事実関係を確認する
次に、相談を受けたパワハラ被害について、事実関係を確認します。具体的には、相談してきた被害者本人や、職場の同僚などにヒアリングして、事情の把握に努めます。
パワハラはセンシティブな問題で、事実関係には細心の注意を要するため、次章「パワハラ相談を受けたときの事実確認の方法」で解説します。
ヒアリング初期の段階で、加害者に接触してよいかはケースバイケースです。
加害者に接触した結果、パワハラを否定されて証拠がなくなってしまったり、パワハラ被害を相談した被害者に対する不利益な扱い、報復が予想されたりする場合、しっかり被害者から事情を聞き、証拠を集めてからの方がよいこともあります。
「報復人事の事例と対策」の解説

相談を受けたパワハラの証拠を集める
パワハラの相談をした人のヒアリングを終えたら、そのパワハラ被害が事実かどうか、裏どりが必要です。つまり、証拠収集をするということです。相談ケースのなかには、気に入らない上司への嫌がらせ目的や、事実無根のパワハラ被害だったり、被害妄想による誇張だったりと、そのまま信じるわけにはいかない例もあります。
ありもしないパワハラ被害で加害者に無実の罪を着せる「パワハラ冤罪」もまた問題です。このとき、相談を受けた側が、ヒアリングの内容を裏づける証拠や、目撃者を探すことが、冤罪を避ける重要なポイントとなります。
「パワハラの証拠」の解説

相談されたことを会社に報告する
パワハラを相談された上司に、最終的な判断権がないときは、更に上位の立場の人に報告するようにしてください。重度のパワハラ相談だと、会社全体として対応する必要があり、社長への報告が必要となります。
相談直後の緊急対応を終え、パワハラが事実だと確認できたら、社長や人事、自身の上司など、ふさわしい人物に対して被害状況を報告し、一緒に対策を練るべきです。企業規模やパワハラの内容、程度によっては、初期段階から、会社全体で対応するのがよいケースもあります。今後の再発防止もまた、あなた一人では対応するには限界があり、全社での協力が不可欠です。
複雑なパワハラの証拠集めや、将来のパワハラ防止策は、弁護士のサポートが有益です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

パワハラ加害者に対応する
パワハラの相談への対応が終わり、事実確認がとれたら、パワハラ加害者への対処をします。
パワハラ加害者の責任を追及したり、社内の処遇を決めたりします。パワハラ加害者の言い分にもよく耳を傾け、弁解の内容や加害者の態度、再発のおそれなども考慮して、懲戒処分や解雇などのなかから、相当性のある処遇を決めるようにします。重すぎる処分だと、逆に加害者とされた人から争われるおそれもあるため、注意してください。
「普通解雇と懲戒解雇の違い」の解説
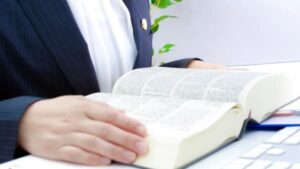
パワハラ相談を受けたときの事実確認の方法

次に、相談を受けた人が事実確認をするときに注意すべきポイントを解説します。パワハラの相談を受けた上司がすべき対応のなかでも、特に注意を要するのが事実確認のプロセスです。
パワハラ相談者を安心させる
まずは、相談してきたパワハラ被害者を安心させるのが大切です。重度のパワハラ被害を受けると、過度のストレスで思考能力が低下したり、うつ病や摂食障害など、健康ではない方も少なくないもの。事実確認の場でも気が動転し、うまく説明できない方もいます。
パワハラ被害者の現状に気を配りながら、勇気を出してパワハラを相談してきてくれたことをねぎらうなど、上司という責任ある立場の者として、被害者が安心して相談できる工夫が大切です。「社内で不利益に扱われるのでは」という恐怖から、パワハラを相談しづらいという人も多いので、被害を正直に申告しても不利益に扱わないことをはじめに伝える必要があります。
「職場のモラハラの特徴と対処法」の解説

会話のペースを合わせる
パワハラを相談されたとき、事実確認のヒアリングでは、被害者側の会話にペースを合わせましょう。「手早く状況を確認したい」といった相談を受けた側の都合を優先し、まくしたてるように質問すれば、パワハラ被害者を不安にしてしまいます。ヒアリングをストレスに感じた被害者が萎縮すると、さらに健康状態が悪化するなど二次被害を生むおそれもあります。
パワハラ相談者のプライバシーを守る
パワハラの相談を受け、ヒアリングするときは、被害者のプライバシーが害されないよう注意してください。プライバシーに配慮すれば、被害者の安心にもつながります。逆に、パワハラを相談したと加害者に知られてしまうと、被害者が報復を受けるおそれもあります。
具体的には、次のような点がポイントとなります。
- 加害者に知られないようにし、報復を防ぐ
- 加害者の席から離れた場所、防音設備のある会議室などで行う
- 場合によっては、社外の場所でヒアリングをする
- 相談内容を社内・社外に共有するときは被害者の同意を得る
- 重度のパワハラでは、弁護士に事実確認をしてもらう
パワハラの相談を受けたら、すべきでない対応

パワハラの相談を受けたら、慎重に対応しなければならず、「すべきではない対応」もあります。上司としてパワハラの相談を受けたなら、二次被害の当事者とならないよう注意してください。
相談内容を一般化してはいけない
パワハラが違法なのは当然ですが、一般論に終始しては、相談された個別事案の問題点を見逃しかねません。相談してくれた人の気持ちに寄りそうためにも、一般化はいけません。
相談に対する次のような回答は、すべきではありません。
- 上司なんてみんな厳しいものだ
- うちの会社ではその程度の対応はよくあることだ
- うちの社長はパワハラ気質だからそれくらいは普通
- みんな我慢しながらやっている
- 社会人としての修行が足りない
相談を受け、責任をもって対応すべき立場なのに、このような発言をしてしまう「中間管理職」は、既に自分も、ブラック企業に染まって手先になっているのかもしれません。自分で気付けるうちに、悪質な環境の職場からは抜け出すことをおすすめします。
「入社した会社がブラックたったときの辞め方」の解説

相談されたパワハラを否定しない
相談されたパワハラを否定するのもまた、すべきでない対応といえるでしょう。相談に対する次のような発言も、決してすべきではない対応です。
- 考えすぎるとよくない
- 文句より仕事に集中すべきだ
- この程度でパワハラというのは気にしすぎだ
- パワハラされるあなたにも原因がある
- 仕事のやる気がないのではないか
パワハラの被害を受けていると相談されたのに叱責してしまうという対応はもってのほかです。相談したことによってかえって悪化したと言われないよう、丁寧な聞き取りを心がけましょう。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

パワハラを相談されたのに放置したら責任がある?

パワハラ被害の相談を受けたのに、放置したときのリスクについて解説します。
パワハラはデリケートな問題で、慎重に対応しなければなりません。そのため、パワハラ被害の相談を受けたときの対応は、相談される側にとっても大きな労力であり、放置したい気持ちはわからなくはありません。
しかし、パワハラ被害を放置することには、大きなリスクがあります。場合によっては、相談を受けた上司の側にとって不利益のある場面も少なくありません。
相談者から慰謝料を請求される
パワハラは不法行為(民法709条)にあたる違法行為です。加害者は、被害者の受けた苦痛について、慰謝料をはじめとした損害賠償を請求されます。違法なパワハラをした加害者に責任があるのは当然ですが、相談された上司、管理職にとっても人ごとではなく、適切な対処をしないと、責任が降り掛かってくるリスクがあります。
管理職には、職場内の秩序を維持するために、部下の行動を監督し、管理する職責があります。それにもかかわらず、部下の問題行為に目をつむり、パワハラ被害を放置していると、「対応が不適切だった」として管理責任、監督責任を問われるおそれがあります。
このとき、被害者から、管理・監督すべき立場にあった人もまた、加害者と同時に、損害賠償請求を受けてしまう危険があります。
「安全配慮義務」の解説

人事考課に影響する
パワハラを相談されていたのに放置したと会社の上層部に発覚すれば、人事考課に悪影響となるおそれもあります。相談された際の対応が適切でなかったことで「管理職として不適任だ」と判断されると、低評価を受けたり、降格や減給といった処分の対象となってしまう可能性があります。
パワハラ防止策を徹底している会社では、管理職研修を実施するなどしてパワハラ知識を教育しているはずです。パワハラを相談されたのに見て見ぬふりをすることは、社内でも「問題ある上司」とみられ、評価が下がったとしても仕方ありません。
なお、会社が十分な教育を施さない結果として、相談を受けてもどうしてよいかわからないというなら、問題は企業側にあり、低評価とするのは不当な場合もあります。
「不当な人事評価によるパワハラ」の解説

会社からも損害賠償請求されるおそれ
会社としてパワハラを放置すれば、安全配慮義務違反となり、会社が被害者から損害賠償請求を受けます。このとき、会社が被害者に賠償しなければならなかったときに、その賠償額の一部について、相談を受けたのに放置していた人に対して請求されるおそれがあります。
このように、賠償責任の一部を請求することを、法律用語で「求償」といいます。パワハラ被害の放置は思いもよらぬ不利益を招くこともあり、とても危険です。「面倒だ」という気持ちは捨て去り、誠実に対応していくことが大切です。
「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

パワハラの相談を受けたら、対応の注意点
最後に、パワハラの相談を受けたら、注意しておきたい対応のポイントを解説します。
部下のパワハラは上司の責任になりうる
上司の立場にある社員には、部下を監督する責任があります。一般には、監督責任、管理責任などと呼ばれます。
そのため、自分の部下が、さらに下の立場にある社員にパワハラをしていたとき、それを知りながら放置していると、上司の責任も問われることとなります。すなわち、「部下のパワハラは、上司の責任になりうる」ということなのです。社長であれば、代表者ですからなおさらであり、会社で起こったことの最終責任は全て自分が負うと考えて対応するべきです。
「上司が指示をして部下にパワハラさせた」「上司も結託して部下をいじめた」といった悪質なケースで責任を負うのは当然ですが、悪意がなくても、「パワハラを受けたと相談されていたのに、放置し、さらに被害を拡大した」というときにも、監督不行き届きと言われてしまいます。
管理職は、その名の通り、部下を管理する責任がありますから、パワハラを防止するという会社の義務の一端を担っていることを自覚し、しっかりと対応すべきです。
「管理職を辞めたい場合の注意点」の解説

相談したのは無駄だったと思わせない
パワハラの相談を受けたら、その後にどのように対応するにせよ、きちんと相談者にフィードバックすることが大切です。相談してくれた勇気に報いるためにも、相談したのが無駄たったと思わせない努力をしてください。
細やかにフィードバックしておかないと、どのような対処をしてくれているかわからず、「相談したのは無駄だったのか」「どうせ相談してもなにもしてくれないんだろう」と思われてしまいます。「上司に相談してもなにも意味がなかった」と思われたからといってあきらめてくれるわけではありません。次は、社外、つまり、弁護士に相談され、トラブルが拡大していくケースもよくあります。
「パワハラのもみ消しへの対抗策」の解説

発見しづらい間接的なパワハラに注意
パワハラには、様々なタイプがあります。直接的な暴力や暴言のあるときはわかりやすいですが、仕事を与えない、職場環境を悪くするといった間接的なパワハラも、違法なことに変わりはありません。間接的なパワハラは、明らかには指摘されづらい方法で、こっそりと陰湿に行われます。
発見しづらい間接的なパワハラこそ、相談されたときに注意深く聞くようにしてください。被害状況が見えづらいとき、相談があっても「パワハラにならないのでは」「気にしすぎでは」と放置されがちです。しかし、隠れた悪質なパワハラこそ、社長、管理職など上の立場の者が、積極的に暴いていく必要があり、相談を受けたときには特に注意の必要なケースです。
「パワハラにあたる言葉一覧」「職場で無視されるのはパワハラ」の解説


まとめ

今回は、部下からパワハラ被害の相談を受けた上司がとるべき行動と注意点を解説しました。
パワハラの相談を受けたのに、適切な対応をせずに放置するのは危険です。パワハラ被害者からすれば、「相談をしたあなた=会社」という考えの場合も多いものです。「事後対応が適切でなかった」といった会社に対する責任追及において、あなたも巻き込まれる危険もあります。
パワハラ被害の相談を受けたら、まずは事実確認が大切です。バランスの取れた対応が重要であり、一方で、被害者に寄り添い、共感しながら誠実に対処し、他方で、証拠に基づいて真実を追及し、冤罪を生み出してしまうことは避けなければなりません。
万が一、相談を受けた内容が自分の手にはおえず、対応にこまるときには、弁護士にお気軽にご相談ください。
- パワハラを相談されたとき、上司、管理職としての責任を果たす
- パワハラの相談を受けたら、まずは丁寧な事実確認が大切
- パワハラの相談を受けたのに放置すると、損害賠償などの責任追及されるおそれあり
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【パワハラの基本】
【パワハラの証拠】
【様々な種類のパワハラ】
- ブラック上司のパワハラ
- 資格ハラスメント
- 時短ハラスメント
- パタハラ
- 仕事を与えないパワハラ
- 仕事を押し付けられる
- ソーハラ
- 逆パワハラ
- 離席回数の制限
- 大学内のアカハラ
- 職場いじめ
- 職場での無視
- ケアハラ
【ケース別パワハラの対応】
【パワハラの相談】
【加害者側の対応】





