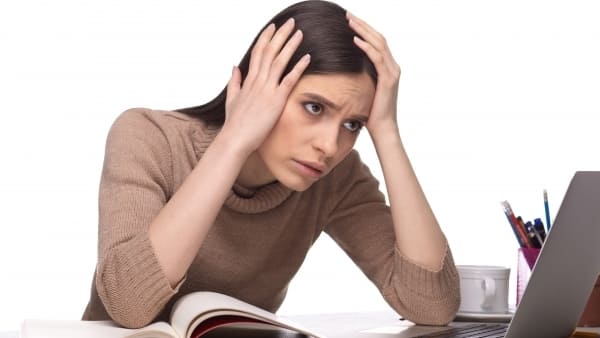社内にいるとき、仕事机に向かってパソコンを打つオフィスワーカーは多いでしょう。経理や事務、IT職種などはデスクワークが中心の方が大半です。
デスクワークを長時間すると、目が痛くなり、肩こりがひどくなるなど、業務効率が大きく下がりってしまいます。適度な休憩が必要なのは当然。しかし、休憩による離席が多すぎて社長や上司から注意されることがあります。
 社長
社長離席が多すぎて、仕事が進んでいない
 社長
社長離席して、サボっているのではないか
注意にとどまらず、懲戒処分など不利益な扱いを受けてしまったり、評価が低くなって会社にいづらくなって退職してしまったりする人もいます。トイレなどの生理現象やタバコ休憩、外の空気を浴びるといった必要な離席もあるのに、回数を制限するのは違法ではないでしょうか。
今回は、離席回数を制限し、自由を奪う会社の命令に従う必要があるのか、労働問題に強い弁護士が解説します。
離席回数の制限は違法?

会社側としては、業務に集中させようとして行う離席回数の制限。しかし、労働者にとっては自由の束縛で、逆に業務効率を下げる命令に感じるのではないでしょうか。
離席回数の制限もまた、常識的な範囲であれば、業務命令として有効なケースもあります。つまり、常識的な範囲内なら、離席回数の制限に従わなければなりません。
そこで、どの程度の離席回数の制限が適法で、どのようなときに違法になるのか、具体的に解説します。違法の判断基準は、次の3つの側面から考えることができます。
離席回数を制限する目的
会社側としては、離席回数を制限する目的は、あまりにも離席が多いと「業務に専念、集中していないのではないか」と疑われるからです。離席が多すぎて、仕事をしていない社員には、業務に集中させるための制限が必要です。
このような会社側の目的自体は、正当なものと考えられます。労働者は、会社に雇用されると、就業時間中(始業時刻から終業時刻までの間)は、会社の業務に専念すべき義務(つまり、「職務専念義務」)を負うからです。
離席回数を制限する範囲
以上のとおり、労働者の怠慢を回避するための離席回数の制限とであれば、目的は適法です。ただし、その目的に合った範囲での制限にとどまっている必要があります。目的が適法でも、あまりに厳しい制限だと、目的と比較して「過剰」であり、違法になります。
あまりにも離席回数の多い、集中力の散漫な社員への指導なのであれば、せいぜい「1時間に1回程度、数分程度」という制限の範囲で足りるでしょう。これに対して、「1日1回しか離席していけない」など、妥当な範囲を超えた過度な制限は、目的にあった制限とはいえず、不当なパワハラ、職場いじめと考えられます。

「パワハラと指導の違い」の解説

労働者に与える不利益の大きさ
離席回数を制限すれば、労働者には「自由の制限」という不利益を与えます。ある程度は、仕事上のこととして我慢しなければなりません。しかし、労働者に与える不利益があまりに大きすぎるとき、その制限は違法の可能性があります。
労働者は、雇用されて給料をもらっていれば、ある程度は、仕事による苦労を許容しなければなりませんが、不利益が大きすぎる業務命令は、違法となるからです。「水を飲むな!」という命令をする体育会系の部活が昔はありましたが、「トイレに行くな!」というように、生理現象を抑制し、労働者の生命、身体に危険が及びかねないような離席回数の制限は、違法と考えてよいでしょう。
「職場いじめの事例と対処法」の解説

離席回数の制限の、例外的なケース

ここまでは、離席回数を制限するのが違法か、適法かについての解説でした。
これに対して、離席回数を制限するのが、特殊なケースにおいては違法だと評価されやすくなります。そこで、離席回数の制限についての例外的なケースについて解説しておきます。
体調の悪い労働者のケース
離席回数を制限する業務命令が、労働者に与える不利益が大きすぎるときは、その業務命令が違法、無効と判断される可能性が高まると解説しました。
誰にでも体調の悪い日があります。たまたま体調を崩している労働者がいたとき、その人の離席回数が少しくらい多かったとしても、厳密に制限してしまっては不利益が大きすぎるでしょう。「体調が悪い」という特殊な状況をまったく無視し、形式的にルールを適用するのは違法です。
このとき、会社が労働者に負う、安全配慮義務に違反しています。そのため、体調が悪いのに、離席回数の制限に違反したとして処分するのも、違法の可能性が高まります。
「安全配慮義務」の解説

残業の多い労働者のケース
労働時間内の離席回数がとても多く、「業務に集中できていない」と考えられるにもかかわらず、一方で遅くまで残って残業代をもらおうとする労働者は問題が大きいです。頑張れば就業時間中に仕事を片付けられるのに、離席が多い結果、残業が多くなるのは妥当でないからです。
残業代を多くもらうために離席を繰り返しているのが明らかなら、懲戒処分、解雇など、厳しい処分を受けてもしかたありません。とはいえ、残業代を減らしたいからと「離席を減らせ」と命じるのは不当です。離席を含め、労働時間がタイムカードに正しく反映されない会社は、注意が必要です。
「タイムカードの改ざんの違法性」の解説
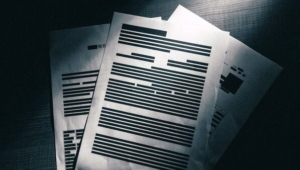
離席回数を理由に懲戒処分・解雇されたら?
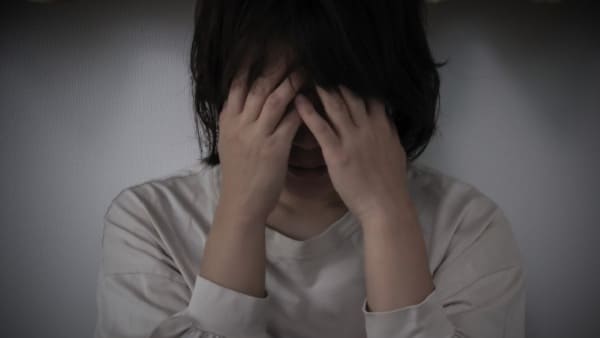
最後に、離席回数を理由に不利益な処分を受けてしまったら、労働者はどう対応したらよいか解説します。会社が、離席回数のルールを決めているとき、この離席回数のルールや、業務命令に違反して、禁止された離席を繰り返すと、不利益な処分を下される危険があります。
例えば、離席回数がルールを超えたという理由で懲戒処分になるケース。更には、離席回数が多いと「仕事ができない」という低評価につながり、退職勧奨を受けたり、最悪は解雇されてしまったりするケースもあります。
離席回数が、不利益な処分の理由になる?
離席回数を理由として、会社が懲戒処分や解雇などの不利益な処分を下せるかどうかは、その離席回数の制限が、適切であるかどうかによって変わります。本解説の通り、離席回数を制限する理由があり、その理由に対して、制限の程度が常識的な範囲内にとどまるときは、この制限に違反してしまっていることは、不利益な処分をする理由となります。
「解雇の意味と法的ルール」の解説

離席回数と、不利益の程度は相当?
万が一、離席回数の制限が、不利益な処分の理由になるときでも、その違反の程度と、不利益の程度のバランスがとれていなければなりません。
つまり、離席回数の制限に違反をして、離席をした回数、頻度、理由などによって、違反の程度が小さいにもかかわらず、懲戒解雇をはじめとした不利益の程度が重すぎる処分をすれば、違法、無効な「不当解雇」の可能性があります。
離席回数の制限が適切であっても、これにわずかに違反しているに過ぎない場合であったり、体調不良、ご家族の不幸などやむを得ない理由がある場合には、大きすぎる不利益を科されるいわれはありません。
「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

離席時のルールは守る
離席回数を制限するいわれはないときでも、離席時のルールは守っておきましょう。離席時のルールは、会社に不利益を与えないだけでなく、他の社員に迷惑をかけないためにも大切です。
例えば、上司への報告、タイムカードの打刻、業務の引き継ぎなど、離席時のルールが社内にあるとき、ルール違反をしてしまえば、注意されたり懲戒処分を受けたりする危険があります。
「協調性欠如を理由とする解雇」の解説

まとめ

今回は、離席回数を制限されるのは違法かどうか、そして、離席回数を制限する業務命令に、労働者が従わなければならないのか、解説しました。
労働者は、会社に雇われると、指揮監督を受けます。そのため、業務命令に従う必要があるのが基本です。しかし、会社に全人格的に従う「奴隷」ではありません。
会社の業務命令が違法、無効なときは、違反したからと責められることはありません。それを理由に懲戒処分、解雇など処分されたとしても、労働審判や訴訟といった裁判手続きによって、その違法性を争うことができます。
【パワハラの基本】
【パワハラの証拠】
【様々な種類のパワハラ】
- ブラック上司のパワハラ
- 資格ハラスメント
- 時短ハラスメント
- パタハラ
- 仕事を与えないパワハラ
- 仕事を押し付けられる
- ソーハラ
- 逆パワハラ
- 離席回数の制限
- 大学内のアカハラ
- 職場いじめ
- 職場での無視
- ケアハラ
【ケース別パワハラの対応】
【パワハラの相談】
【加害者側の対応】