トイレ休憩の扱いと、勤務時間中のトイレ制限、トイレ禁止の違法性について解説します。
お昼の休憩時間でなくても、仕事中にトイレに行きたくなることがあるでしょう。排泄は生理現象ですから止めようもありません。それなのに上司から「仕事中にトイレにいくな」「トイレに行き過ぎだから減給する」などと注意されると、対応に困ってしまいます。どれほど仕事が大切とはいえ、トイレに行かないのは無理があります。
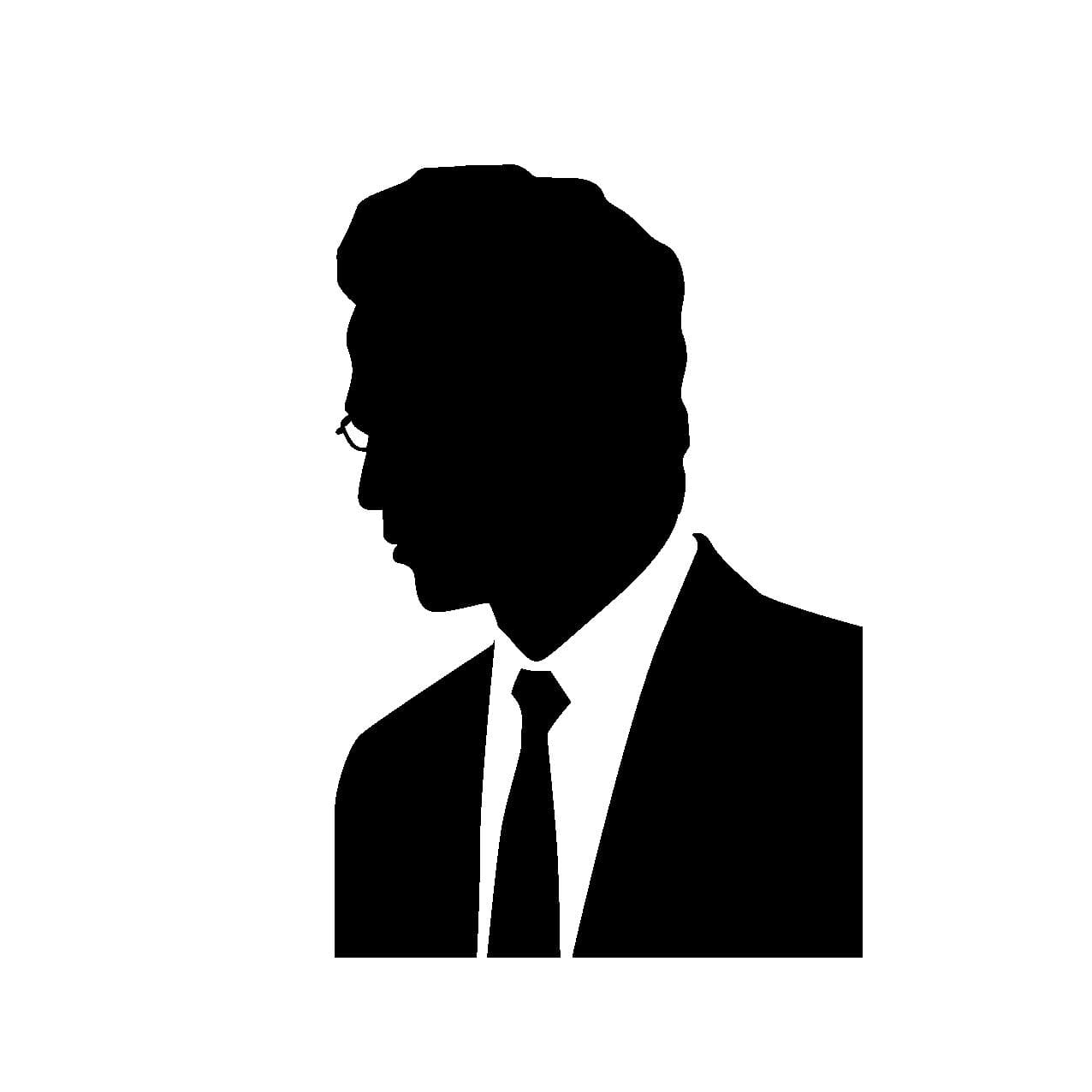 相談者
相談者昨夜飲みすぎて、ついトイレ回数が増えてしまった
 相談者
相談者オフィスのエアコンが強くて、体が冷えてしまった
仕事中のトイレを禁止する命令はありえないと思うかもしれません。しかし、トイレ回数を制限したり、トイレにいった時間を労働時間から引くブラック企業は実際にあります。不適切な命令は、嫌がらせであり、違法なパワハラにあたる可能性もあります。
また、トイレ休憩を取らせない、行かせないよう無理させるといった対応は、そのトイレ休憩が「労働時間」と扱われる結果、残業代の未払いという労働基準法違反となる可能性もあります。
- 仕事中のトイレを禁止するのは違法であり、パワハラの疑いあり
- トイレ休憩の時間を差し引き、給料や残業代を減らすのは労働基準法違反
- トイレ休憩を理由とする解雇は、労働者がよほど悪質でなければ不当解雇
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
仕事中のトイレを禁止するのは違法

会社は、雇用している労働者に対し、業務命令をしたり、企業秩序を守るためのルール(服務規律)を定めたり、その秩序を乱した者に懲戒処分を下したりすることができます。この一連の扱いによって、社内で働く人に対して一定のルールを強制できるわけです。
しかし、社内のルールは合理的なものでなければならず、生理現象であるトイレの回数を制限したり、トイレに行くことを禁止したり、そのルール違反に対して制裁を加えたりするといった非常識な内容まで、業務命令権として認められるわけではありません。
トイレを禁止する会社側の理由
労働者は、会社で働くかぎり、社内のルールに従わなければなりません。
すると、トイレ禁止や制限、労働時間からの除外(賃金の控除)といった内容が雇用契約書や就業規則に定められていた場合には、従う必要があるようにも思えます。しかし、労働契約の内容として書面に定めて約束していても、内容が法律違反ならそのルールは無効です。
会社が、できるだけトイレに行かないようにしてくるのは、トイレ休憩をされてしまうとその分だけ業務に費やす時間が減ると考えているからでしょうが、ブラック企業の発想と言わざるを得ません。
「休憩を取れない場合の対処法」の解説

トイレ禁止は、公序良俗違反となる
雇用契約や就業規則で定めたルールであっても、違法なものについては無効となる可能性があります。したがって、その違法性を検討しなければなりません。トイレを制限したり、禁止したりすることは、人の生理現象を止めるに等しく、非常識なのは明らかです。
このような非常識なルールは、公序良俗(民法90条)に違反するおそれあり。
民法90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
民法(e-Gov法令検索)
要するに、社会的に見て明らかにおかしい決まりや、非常識なルールは、法的にも違法であり、無効となる可能性が高いということです。
トイレに行きたくなるのは生理現象であり、止めようがありません。これは、たとえ仕事の時間中でも同じことです。常識的な頻度、回数ならば、トイレに行ったからといって「仕事のやる気がない」ということにはなりません。したがって、勤務時間中の「トイレ回数の制限」や「勤務時間からの除外」といったルールは、民法90条に違反して無効だと考えられます。雇用契約書や就業規則に定められていても、従う必要はありません。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

トイレに行かせないのはパワハラにあたる

次に、トイレに行かせないことがパワハラにあたるケースと、対処法を解説します。
トイレ休憩が正当な権利だとしても、会社からすれば疎ましく思われるものです。トイレのふりをしてスマホゲームをしたりLINEを返したり、サボったりする悪い人もいるため、トイレ休憩は、労働者が思っているよりも会社に敵視されています。
社長や直属の上司から「トイレにいくな」と命令されると、頻繁にトイレ休憩を取るのは難しいことでしょう。しかし、トイレに行かせないのは違法であり、パワハラに当たります。不合理で、非常識な命令に、従う必要はありません。
不合理な業務命令にはしたがわない
労働者は、会社に雇用されると、業務命令にしたがう義務があります。そして、業務時間中は、職務に専念しなければなりません(職務専念義務)。
しかし、それでもなお、不合理な業務命令にしたがってはなりません。勤務時間中にトイレにいくことを禁止され、トイレにいかせてもらえなかったり、トイレ回数を制限したりする命令は、到底合理的とはいえず、従う必要はありません。
過去には「うちは体育会系だから」といった理由で、不合理な精神論がまかり通っている時代もありました。「部活中は水を飲むな」というのが常識だった世代もあるでしょう。古い人間ほど、自身の価値観や精神論を押し付けるもので、「トイレに行くのは怠慢だ」という価値観の人がいるのは確かですが、少なくとも現代では非常識な考え方だといってよいでしょう。
「休憩時間が短いことの違法性」の解説

違法なパワハラをされたら慰謝料を請求する
会社独自のルールや、不合理な業務命令を強要されたとき、パワハラといってよいでしょう。命じるのみでなく、反抗すると大きな不利益があるケースもまた、同じくパワハラで訴えることができます。トイレ休憩を利用したパワハラには、次のような例もあります。
- トイレ休憩にいくたびに怒られる
- パートは短時間だからトイレにいくなといわれる
- コールセンターで絶え間なく電話がなるのでトイレにいけない
- トイレ休憩が申告制で、いくたび上司に報告せねばならない
- 許可をとらないとトレイにいけない
- 長時間トイレにいくことができず働かされ続ける
- トイレが長いと、社員全員の前で怒られる
- トイレのたびに、タイムカードを打刻させられる
- トイレに行かないためオムツをして働かされる
会社は、労働者を、安全な職場で健康的に働かせる義務(安全配慮義務)があります。満足にトイレ休憩もとれないような職場は、健康的とは言い難いですから、安全配慮義務違反であり、慰謝料をはじめとした損害賠償請求をすることができます。
「パワハラの相談先」の解説

トイレ休憩を理由として賃金や残業代が減らされたときの対応

トイレを禁止したり、回数・時間を制限するような一方的な会社ルールは違法であり、労働者としても従う必要はないと解説しました。
一方で、ブラック企業によるトイレ休憩への非難が、「禁止命令」ではなく「賃金の減額」として現れることがあります。つまり、トイレにいった時間を仕事をしていないので労働時間には算入せず、給料を控除したり、残業代を支払わなかったりするといった扱いです。このような扱いにも屈する必要はなく、適切な対応を理解しておいてください。
トイレ休憩も、労働時間にあたる
トイレ休憩を労働時間から除外すると、勤務している時間がその分だけ減ってしまいます。その結果、終業時刻を超えて働いたのに、残業代が発生しないと会社から反論されることがあります。しかし、このような扱いは違法となる可能性が非常に強いです。
結論として、トイレ休憩は「労働時間」です。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指すところ、トイレ休憩が「労働時間」ではなく「休憩時間」ならば、労働者はその時間を自由に利用できる必要があります。勤務中に取る短時間のトイレ休憩は、常識的な範囲である限り、「休憩時間」として自由に利用することはできないほどの時間しかないでしょう。トイレ休憩の時間を使って外出したり、仕事の休息を取ってリフレッシュしたりするのは無理があります。
したがって、長時間トイレにこもったり、トイレ休憩のついでに食事したり外出したり、ゲームをしてサボったりといった不適切な利用をしない限り、トイレの時間は労働時間としてカウントすべきです。常識的なトイレの時間を、労働時間から除外するのは、不適切な対応です。
「労働時間の定義」の解説

未払残業代を請求する
トイレの時間を理由にした残業代のカットは違法です。もし、あなたの勤務している会社で、トイレ休憩を理由に残業代を減らされてしまったら、未払いとなっている残業代を請求することができます。「給料を引かれるなら、できるだけトイレを我慢しよう」という人もいるかもしれませんが、体調が悪化してしまうので、おすすめできません。
トイレ休憩の不適切な扱いによって残業代に未払いが生じれば、労働基準法違反であり、違法です。おそらく、1日のトイレの時間を合計すれば、10分程度にはなるのではないでしょうか。1回あたりは短時間のトイレも、積もり積もればそれなりの時間数になるのは確かです。わずかな時間だとしても、あわせればそれなりの時間になります。残業代請求では損しないように細かく計算する必要があり、残業代は1分単位で請求するのが原則であることを理解しておいてください。
「残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

トイレ休憩を理由に解雇されたときの対応

最後に、トイレ休憩を理由に、解雇されてしまったときの対応を解説します。トイレ休憩を理由に解雇されるケースには、例えば次のような理由があります。
- トイレ休憩の回数が多く、サボっているから解雇
- トイレ休憩の時間が長く、成果が出せていないから解雇
- ライン作業中に勝手にトイレにいって迷惑をかけたから解雇
- 職場のトイレを使いすぎて迷惑だから解雇
解雇は、労働者にとって大きな不利益であり、強制力の強い手段です。解雇されてしまうともなれば、いかに理不尽な命令でも従ってしまう人も多いでしょう。しかし、トイレ休憩を理由とした解雇は、違法な不当解雇である疑いが非常に強いです。不当解雇は無効となりますから、やはり、その元となったトイレを禁止する命令について、たとえ解雇すると脅されても従ってはいけません。
トイレ休憩を理由に解雇されるケース
解雇は、労働者から生活の基礎となる給料を奪ってしまいます。そのため、他の懲戒処分などのペナルティに比べても、解雇は法律で厳しく制限されています。
具体的には、解雇権濫用法理のルールよって、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、違法な不当解雇として無効となります(労働契約法16条)。

トイレ休憩を理由にしてクビにする際は、適法に解雇するならば、解雇に足るほど悪質なケースである必要があります。例えば、次のように労働者にあきらかな非のある例では、解雇されても仕方ないかもしれません。
- 仕事中にトイレばかりいっていて業務をほとんどしない
- 勤務時間中の大半をトイレで過ごす
- 一度トイレにいくと寄り道ばかりで戻ってこない
「不当解雇の裁判の勝率」の解説

トイレ休憩を理由とした解雇が「不当解雇」となるケース
解雇権濫用法理のルールに照らして、客観的に合理的な理由がなかったり、社会通念上の相当性がなかったりするとき、その解雇は不当解雇となります。不当解雇をされてしまった労働者は、解雇の無効を主張して会社と争い、撤回を要求することができます。
少なくとも、次のようなケースは、トイレ休憩が常識の範囲内にあるといえ、問題がないものでしょう。この程度のことで解雇するなら、不当解雇といって差し支えありません。
- 1回あたり5分、10分程度のトイレ休憩
- 1日数回程度のトイレ休憩
- トイレ休憩のみ、もしくは、帰り道に少し寄り道する程度
- トイレ休憩の時間・回数を注意され、すぐに改善した
- トイレ休憩以外の時間で、残業せず十分に業務を終えている
ただし、あくまで常識による判断なので、「何分以上なら、仕事中のトイレが長いといえるのか」「何回以上なら、トイレ休憩が多すぎるといえるのか」は、時と場合によって慎重に判断しなければなりません。
「解雇を撤回させる方法」「解雇の解決金の相場」の解説

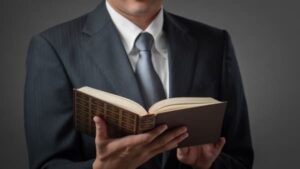
まとめ

今回は、勤務時間中のトイレ休憩の問題について、労働法の観点から解説しました。
ブラック企業が押しつける非常識なルールには、到底信じがたいものもあります。社内で当然のものとして通用していると従ってしまいがちですが、社会常識に照らして冷静に判断してください。
会社としては、トイレ休憩ばかりしていると仕事が進まないため、トイレ休憩をサボりと同じ扱いとしてしまいがちです。しかし、トイレは生理現象であり、禁止するのは不適切です。トイレに行かせないような命令は、違法なパワハラに該当します。会社から不適切なルールを強要されたとしても、そのルール自体が違法であり、無効となるため、従う必要はありません。
トイレを禁止したり回数制限したりといったことが許されないのは当然であり、むしろ、常識的な回数ないし頻度なら、トイレは「休憩時間」ではなく「労働時間」と考えるべきです。その結果、トイレ休憩の分の給料を控除したり、休憩として扱っていたりする場合には、残業代の未払いが生じている可能性もあります。
- 仕事中のトイレを禁止するのは違法であり、パワハラの疑いあり
- トイレ休憩の時間を差し引き、給料や残業代を減らすのは労働基準法違反
- トイレ休憩を理由とする解雇は、労働者がよほど悪質でなければ不当解雇
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【残業代とは】
【労働時間とは】
【残業の証拠】
【残業代の相談窓口】
【残業代請求の方法】





