パワハラというと「上司から部下へのパワハラ」をイメージするでしょう。上司という優越的な関係を利用すれば、パワハラを容易に起こせるからです。
しかし、パワハラはこのような典型例に限られません。「部下から上司へのパワハラ」、つまり、逆パワハラもまた、違法なハラスメントに違いありません。職場の人間関係が複雑化し、権利の保護が進む現代、パワハラも多様化しています。
 相談者
相談者部下が言うことを聞かないのはハラスメントでは?
 相談者
相談者上司が部下をパワハラで訴えられるのでしょうか?
部下から嫌がらせされたり、いじめを受けたりする上司もいます。上司も1人の人間であり、ハラスメントを受ければ傷付くのは当然です。そのため、違法な逆パワハラを受けたら、慰謝料をはじめとした損害賠償を請求できます。
今回は、部下から上司へのパワハラ、つまり「逆パワハラ」の具体例や対策を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 逆パワハラは部下から上司への嫌がらせだが、通常のパワハラ同様に違法となる
- 逆パワハラは、一般のイメージと反し、理解されづらく対策が遅れがち
- 社内で相談しても逆パワハラがなくならないとき、証拠を集めて訴えることが可能
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
逆パワハラとは部下から上司へのパワハラのこと

逆パワハラとは、部下から上司へのパワハラのことです。「逆ハラ」「逆ハラスメント」などと呼ぶこともあります。
パワハラは、上司から部下へ行われるものが主です。これに対して「『逆』パワハラ」というのは、典型的なパワハラとは「逆」に、部下が加害者、上司が被害者となっているという意味です。
被害者・加害者が一般的なイメージと逆なこと以外は、逆パワハラもまた通常のパワハラと全く変わりありません。パワハラは、職場における優越的な関係を利用した嫌がらせですが、「優越的な関係」は上司と部下といった職場の上下関係、主従関係で必然的に決まるわけではありません。つまり、職場では必ずしも「上司が優位」とは言い切れず、「部下が優位」となってパワハラが起こる場面もあるのです。
例えば次の理由で、「部下の方が上司より優位だ」という場面があります。
- 部下の方が専門的な知識が豊富な場合
例:IT技術、スマホの操作、パソコンスキル、流行ものの知識など - 部下の方が業務経験が豊富な場合
例:中途採用の経験豊富な部下のケースなど - 部下の方がコミュニケーション力がある場合
例:若手の方が会話スキルに優れている場合、同年代の顧客との信頼関係を構築しやすい場合など
これらのケースでは、職場における立ち位置は部下の方が優位になることがあります。上司といえど部下に教えを乞うたり、社内の評価も部下の方が高くなったりします。
部下から上司へのパワハラが起こることが一般にイメージしづらい点が、逆パワハラの最も深刻な問題です。
上司から部下へのパワハラほどよく起こる問題ではないため、逆パワハラは気付いてもらいづらく、対策が遅れがちです。また、相談しても事後対応をしてもらえず、放置されて二次被害が生じる例も少なくありません。逆パワハラの加害者となる部下の側にも自覚のないケースが多いです。
逆パワハラもまた「パワハラ」であると理解し、正当な権利を守るため、知識を身に着けておく必要があります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

逆パワハラの具体例

逆パワハラはイメージしづらいですが、理解しやすくするために、逆パワハラの具体例を紹介します。よくある逆パワハラの具体例は、次の通りです。
具体例で見れば、部下から上司への行為のなかにも悪質なパワハラが存在することがよく理解できるでしょう。
部下の知識・経験が豊富な分野で起こる逆パワハラ
部下の方が上司よりも知識、経験が豊富な場合があります。このような分野では、部下から上司への逆パワハラが生じやすい状態になっています。
従来の長期雇用、年功序列の慣行ならば、勤続を重ねるごとに知識、経験が増していき、それに従って出世します。しかし、働き方が多様化して転職が当たり前になった結果、中途採用が増加し、部下の方が知識、経験が豊富であるケースも珍しくはなくなりました。
これにより起こる逆パワハラは、例えば次のケースです。
- 上司がパソコンに疎く、初期設定を部下にやってもらっている
- IT技術の豊富な部下が上司に「こんなこともわからないのか」と発言する
- 年配の上司の聞き間違いを指摘して怒鳴る
- 部下が上司を「無能だ」と陰で馬鹿にする
時代の変化と共に、仕事に必要なスキルは変わっていきます。若い部下の方が新しいスキルを身に着けているケースも多いものです。
部下が上司の言うことを聞かない逆パワハラ
部下が上司を馬鹿にしはじめると、言うことを聞かなくなります。上司の業務命令が正当であっても、部下が従わないことによって逆パワハラが起こるおそれがあります。これにより起こる逆パワハラの具体例は、次のようなものです。
- 残業して早く終わらせるよう指示しても、すぐ帰ってしまう
- 上司の指示を無視して業務を進める
- 会社のやり方に従わない、独自の方法で仕事をしようとする
問題なのは、前章のように能力、知識に差があるケースです。必ずしも上司の命令に従わずとも、部下が成果を出してしまうと、更に上司は軽視されていきます。なお、上司の業務命令がそもそも不当であったり違法であったりするなら、従う必要はなく、拒否すべきです。
「違法な残業命令の拒否」の解説

「パワハラで訴える」という逆パワハラ
パワハラが上司から部下に対して起こりがちなのは、部下が弱い立場にあるからです。しかし、職場の地位が下だからといって、弱い立場だとは限りません。労働者保護が進むにつれて、いわば「過保護」の状態になり、権利意識が強くなりすぎてしまっている方もいます。
部下が、労働者としての権利を主張しすぎる結果、逆パワハラになる例があります。その典型例が、部下が「パワハラで訴える」と主張することによって上司が萎縮してしまうケースです。
- 上司の厳しい注意に対し、「パワハラだ」と騒ぎ立てる
- 指導されたくないので「パワハラで訴え、責任追及する」と怒鳴る
- 「会社に内部通報する」と脅す
- 上司への嫌がらせ目的で、部下が注意指導を無視する
部下が権利を主張しすぎ、逆パワハラが起きると、注意指導がやりにくくなります。
上司が萎縮して消極的になれば、職場の秩序は乱れていきます。その結果、部下は育たず、ミスも増え、ひいては会社にとっても不利益なので、本来なら会社が上司を守るべき場面です。重要なのはパワハラと指導の違いを理解して、すべき注意指導は毅然とした態度で行うことです。
「パワハラと言われた時の対応」の解説

部下が集団でする逆パワハラ
部下が弱い立場なのは、あくまで一対一の話です。部下が集団になって協力すれば、上司よりも強い立場になるケースはよくあります。モンスター社員が他の人を巻き込んで逆パワハラを起こすのが典型例です。部下が集団で起こす逆パワハラには、次の例があります。
- 部下が、集団で上司の悪口をいう
- 上司を仲間外れにし、会話に参加させない
- 部下全員が、嫌いな上司の指示を集団で無視する
- 上司の身体的特徴を馬鹿にしたあだ名(ハゲ、デブなど)をつける
- 部下が結託し、会社に上司の評価を下げる嘘をつく
また、集団的な逆パワハラは、会社の内部だけにはとどまりません。例えば、会社の近隣へのビラまき、ネット上の誹謗中傷などによる逆パワハラの例もあります。集団を巻き込んで行うほど、逆パワハラが上司に与えるダメージは深刻です。
「職場いじめの事例と対処法」「職場で無視されるパワハラ」の解説


逆パワハラを受けたときの対策

最後に、逆パワハラを受けたときの対応について解説します。部下から逆パワハラを受けた上司は、適切な対策を知る必要があります。逆パワハラもまた「パワハラ」の一種なので、直後の対応もまたパワハラと同じことがあてはまります。
逆パワハラの証拠を集める
逆パワハラの対策でも、証拠集めが重要なのは、通常のパワハラと同じです。どのような対策を講じるにせよ、逆パワハラを受けたことを説明するために、証拠が必要です。
逆パワハラが隠れてこっそりされるなら、パワハラの録音が大切な証拠となります。逆パワハラの被害を明らかにするため、「5W1H」を意識し、メモにまとめておきましょう。
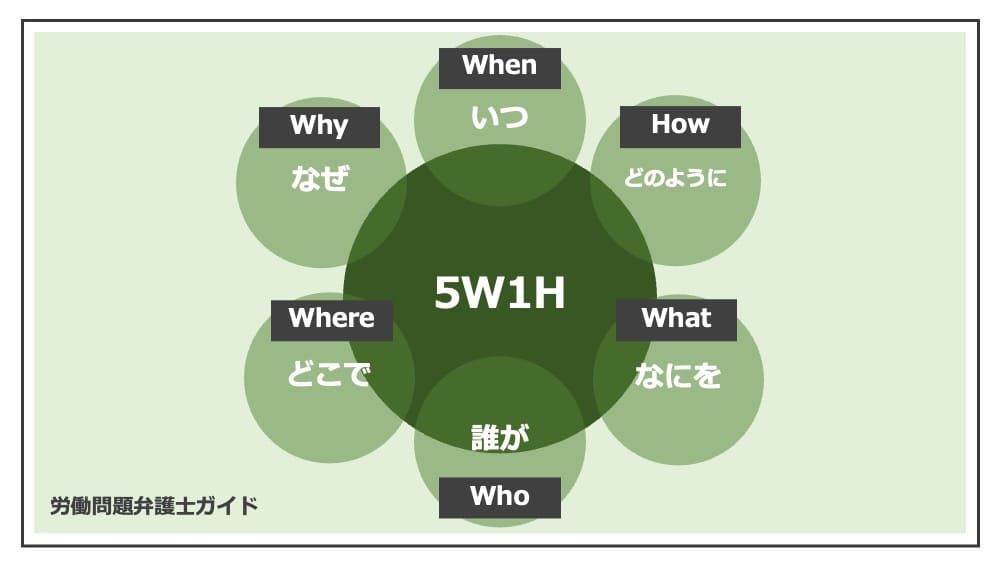
証拠集めでは、「部下の正当な権利主張」との区別が必要です。つまり、部下の言動が「正当な権利主張」の程度を超えて悪質だと、証明しなければなりません。
「パワハラの証拠」の解説

会社に相談する
次に、逆パワハラを受けたことを会社に相談しましょう。社長や人事、パワハラ相談窓口などが、適切な相談先となります。適切に対処してくれる会社なら、逆パワハラの事態が、実際には上司による適切な指導であることを社内に周知し、上司を責めないようにしてくれるでしょう。
ただし、逆パワハラは、一般のイメージと逆なため理解してもらいづらいこともあります。「上司がしっかりすべき」などと逆に注意するような会社だと、社内での相談によっては解決が困難です。
「パワハラの相談窓口」の解説

逆パワハラだと認定してもらう
会社に逆パワハラだと認定してもらえれば、被害の救済を受けられます。この認定のため、証拠が大切なのは当然です。逆パワハラだと認定してもらえれば、加害者である部下に、会社が注意をしてくれます。また、被害がこれ以上拡大しないよう、部下を異動させる対策もあります。
更に、逆パワハラの程度がひどく、しつこく繰り返されるケースは、懲戒処分や解雇も検討されます。
「やる気のない社員を解雇させるための対応」の解説

弁護士に相談する
弁護士なら、逆パワハラの事例でも、その問題性をよく理解してくれます。適切な対処をしない会社に対しては、弁護士から警告書を送付してもらう手が有効です。
逆パワハラは、社内で相談しても理解されづらいものです。「上司が部下からパワハラされる」とは誰にも理解してもらえず泣き寝入りしている方もいます。パワハラが社会問題になった当初は、誰も想定しませんでした。それでも現在では、部下から上司への逆パワハラは、よく相談を受けるケースとなっています。
自分の扱いが逆パワハラなのか疑問が生じたら、弁護士の無料相談で解消しましょう。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

部下からの逆パワハラで訴える
逆パワハラといえど、我慢すればうつ病や適応障害など、大きな被害が生じてしまいます。社内で解決できないときは、労働審判、訴訟などの裁判手続きに訴えて、責任追及する必要があります。
会社が適切な事後対応をしないなら、安全配慮義務違反の責任があります。部下だろうと上司だろうと、職場での安全は保障されなければなりません。労働審判なら、簡易かつ迅速に、逆パワハラ対策を怠った会社の責任を追及できます。
労働審判でも解決できないなら、訴訟へ進みます。また、会社の責任だけでなく、逆パワハラした加害者も同時に訴えたいときも、訴訟が最適です。
「労働問題の種類と解決策」の解説

まとめ

今回は、逆パワハラの違法性と対処法について、具体例を踏まえて解説しました。
パワハラのケースの多数は、上司から部下に対して行われます。しかし「部下だから弱い」というのは誤りで、少なくとも全てのケースにあてはまる一般論ではありません。ITベンチャーの台頭に示されるように最新の知識が重視されるとき、若い方が有利なこともあります。働き方が多様化し、権利意識も先鋭化するといった社会の変化が、部下から上司への逆パワハラを増加させています。
部下からの嫌がらせに遭っていることは、全く恥ずかしいことでも後ろめたいことでもありません。逆パワハラの被害には適切に対処し、正当な権利を主張しなければエスカレートしてしまいます。加害者や会社に対して慰謝料請求をしたいときは、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 逆パワハラは部下から上司への嫌がらせだが、通常のパワハラ同様に違法となる
- 逆パワハラは、一般のイメージと反し、理解されづらく対策が遅れがち
- 社内で相談しても逆パワハラがなくならないとき、証拠を集めて訴えることが可能
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【パワハラの基本】
【パワハラの証拠】
【様々な種類のパワハラ】
- ブラック上司のパワハラ
- 資格ハラスメント
- 時短ハラスメント
- パタハラ
- 仕事を与えないパワハラ
- 仕事を押し付けられる
- ソーハラ
- 逆パワハラ
- 離席回数の制限
- 大学内のアカハラ
- 職場いじめ
- 職場での無視
- ケアハラ
【ケース別パワハラの対応】
【パワハラの相談】
【加害者側の対応】





