上司が高圧的な態度を取ったり、同僚が日常的に嫌がらせを受けていたりなど、パワハラの現場を目撃し、違和感や不快感を覚えた人もいるでしょう。しかし、自分が当事者でなく「第三者の立場」だと、通報すべきなのか、悩むことがあります。
 相談者
相談者被害者が何も言わないのに通報すべき?
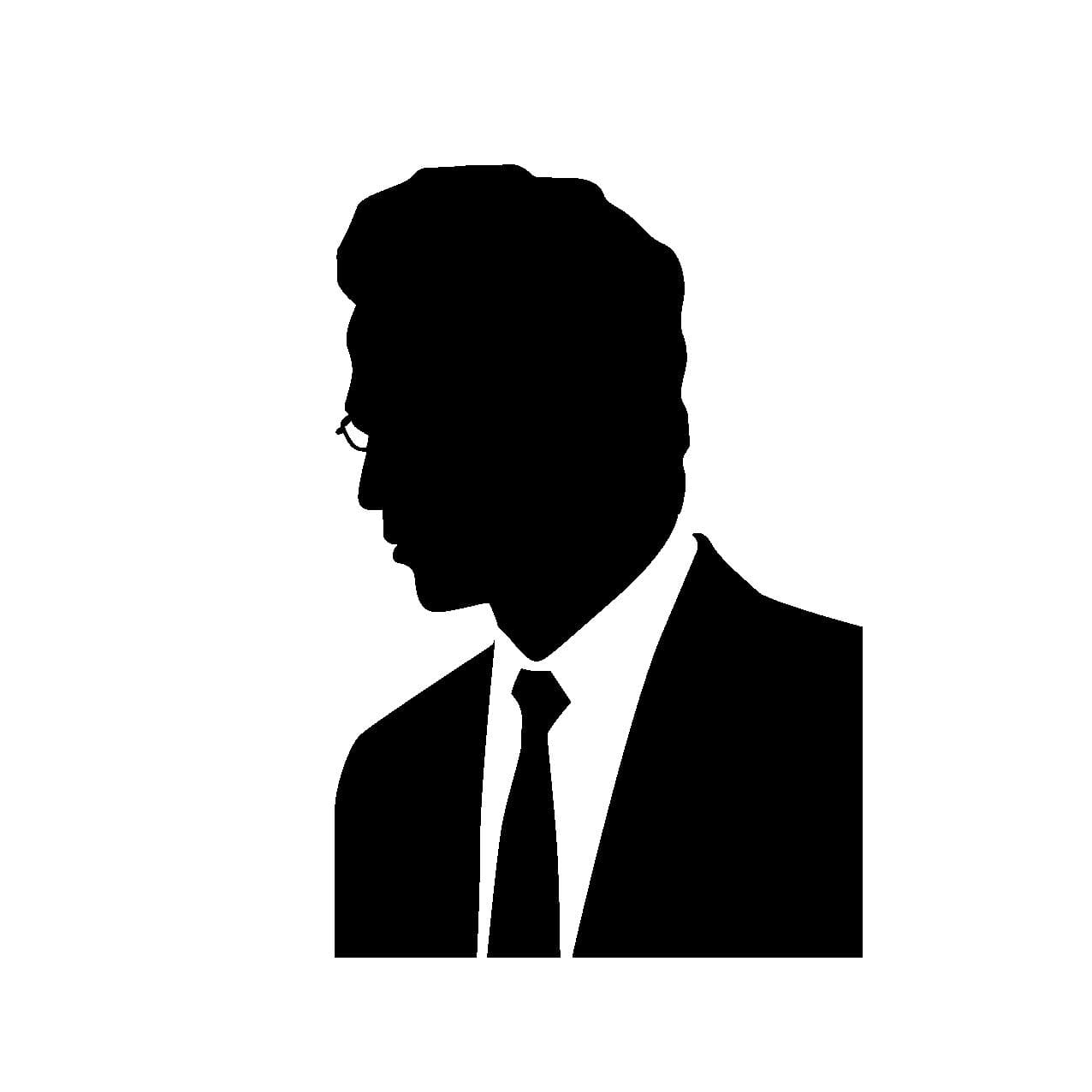 相談者
相談者後でトラブルに巻き込まれないか不安…
葛藤を抱え、行動に移せず悩んでいる方も少なくありません。
実際のところ、弁護士の元にも、パワハラを見た周りの人から法律相談が寄せられるケースもあります。第三者であっても、正しい対応は、職場の健全な環境づくりに役立ちます。
今回は、第三者がパワハラを訴えることが法的に可能かどうか、通報する際のリスクや注意点、具体的な対応方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- パワハラは、被害者本人ではなく第三者が相談することも可能
- パワハラを目的した場合、その証言は証拠になるので情報提供は役立つ
- 第三者がパワハラを通報するときは、感情的にならず冷静に対応する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
パワハラを第三者が訴えることは可能?
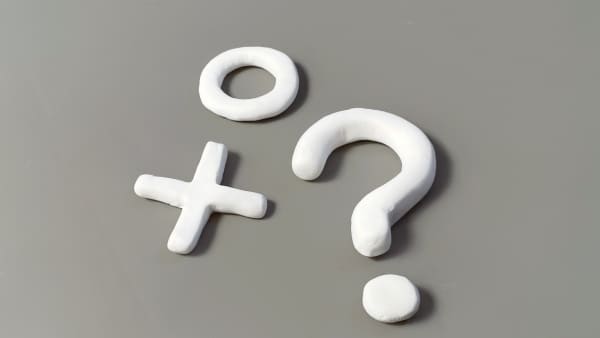
はじめに、パワハラを第三者が訴えることは可能なのか解説します。
パワハラは、職場で深刻なトラブルを生む行為です。被害者本人が声を上げにくい状況も少なくないので、第三者が動くかどうかが、被害の抑止に直結することもあります。
パワハラ防止法上の義務
2020年6月施行の労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)は、企業に対し、職場におけるパワハラ防止のための措置を講じる義務を課しています。具体的には、相談窓口の設置や再発防止策、周知・啓発活動などが必要とされ、そのガイドラインでは、被害者本人の相談に限らず、職場で状況を見聞きした目撃者や同僚などの第三者からの通報も想定されています。
そのため、会社は、相談窓口の設置や迅速な調査・対応体制を整える必要があります。
被害者本人が声を上げにくい現実を踏まえると、周囲からの通報も、パワハラ防止の重要な契機になります。つまり、「当事者しか相談できない」は誤りで、目撃者の通報もまた正当な行動です。
目撃者が声を上げることで、被害者もまた相談しやすい環境が生まれ、企業が適切な調査・対策を実施するきっかけになります。つまり、第三者による通報は法律上も想定され、実務上も重要な役割を担っているのです。
「相談を受けた上司が取るべき対応」の解説

安全配慮義務との関係
労働契約法5条は、使用者は労働者が安全に労働できるよう配慮することを義務付けています。この「安全」には、肉体的な安全だけでなく、精神的な健康(メンタルヘルス)を守る義務も含むので、職場でのパワハラを放置すれば、安全配慮義務違反となります。
この点からも、パワハラを目撃した第三者の通報は、職場環境を改善する重要なきっかけとなります。企業が、通報を受けたにもかかわらず事実確認や調査、聞き取りを怠れば、安全配慮義務違反となって損害賠償責任が生じます。
特に、役員や管理職は、パワハラを見て見ぬふりをすると、「適切に職場環境を守らなかった」と判断される可能性が高いです。
「パワハラを黙認するのは違法」について解説

家族はパワハラを訴えられるのか?
一方で、パワハラの被害者本人ではなく、家族が訴えることは原則としてできません。
労働審判や訴訟で原告となることができのは、被害を受けた当事者に限られます。そのため、家族ができるのは、被害者が精神的ショックで動けない場合などに弁護士に相談したり、会社への欠勤連絡を代わりに行ったりといった範囲にとどまります。
ただし、裁判手続きで、家族は「証人」として重要な役割を果たします。例えば、被害者が家庭で、いつどのように体調を崩したか、生活の様子を具体的に伝えることで、パワハラの影響が日常生活にまで及んでいることを示す材料となります。
また、民法711条は、被害者が死亡した場合に、被害者の父母、配偶者、子には、近親者固有の慰謝料が認められることを定めています。
「パワハラの相談先」の解説

目撃者の通報が被害者を救う第一歩

パワハラの被害者は、しばしば、自ら声を上げにくい状況に置かれます。
これには、次のように多くの理由があります。
- 「自分が悪いのではないか」と罪悪感を抱いている。
- 加害者の立場が強く、報復を恐れている。
- 人事評価への影響が不安。
- キャリアへの悪影響を心配している。
- 「通報すると会社に居づらい」と考えている。
そして、被害者自身が声を上げないと、パワハラ問題は長期化し、深刻化する傾向にあります。そのため第三者の通報は、パワハラ被害を早期に発見し、被害の拡大防止につながります。
第三者の通報は、被害が顕在化するきっかけとなります。同僚や後輩が上司のパワハラを目撃し報告したことで、企業が事実確認に動き、被害の拡大を防がれたケースもよく見られます。
周囲の人が行動を起こすことで、被害者自身も「自分には味方がいる」と感じ、通報をきっかけに相談しやすくなります。「誰かが自分の代わりに通報してくれた」という事実は、被害者にとって心の支えになるでしょう。
目撃者による行動は、被害者を孤立させず、声を上げやすい雰囲気を作り、ひいては職場全体の健全化にも繋がります。
パワハラは職場の士気や生産性を著しく下げる深刻な課題ですが、「誰かが見ているかもしれない」という抑止力が働けば、再発防止の効果もあります。
第三者自身も、パワハラ現場を日常的に見ることはストレスでしょう。
これは、二次被害の一種ともいえ、放置すれば職場環境はますます悪化します。そのため、「見ているだけで辛い」という気持ちを持つ第三者が通報することは、心理的負担を軽くして、自分を守る行為でもあります。
「ハラスメント行為そのものに第三者として不快感を覚える」といった感情や違和感を我慢せず、しっかりと通報することが被害者、職場環境、そして自分をも救う第一歩となるのです。
「パワハラはなぜ起こる?」の解説

パワハラを目撃した第三者が取るべき具体的な行動

次に、パワハラを目撃した第三者が取るべき具体的な行動について解説します。
被害者本人が声を上げられない場合、周囲の行動は、状況改善の大きな力となります。ただし、感情的に動いてしまうと、かえって悪化する危険とも隣り合わせです。
被害者に声をかけ状況確認
パワハラを目撃した場合、まず重要なのは被害者の気持ちを尊重することです。
被害者に声をかけて状況を確認しましょう。一方的な正義感で「許されないことだろう」と勝手に判断するのでなく、被害が一時的か、継続しているかといった事実を落ち着いて確認し、あくまで「被害者の支援」として関わるのが大切です。
「自分が正義の味方だ」と意気込み、被害者の意思を無視して通報すると、かえって被害者の立場を不安定するおそれがあります。
パワハラ被害者は、孤立感を抱えることが多く、声をかけること自体が「見てくれている人がいる」という意味で、被害者の心理的な支えになります。一人で抱え込んでいる人も少なくないため、その一言が相談に踏み出すきっかけになるでしょう。もし被害者がパワハラを受けていることを言えない状況なら、第三者が相談を促すことで、次の行動を取りやすくなります。
「パワハラにあたる言葉一覧」の解説

パワハラの証拠を記録する
パワハラの事実を伝えるには、客観的な証拠が必要です。
証拠は、客観的で具体的な内容が重要であり、目撃した日時や状況、発言内容などを、スマートフォンのメモ機能や録音を活用して残しておきましょう。記録を作成する際は、第三者としての中立的な視点を意識し、冷静に記録することが大切です。自分の主観や感情を加えると、証拠としての価値が下げてしまうので、あくまで「事実のみ」を整理すべきです。
第三者の証言は、社内調査や裁判でも、大きな力を持ちます。利害関係のない第三者が、被害者や他の目撃者と同じ内容を確認していると明らかになれば、被害申告の信憑性が増し、企業も誠実に対応せざるを得なくなります。
「パワハラのメモの作り方」の解説

適切な窓口に情報提供する
パワハラを目撃した第三者が、適切な窓口に情報提供することも有意義です。
被害者が直接声を上げられないケースほど、第三者からの情報提供がきっかけとなって企業や行政が調査を実施することも珍しくありません。
社内のハラスメント相談窓口
前述の通り、パワハラ防止法により、企業はハラスメント相談窓口を設置する義務があります。これは、被害者本人だけでなく、第三者からの情報提供も受け付ける役割があります。また、担当部門としては、人事部やコンプライアンス部門が対応するケースが多く、近年は、法律事務所などの外部機関に委託する企業も増えています。
相談者・通報者の秘密やプライバシーは守られるのが当然で、多くの会社は匿名での相談も可能としています。また、通報を理由に不利益な扱いをするのは違法です。
「内部通報をもみ消されない方法」の解説

外部の行政機関
社内窓口に相談しにくい場合は、外部の行政機関を利用しましょう。
代表的なのが労働基準監督署であり、重大な違法行為が疑われる場合の相談先となります。労働条件や職場環境に関する違反の有無を調査し、必要に応じて指導や是正を行う行政機関ですが、パワハラには直接的に対応してくれない可能性があります。
また、都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」では、パワハラを含む幅広い労働問題について無料で相談できます。第三者からの相談も可能なので、被害者本人が動けない場合にも有効な窓口です。法的対応を要するなら、弁護士に相談し、損害賠償請求や労働審判、訴訟を見据えたアドバイスを受けるのも有益です。
「労働基準監督署への通報」の解説

第三者がパワハラを訴えることは可能?

次に、第三者がパワハラを訴えることが法的に可能かどうかについて解説します。
職場で目撃したパワハラについて通報する意義は大きいですが、法律上は「被害を直接受けた本人」と「第三者」とでは扱いが大きく異なります。
法的には訴えることはできないのが原則
パワハラに関して法的手続きを取れるのは、被害を直接受けた本人に限られます。
例えば、民事訴訟で損害賠償を請求する場合、原告になれるのはパワハラにより精神的苦痛や経済的損害を受けた被害者本人です。家族や同僚はもちろん、目撃しただけの第三者には損害が発生しておらず、原告として請求することはできません(代理で訴えることもできません)。
刑事告訴も同様で、暴行や脅迫といった犯罪が成立するパワハラでも、告訴できるのは被害者本人です。第三者が「告発」として刑事事件化を求めることはできますが、捜査が進むかどうかは捜査機関(検察・警察)の判断次第と言わざるを得ません。
このように、訴訟や告訴は「被害者本人の権利」に属するため、たとえ第三者が問題意識を持っても、本人の意思を無視した権利行使はできません。第三者にできるのは、通報や証言、被害者への支援といった補助的な役割にとどまります。
「会社を訴えるリスク」の解説

弁護士に相談すべきケース
一方で、企業がパワハラを知りながら放置した場合、被害は深刻化してしまいます。
このようなケースでは、パワハラを目撃した第三者も、弁護士に相談することで事態改善のきっかけを作ることができます。本来、被害者が著しい不利益を受けているなら、安全配慮義務違反や使用者責任が問題となり、企業は迅速に対処すべきです。
また、第三者が勇気を出して通報したのに、報復人事や嫌がらせを受けるケースも少なくありません。パワハラ防止法は、通報者への不利益取扱いを禁じていますが、現実問題としては隠れて嫌がらせを受けるケースは跡を絶ちません。このようなケースでは、通報者自身が被害者となるので、速やかに弁護士に相談して救済を受けるべきです。
訴訟に発展する可能性がある場合や、公益通報者保護制度の利用を検討する場合も、専門的なアドバイスが不可欠です。
「労働問題に強い弁護士」の解説

第三者がパワハラを通報する際の注意点

最後に、第三者がパワハラを通報するときに注意すべきポイントを解説します。
通報は、被害者を守り、職場環境を改善する大切な行動ですが、伝え方や姿勢を誤ると逆効果なこともあります。特に、パワハラ加害者に制裁を加えることを目的にするのでなく、あくまで将来の改善に繋げる視点が大切です。
通報者への不利益取扱いは禁止される
パワハラ防止法では、通報者や相談者への不利益な取扱いは禁止されています。
例えば、通報したことを理由に降格したり左遷したり、報復人事や不当な異動、昇進の妨害や解雇といった行為をすることは、法律違反です。
それでも現実には「通報したことで上司から疎外された」「評価が下がった」といった相談は存在します。この場合、労働基準監督署や労働局に相談したり、弁護士に依頼して労働審判や訴訟を通じて救済を求めたりすることができます。
実際に、上司の不正を内部通報した社員が、その後ほとんど仕事を与えられない部署へ配置転換され、遠方への異動を命じられた事例があります。このような被害は、本当に「通報したこと」が理由となっているのかが見えづらい面があるので、慎重に対処しなければなりません。
「違法な報復人事への対策」の解説

感情的にならず客観的な事実を伝える
パワハラを目撃すると、強い憤りを感じるでしょう。しかし、第三者が通報する際に大事なのは、感情のまま行動せず、事実を客観的に伝えることです。正義感だけで突き進むと、加害者への批判や感情が先立ち、かえって信頼性を損ねます。
通報では「いつ、どこで、誰が、何をしたのか」といった事実を、具体的に説明することが重要です。嘘をついたり誇張したり、推測や憶測を含めたりすると、名誉毀損や業務妨害といった法的責任を負う危険もあるので注意しましょう。
「名誉毀損したら解雇される?」の解説

パワハラが起こる職場の改善を求める
パワハラを通報する目的は、「加害者を懲らしめること」ではなく、被害の再発防止と職場環境の改善に置くべきです。建設的な意図で通報すれば、会社にも受け入れられやすくなります。
企業には通報を受けた後、ハラスメント防止研修の実施、組織体制や人事配置の見直し、相談窓口の強化といった施策を通じて、再発を防ぐ体制を整える責任があります。第三者による通報は、その仕組みづくりの出発点となり、企業の取り組みを促すきっかけとなります。
「安全配慮義務」の解説

まとめ

今回は、パワハラ被害者本人だけでなく、周りの人が訴えるケースを解説しました。
パワハラは、被害者に苦痛を与えるだけでなく、周囲の職場環境に悪い影響を及ぼします。たとえ自分が直接の被害者でなくても、「目撃した」「見過ごせない」と感じたなら、第三者として会社に相談したり、行政機関に通報したりすることが可能です。むしろ、安全な職場環境を守るためには、必要不可欠な行動とも言えるでしょう。
ただし、通報の際は正しい手順を踏み、不利益を受けないよう注意しなければなりません。「誰かが言わないと状況が変わらない」というとき、あなたがその「誰か」になることが、職場全体を健全な方向に変化させるきっかけになります。
迷ったときは一人で抱え込まず、社内の相談窓口や、弁護士への相談を検討してください。
- パワハラは、被害者本人ではなく第三者が相談することも可能
- パワハラを目的した場合、その証言は証拠になるので情報提供は役立つ
- 第三者がパワハラを通報するときは、感情的にならず冷静に対応する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【パワハラの基本】
【パワハラの証拠】
【様々な種類のパワハラ】
【ケース別パワハラの対応】
【パワハラの相談】
【加害者側の対応】
★ 証拠収集の労働問題まとめ
【残業代請求の証拠】
【労働問題の証拠】





