「退職」は、人生の岐路ですが、何度も訪れる機会ではありません。そのため、「退職したらやること」を熟知していない人が多いのは当然。また、退職したらすべきことが、思いのほか多くあるのも混乱のもとです。
退職したらやることは、その人の状況や退職理由、将来の計画によっても異なります。円満退職できず労使トラブルを抱えると、会社が非協力的なことも。労働問題の解決のために、労働審判や訴訟などの法的手続きを要するケースもあります。
退職したらやることの多くは、行政での手続きです。失業保険をはじめとした手続きをスムーズに進めるには、退職前からの準備も大切。退職日までの期間に余裕があるなら、退職先との関係ですべきことを先に済ませましょう。
今回は、退職したらやることを、順を追って、労働問題に強い弁護士が解説します。
退職したらやることの順番は?退職後に必要な手続きを解説

まず、退職したらやることについて、順番に解説します。
退職したらやることは多岐に渡るため、順に進めていく必要があります。すぐに期限が到来する手続きもあり、優先順位を把握し、速やかに着手してください。なお、これらのステップを進める順番について、優先順位を付ける必要があります。
- 違法な労働問題がないか確認する
労働問題が残存しているなら直ちに証拠集めが必要です。そのため、最優先の順位となります。 - 必要書類の交付を求める
以下の手続きを進めるのに、会社の交付する書類を要する場合があります。そのため、第二順位のステップとなります。 - 住民税の支払いをする
住民税を給料天引きで払っている場合、退職の翌月の住民税から対応が必要となります。 - 健康保険の切り替え手続き
国民健康保険に切り替える場合、退職日から14日以内が期限です。 - 年金保険の切り替え手続き
国民年金保険に切り替える場合、退職日から14日以内が期限です。 - 失業保険の手続きをする
労働者の手続きに期限はないものの、離職日の翌日から1年しか失業保険がもらえないため、離職票を受け取ったらすぐ手続きしましょう。離職票は、会社がハローワークに対し、離職から10日以内に手続きする必要がありますが、労働者の手元に届くのはもう少し後になります。円満退職なら、できるだけ在職中に準備してもらえるよう求めましょう(離職票の受け取り方、離職票が届かない場合の対処法参照)。 - 未払いの金銭がないか確認する
残業代の時効は3年で、給料日ごとに3年前の残業代が時効にかかります。
退職後、次の給料日が来るまでには請求すべきです。
違法な労働問題がないか確認する
退職前後で、会社の対応に疑問を感じたら、違法な労働問題がないか確認しましょう。違法な点に気づいたら、責任追及はできるだけ早期に行うべき。退職後でも遅すぎはしませんが、放置して期間が経つと証拠がなくなることも。証拠が散逸すれば、いざ労働審判や裁判で戦うにも、不利になるおそれがあります。
最重要なのは、「辞め方」に関するトラブル。つまり、違法な退職強要や、不当解雇といった問題点です。退職そのものに不満があるなら、ただちに異議を述べる必要があります。
特に、解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でない場合には、違法な不当解雇として無効ですから(労働契約法16条)、直ちに異議を述べ、争うべきです。

会社の不適切な対応を争うには、証拠を集める必要があります。労働審判や訴訟など、法的な手続きを有効活用するには、早めに弁護士へ相談ください。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

必要書類の交付を求める
退職の時点で、今後必要となる書類の交付を、会社に請求しましょう。退職後のプロセスを円滑に進めるには、次の資料を受領する必要があります。これらの資料は、次章以降の手続きをスムーズに進めるのにも必須のものです。
- 離職票・雇用保険被保険者証
いずれもハローワークでの失業保険の受給に必要です。雇用保険加入時に発行される雇用保険被保険者証は、会社に預けてある場合は返還を求めましょう。 - 退職証明書
健康保険や年金の加入手続き、転職先への提出などに利用します。労働基準法22条1項で発行が義務付けられています。 - 健康保険の資格喪失証明書
国民健康保険に加入する際、必要書類となります。 - 年金手帳
基礎年金番号や加入歴といった重要な情報が記載されており、年金に関する手続きをする際に必要です。入社に会社に預けた場合は、返還を求めてください。 - 源泉徴収票
確定申告、転職後の年末調整などに利用します。所得税法226条1項で、退職後1ヶ月以内の発行が義務付けられています。
また、今後の手続きでは、マイナンバーカードや身分証明書、印鑑など、労働者自身で準備しておくべきものもあるので、手元に揃えておいてください。手続きが遅れるほど、労働者に不利益があります。そのため、会社のせいで遅れることのないよう、速やかに依頼しておきましょう。
なお、離職票記載の離職理由により、失業保険を受給できるタイミングや額が異なります。一般に、自己都合退職より、会社都合退職の方が有利。真実と異なる離職理由を記載された場合、ハローワークへの異議申し立てが可能です。
「自己都合と会社都合の違い」の解説
住民税の支払いをする
住民税は、在職中は給料から天引きされている人が多いでしょうから、退職する場合にはその支払いについて検討する必要があります。住民税の支払い方法について、退職のタイミングやその後の離職期間によって扱いが異なるため、注意を要します。
退職後、1ヶ月以内に転職する場合
退職後、1ヶ月以内に転職する場合には、次の就職先の給料から天引きすればよいため、転職先にも天引きの手続きを依頼し、異動届を提出すれば手続きは完了します。
退職後、1ヶ月以上離職する場合
これに対して、転職後に1ヶ月以上離職する場合には、空白の期間における住民税の支払いは、退職の時期によって扱いが異なります。
- 1月1日〜5月31日までの退職
最終月の給料及び退職金から、5月分までの住民税が控除され、6月以降は自身で支払う - 6月1日〜12月31日までの退職
退職月までの住民税が給料から控除され、翌月以降は自身で支払う
健康保険の切り替え手続き
退職したら、速やかに、健康保険証を会社に返還します(本人分だけでなく、被扶養者分も返還を要する)。退職直前までは利用できるので、健康保険証の返還は「退職後」で構いません。なお、失効した保険証を使用すると、後に清算が必要となります。
そして、退職後に離職期間が1日でも生じるなら、健康保険の切り替え手続きが必要です。この手続きには選択肢が3つあり、利用条件や期限が異なるため損のないよう比較検討してください。
| 任意継続を利用する | 国民健康保険に加入する | 家族の扶養に入る | |
|---|---|---|---|
| 利用条件 | 退職前の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること | - | 年収が130万円未満。 家族が健康保険の被保険者(その家族の年収が自分の倍以上であることが必要) |
| 手続きの期限 | 退職の翌日から20日以内 | 退職の翌日から14日以内 | - |
| 手続きの場所 | 加入していた健康保険組合、居住地域の社会保険事務所など | 住所地の市町村区役所の国民健康保険担当窓口 | - |
| 必要なもの | ・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 ・1ヶ月分の保険料 | ・健康保険の資格喪失がわかる証明書 (退職証明書や離職票でも可) ・各市町村の定める届出 ・印鑑 | - |
| 利用できる期間 | 最長2年間 | - | - |
日本は国民皆保険制度のため、全く保険に加入しないのは許されず、いずれかには加入する義務があります。なお、離職期間が1日も発生しない場合、切り替えは不要です。転職先に入社後、会社に手続きを進めてもらい、完了後に新しい健康保険証を受け取れます。
年金保険の切り替え手続き
退職し、転職までに期間が空く場合、国民年金への切り替え手続きも必要です。具体的な手続きは、以下の通りです。
| 手続きの期限 | 退職の翌日から14日以内 |
| 手続きの場所 | 市区町村役所・役場の国民年金窓口 |
| 必要なもの | ・年金手帳 ・退職日が証明できる書類 (離職票や退職証明書でも可) ・印鑑 |
国民年金の被保険者には、次の種類があります。
- 1号被保険者
20歳以上60歳未満の個人事業主・自営業者・農業者・漁業者など、学生、フリーター、無職の方 - 2号被保険者
厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する会社員、公務員など - 3号被保険者
2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)
退職したその月中に、転職先に入社する場合には、国民年金への切り替えは不要で、転職先において厚生年金への加入手続きを行うこととなります。なお、独立して個人事業主になったり、起業して雇用主になったりする場合には、国民年金に切り替えることとなります。
ハローワークで失業保険の手続きをする
離職票を受領したら速やかに、最寄りのハローワークで失業保険の手続きをしましょう。
失業保険の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年間となっています。そのため、より長い期間受給するには、できるだけ早く手続きを進めるのがお勧めです。
「失業保険をもらう条件と手続き」の解説

未払いの金銭がないか確認する
会社に、未払いの金銭がある場合は速やかに請求すべきです。未払いがないかどうか検討すべきものは次の3種類です。
給料については3年、退職金については5年の時効が存在するため、速やかに検討しましょう。特に、残業代の証拠を会社に破棄される可能性もあり、速やかな対処を要します。未払いの残業代請求は早ければ早いほどよいです。既に退職済みなら、会社からの報復行為に怯える必要もありません。
退職金も、不当に不支給となったり減額となっていたりするとき、差額を請求できます。円満に退職できなかった際に起こるトラブルですが、理由のない減額は許されません。解雇の場合、30日前に予告されていなければ、不足する日数分の解雇予告手当を請求できます。
「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

退職後にしばらく無職となる場合に必要な手続き

次に、退職後にしばらく無職となる方にとって、必要な手続きを解説します。すぐに転職先が決まらず、離職期間が長くなりそうなときには、やることが増える可能性があるので注意してください。
確定申告をする
退職した年中に、新しい会社に就職しない場合には、翌年に所得税の確定申告をする必要があります。確定申告は、翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間が期限となるのが原則で、居住地を管轄している税務署に、確定申告書を提出して行います(この際、前の会社の発行する源泉徴収票が必要です)。
次の転職に備えて資料を保管する
しばらくは無職だとしても、転職活動を再開した際には、前職から交付された様々な資料の提出が求められます。そのため、当分は職につかないとしても、本解説における書類は退職後も大切に保管しておくのが重要です。
なお、年内の転職に成功した場合には、次の就職先に年末調整をしてもらうため、源泉徴収票の提出が必須となります。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職する「前」にやるべきでないか検討する

今回は、退職したらやることを解説しました。
しかし実際は、これらのことの多くは退職「前」でもすることができます。むしろ、円満退職の場合、最終出社日から退職まで相当期間が空くこと多いもの。少しでも早く着手し、できることから済ませるべきです。
退職の時点とは「労働契約の終了時」のことを言います。ただ、それより前に、退職届を出したり、退職合意書を結んだり(最悪は、解雇を予告されたり)など、少なくとも将来会社を辞めることについては、少し前から決まっているのが通常です。
自己都合の退職でも、会社都合の退職でも、即日解雇などよほど特殊なケースでない限り、退職前から準備を進められることに変わりはありません。
退職を決断したら、退職「前」に片付けておけることをご検討ください。なお、次のことは、むしろ積極的に、退職「前」にしておくべきです。
- 業務の引き継ぎ
業務の引き継ぎもまた「業務」であり、給料が払われる退職前にすべきです。
(※ 参考:引き継ぎが間に合わない時) - 有給休暇の消化
有給休暇は「休む権利」であり「給料をもらう権利」ではありません。退職前(つまり在籍中)でないと消化できず、未消化のまま残すのは損です。
(※ 参考:退職前の有給消化と買い取り) - 貸与品の返却
貸与品は会社の所有物で、パソコンやスマホなど高価なものもあります。顧客情報など企業秘密が記録されており、返却が遅れると紛争の火種になりがちです。
(※ 参考:貸退職時の貸与品の返却) - 私物の引き取り
会社にある私物は退職前に引き取らなければなりません。直接取りに行くのが難しい状況なら、郵送や処分を依頼する方法もご検討ください。
仕事を続けながら準備も並行して行うのは辛いかもしれませんが、退職後にやるべきことができるだけ少ない方が、スムーズに退職することができます。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職後に「やるべきでないこと」について
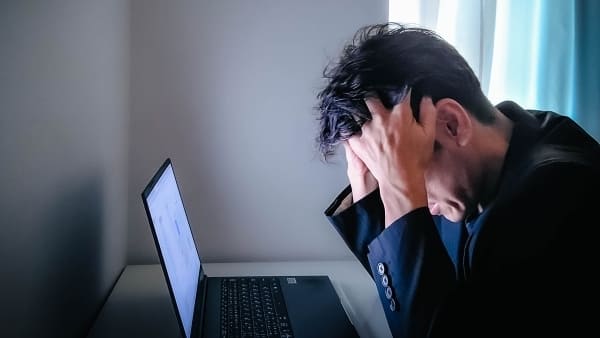
以上は、退職したらやるべきことの解説でしたが、逆に、退職後に「やるべきでないこと」にも目を向ける必要があります。例えば、次のケースを想定してください。
- 退職後の競業避止義務を定める誓約書にサインした場合
禁止された範囲の競業行為は、退職後もすべきではない。
(参考:誓約書を守らなかった場合) - 同業他社に転職する場合
前職の企業秘密を開示、漏洩すべきではない。 - 不当解雇を主張して争う場合
退職金、解雇予告手当を受け取るなど、解雇を認めたと受け取られる行為をすべきではない。
(参考:不当解雇を争う場合の禁止事項) - 転職先にリファレンスチェックの実施を求められた場合
経歴詐称をしてはならない、無限定に同意をすべきではない。
(参考:違法なリファレンスチェックの断り方)
特に、円満退職でないケースでは、やるべきでないことが多いため、注意を要します。
「不当解雇を争う間も再就職してよい理由」の解説

退職後やることのリスト
最後に、退職後やることのリストについて、まとめて紹介しておきます。仕事を退職した前後でやるべきことを見逃さず、順番に進めていくチェックリストとして活用してください。
まとめ

今回は、退職したらやることの順番、手続きや、そのポイントを解説しました。
退職は労働者にとって一大決心であり、退職の理由によってはかなり大きな負担にもなります。退職したらやることを理解し、できるだけ早く進めることは、退職後の生活の安定に繋がります。可能な限り、退職前から準備を進め、いざというとき慌てないようにしておきましょう。
特に、退職したらすべき行政手続きを速やかに進め、メリットを不足なく受け取っておくべきです。また、会社の対応に違法な点があるなら、責任追及しなければ損する危険があります。不当解雇や残業代の未払いなど、不満があるなら泣き寝入りせず、弁護士にご相談ください。
【退職とは】
【退職時の注意点】
【退職できないとき】
【退職金について】







