仕事中、どうしてもうとうとしてしまうことがあります。
ランチ後など、少しだけ居眠りしてしまおうという誘惑に負ける方も。
睡眠は生理現象、仕事中とはいえ「絶対に寝ない」というのは難しいかもしれません。
しかし、仕事中の居眠りは、最悪はクビ、つまり解雇の理由となる危険があります。
 相談者
相談者前夜遅くまで飲んでいて、会議中に寝てしまった
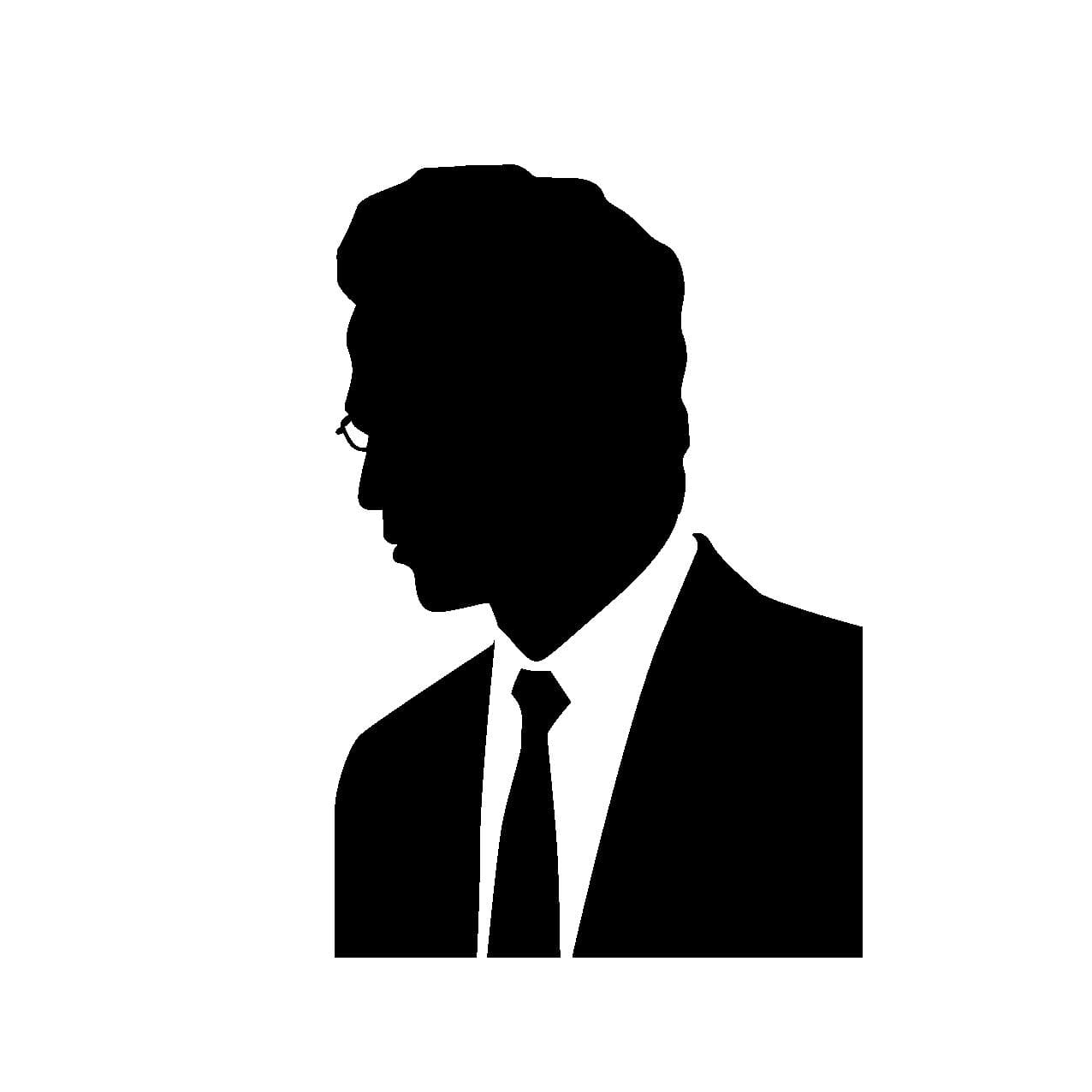 相談者
相談者会社で寝てたのが上司にバレ、クビだといわれた
こんな甘い考えだと、勤務中の居眠りの大きなツケを負うでしょう。
誰も見ていないと思っても、会議室で寝ていたのが、会社にバレるケースは多いです。
解雇までされずとも、居眠りが理由で評価が低下したり懲戒処分を受けたりするケースもあります。
「同じ給料なのに居眠りしてサボっていた」と不公平感を抱かせるリスクもあり、発覚すれば厳しい処分を検討せざるをえないのが、居眠りトラブルの怖いところ。
今回は、仕事中の居眠りでクビになってしまった時の対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 仕事中の居眠りは、職務専念義務違反であり、人事処分・懲戒処分の対象
- 仕事中の居眠りで解雇されたとき、重大でないなら、不当解雇だとして争える
- 居眠りへの注意が、ハラスメント的に狙い撃ちでされるケースがある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【解雇の種類】
【不当解雇されたときの対応】
【解雇理由ごとの対処法】
【退職勧奨への対応】
【不当解雇の相談】
仕事中の居眠りが引き起こす労働問題とは

仕事中に居眠りしていた場合には、その時間に本来すべき業務をしていなかったことになります。
労働者は、雇用契約を結ぶことで、定められた勤務時間には労働する義務を負います。
つまり、仕事中の居眠りは、「約束した労働をしていなかった」ということを意味します。
そのため、居眠りの時間が長ければ長いほど、業務への支障が大きいといえます。
雇用契約を結ぶ労働者は、勤務中は業務に専念しなければなりません。
これを「職務専念義務」と呼びます。
居眠りして寝てしまっていては、職務専念義務違反なのは明らかです。
さらに、居眠りは、寝ていた労働者だけの問題ではありません。
ある労働者が居眠りをして仕事をサボっていたと広まれば、会社全体のモチベーションにかかわります。
他の社員の模範となるべき社長や管理職が居眠りしていたとなると、士気の低下にもつながります。
労働問題と、その解決方法は、次の解説をご覧ください。

仕事中の居眠りを理由にされる不利益な処分

仕事中の居眠りが、してはいけない行為だと理解できたら、次にどんな処分が予想されるか説明します。
あらかじめ、受ける制裁を知っておくことで、労働者側でも対処がしやすくなります。
なお、以下のいずれの処分になるかは、居眠りの悪質性の程度によっても使い分けられます。
バランスを損ねる、釣り合いのとれない処分が下されたら、会社と争うのも検討してください。
居眠りした時間の給料が控除される
労働者の給料は、時間によって決められます。
不当に減らすのは違法ですが、「働いていない時間の給料を控除する」のは許されます。
このことを「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼びます。
仕事中に居眠りした時間があまりに長いと、1日の欠勤扱いとされる可能性もあります。
人事評価が下げられる
仕事中の居眠りは、勤務態度の不良として、人事評価でマイナスに扱われるのは当然。
これによって、ボーナスカットされたり減給されたりするおそれもあります。
「不当な人事評価」の解説

懲戒処分を下される
仕事中の居眠りは、勤務態度の不良であるとともに、企業秩序違反でもあります。
他の社員のモチベーションを低下させ、社内の風紀に違反しているからです。
再三の注意にもかかわらず居眠りが続くとき、懲戒処分を下される不利益があります。
懲戒処分は、まずは軽度の戒告・譴責などが適していますが、改善の兆候が見られないと減給、降格、出勤停止など、重度の処分となることもあります。
なお、居眠りは故意ではなく、過失、つまり、健康管理の不注意などが原因のことも。
このとき、意図的な遅刻や無断欠勤と比べれば、多少は軽い処分にすべきと考えられます。
懲戒処分の種類と対処法は、次に解説します。
解雇される
もっとも、長時間の居眠りが常態化し、まるで仕事にならない場合、「職務を遂行する能力が欠如している」と判断され、解雇されてしまう危険があります。
しかし、居眠りは、必ずしも能力不足などとは結びつきません。
たまたま居眠りをしていたのを、過度に強調されるなら、不当解雇の可能性があります。
勤務態度が悪いとして解雇された時の対応は、次に解説します。

仕事中の居眠りでクビになった時、不当解雇を争えるケース

仕事中に居眠りするのは、労働者にとってリスクある行為だと解説しました。
しかし、居眠りが理由なら不利益な処分、解雇もしかたないとあきらめるのは、まだ早いでしょう。
というのも、仕事中の居眠りが理由でも、「不当解雇」になるケースがあるからです。
不当解雇なら、労働審判や訴訟で争って撤回してもらったり、金銭解決したりできます。
居眠りに対する処分ないし解雇が、不当処分、不当解雇となる例について、解説します。
不利益な処分の根拠がない場合
まず、労働者にとって不利益な処分をするときには、根拠が必要です。
特に、懲戒解雇を含む懲戒処分は、あらかじめ雇用契約書ないし就業規則に定め、処分理由と処分内容を決めておかなければ、処分そのものができません。
居眠りを理由に不利益な処分をされたら、根拠規定があるか確認してください。
処分の根拠がないときは違法であり、効力を生じません。
居眠りは「勤務態度の不良」、「職務怠慢」などの定めに含まれるケースが多いでしょう。
「居眠り」が懲戒処分事由、解雇事由として明示まではされないことも。
このとき「その他、従業員として適性を欠く行為」などの一般条項に含まれるか、争いがあります。
少なくとも、列挙された他の理由と同じくらい悪質な居眠りでなければ、一般条項に含まれるとは解釈されません。
解雇に相当性がない場合
解雇は、労働者の職を奪う、とても重い処分。
生活の維持にかかわる重大な不利益を与えますから、厳しく制限されます。
解雇は、解雇権濫用法理のルールにより、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でない限り、違法な「不当解雇」となり無効です(労働契約法16条)。

仕事中の居眠りが、いけないことであるというのは争いない事実でしょう。
つまり、仕事中の居眠りは、「客観的に合理的な理由」には当たると考えられます。
しかし、必ずしも「社会通念上の相当性」の要件まで満たすものばかりではありません。
仕事中の居眠りでクビにしたとき、解雇が相当かどうかは、悪質性がポイント。
問題となった居眠りの、次のような点が考慮されます。
- 居眠りが、解雇という重大な処分に値するほど悪質か
- 居眠りが、業務に大きな支障を与えたかどうか
- 何度も繰り返し行われたか
- 反省しているかどうか
- 注意指導し、改善の余地が見られたか
軽い居眠りや、たった1度だけのあやまちで解雇するのは、違法です。
懲戒解雇を不当だと争うとき、次の解説をご覧ください。
居眠りが会社の責任である場合
居眠りが、前夜の飲み会やゲームのやりすぎなど、労働者の責任の場合、後ろめたいでしょう。
しかし、仕事中の居眠りのなかには、会社に責任があるケースもあります。
会社は、労働者が健康に働けるよう配慮する義務を負います(安全配慮義務)。
安全配慮義務違反だと、労働者の健康管理は、労働者だけでなく会社にも責任があります。
「居眠りが会社の責任である」といえるのは、例えば次のケース。
会社の責任で居眠りしたなら、労働者に落ち度はありません。
居眠りせざるをえない状況に追い込みながら、一方で「居眠りしたから解雇だ」というのは不当。
したがって、こんなケースでは、不当解雇となる可能性が高いといえます。
なお、労務管理のずさんな会社で長時間労働が起こると、残業代が正しく払われないおそれもあります。
会社の責任で健康被害が生じたら、それは労災。
労災にあったら、安全配慮義務違反を理由に、会社に慰謝料請求できます。

仕事中の居眠りを理由とする不当な処分への対処法

仕事中に居眠りするデメリットを理解いただけたでしょう。
しかし、一方で、解雇や懲戒処分など、不当な処分とされるのは違法なケースもあります。
人事処分も懲戒処分も、これに相当するほど悪質な問題があってはじめてできるからです。
そこで最後に、仕事中の居眠りを理由に不当な処分を受けてしまったとき、会社と争う方法を解説します。
「寝ていない」と反論する
そもそも、「仕事中に居眠りしていた」という会社の認定自体が誤っているケースもあります。
社長に嫌われていることが理由で、ちょっと下を向いて考え込んでいたのが「居眠り」と見間違えられ、厳しく問い詰められてしまうケースもあります。
こんなとき、「寝ていない」と断固として反論すべきです。
寝ていないのに「居眠りしていた」と指摘し、「やる気のない社員」とレッテルを貼るのは職場いじめ。
つまり、違法なハラスメントの疑いの強い行為です。
パワハラにあったら、証拠収集のため録音が大切。
「仕事中」の居眠りではないと反論する
労働者が、会社の指揮命令に従うのは、労働時間内に限られます。
つまり、始業と終業の間で、休憩時間を除いた時間(適切な残業命令をされた時間を含む)。
そのため、労働時間外なら、たとえ会社にいても、寝ていることを責められはしません。
例えば、大切な会議で寝てしまわないよう休憩時間に仮眠をとることは、悪いことではありません。
したがって、居眠りはしたが「仕事中ではない」という反論も有効です。
休憩時間が短かったり、ましてや存在しなかったりするのは違法です。
詳しくは、次に解説します。
居眠りは悪質でないと反論する
仕事中の居眠りでも、ちょっとうとうとするくらいは誰にでもあります。
寝ていた時間が短い、回数が少ないなど、解雇するほど悪質でないという事情も、不当処分への反論になります。
居眠りは会社の責任だと反論する
居眠りをしたのが事実でも、労働者の落ち度のないケースもあります。
その典型例は、前章で解説した「会社に責任がある場合」です。
「仕事が忙しすぎて睡眠がとれず、ついうとうとしてしまった」というだけなら、解雇は重すぎ。
不当解雇の可能性が高いでしょう。
このとき、業務が理由で対象不良になったら労災の可能性があります。
また、体調不良や病気が理由の居眠りなら、すぐ解雇するのではなく、まずは休職として様子を見る対応が適切なケースもありえます。
病気なのに解雇されてしまったら、次の解説をご覧ください。
解雇の撤回を求める
仕事中の居眠りを理由にした解雇が、違法な不当解雇の可能性が高いなら、撤回を求めて争います。
まず、交渉で撤回を求め、聞いてもらえないときは、労働審判、訴訟といった法的手続きを利用します。
解雇の理由となった居眠りが事実無根なケースはもちろん、過大な処分だという場合も同様です。
争いが長引き、裁判に発展しそうなときは、処分直後から弁護士に相談するのがお勧めです。
解雇トラブルの解決には、撤回させる方法、金銭解決の方法などがあります。
詳しくは、次の解説をご覧ください。
弁護士に相談する
居眠りをめぐる戦いは、ただ「仕事中に寝ていた」というだけでなく、根深い問題のこともあります。
仕事で活躍し、正当に評価されていれば、少しうとうとしたくらいで解雇されはしないでしょう。
仕事中の居眠りを理由に解雇や懲戒処分されてしまうケースは、それ以外にも、労働者自身がとても不当な扱いを受けている可能性があります。
そして、その不当な扱いが明らかにされないことも。
こんなとき、居眠りを理由に解雇されてはじめて気づくのでは遅いです。
できれば早めに、弁護士に相談し、対策を練っておくのがお勧めです。
労働トラブルの解決は、労働問題に強い弁護士におまかせください。
労働問題をまかせる弁護士の選び方を知ってください。

まとめ

今回は、仕事中の居眠りで、労働者が負ってしまうリスクについて解説しました。
居眠りは、ほんのちょっとでも、バレてしまえば大問題。
懲戒処分になるほか、最悪はクビ、つまり解雇されてしまいます。
仕事中なのに会社で居眠りすれば、職務怠慢といわれてしまいます。
勤務態度が悪いといわれ、低い評価を受け、昇進に響くおそれもあります。
ただ、業務の多忙や長時間労働など、会社側に問題のあるケースもあります。
なるべく仕事中に寝ないよう健康管理するのは当然。
しかし、やむをえない理由で居眠りし、クビになったとき、「居眠りせざるをえないほど多忙なのはつらい」と疑問に思うなら、不当解雇の可能性があります。
- 仕事中の居眠りは、職務専念義務違反であり、人事処分・懲戒処分の対象
- 仕事中の居眠りで解雇されたとき、重大でないなら、不当解雇だとして争える
- 居眠りへの注意が、ハラスメント的に狙い撃ちでされるケースがある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【解雇の種類】
【不当解雇されたときの対応】
【解雇理由ごとの対処法】
【退職勧奨への対応】
【不当解雇の相談】






