取引先との営業や打ち合わせ、接待の場は、セクハラが起こりやすい状況にあります。
「不快だ」「行き過ぎではないか」と思っても、関係性を壊すのを恐れて我慢する人もいます。特に、相手が取引先の社長だと、「セクハラだ」と指摘すれば、仕事そのものがなくなる懸念もあり、違和感を飲み込んでしまう人は少なくありません。
取引先からのセクハラは、立場上受け身にならざるを得ず、被害が表面化しづらい特徴があります。現在、職場のセクハラ対策は会社の義務とされ、制度整備が進む企業も多いですが、加害者が社外の人だと被害の声が上がりづらく、対応が遅れるケースは後を絶ちません。
しかし、取引先が相手でも、セクハラが許されることはありません。被害を受けた労働者は我慢をせず、加害者個人や取引先、勤務先の会社などに責任追及することを検討できます。
今回は、取引先からのセクハラ問題と対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 取引先や顧客との営業・接待では、力関係からセクハラの泣き寝入りが起こる
- セクハラの具体例として、取引を条件とした性的要求や発言などがある
- 取引先の加害者だけでなく会社、勤務先にも責任が生じる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
取引先からのセクハラ問題と判断基準

取引先とのやり取りの中で、「セクハラなのではないか」と思うケースがあります。
セクハラは、社長や上司から受けるものに限られません。業務に関連して行われた性的言動による嫌がらせは、加害者が取引先や顧客であってもセクハラに該当します。
一般的なセクハラの例は、人事評価や労働条件などの不利益をちらつかせて脅したり、ボディタッチや発言で職場環境を悪化させたりといったケースですが、これは、指揮命令や主従の関係のない社外の人には当てはまりません。
しかし、相手が社外だからといって軽視するのは問題です。
むしろ、取引先からのセクハラの特徴は、社内の指揮命令関係がなくても、「契約を切られるかもしれない」「仕事を発注してもらえないかもしれない」といった立場上の不安が、断りづらさを生んでいる点にあります。
このような顧客や取引先からの暗黙の上下関係も、セクハラの原因となります。社外であれば対等かというと、決してそうではありません。
取引先や顧客の言動に違和感を感じたとき、「セクハラかどうか」の判断は、次のポイントを参考に検討してください。
- 仕事(取引)とは無関係な性的発言かどうか。
- 不快であると指摘した後も継続していないか。
- 取引継続などを理由として断りづらい立場を利用されていないか。
これらの要素を満たす場合、セクハラの可能性を検討してください。「相手に悪気があるか」「冗談のつもりかどうか」といった点は、正当化する理由にはなりません。
また、取引先という立場を利用したハラスメントは、「顧客」の優位性を背景にしたハラスメント、つまり、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の側面も併せ持ち、放置すれば被害は更に深刻化していきます。
「カスハラの違法性」の解説

取引先からのセクハラの具体例

次に、取引先からのセクハラについて、具体例で解説します。
取引先からのセクハラは、性的要求、身体的接触といったものだけでなく、取引関係や立場を利用して分かりにくい形で行われる点が、判断をより難しくしています。特別な場面だけでなく、営業活動や日常のやり取りの中でも起こるので、違和感を覚えたら、立ち止まってチェックしてください。
取引や契約をちらつかせるセクハラ
取引先という立場を利用して、新規契約や取引継続を条件にするセクハラがあります。
このような行為は非常に断りにくいため、最も悪質であり、違法性も強い問題です。例えば、次のような具体例があります。
- 性行為をしなければ取引を中止すると脅される。
- 契約締結や更新を条件に、性的な要求を受ける。
- 「君のことが好きだから契約しよう」と好意を示す。
- 肉体関係を拒否したところ、契約を打ち切られた。
明確に言葉にしたり交換条件として示したりしなくても、被害者側が取引を盾にした圧力を感じて、やむを得ず応じてしまったのであれば、セクハラに該当する可能性が高いです。
業務を装った執拗な接触
一見すると仕事の延長に見えても、実際には私的な関係を求めるケースもあります。このような状況は非常に断りづらく、執拗に連絡が続くケースもあります。
- 「打ち合わせ」と称して頻繁に食事や飲みに誘われる。
- 業務と無関係な連絡が、土日や夜間に頻繁ある。
- 断っているのに、プライベートの誘いが続く。
加害者が「仕事の一環である」と主張していても、実際には業務上の必要性が乏しく、断りづらさを利用しているものが多く見られます。
担当者からの発言によるセクハラ
取引先との打ち合わせや訪問時に、セクハラ発言を受けるケースもあります。たとえ社外の人でも、容姿や身体的特徴について言及するのは不適切であり、違法なセクハラとなります。
- 商談中に体型や胸について発言される。
- 容姿をからかう。
- 逆に「きれいだ」「かわいい」などと高評価する言葉を頻繁に投げかけられる。
- 性的な冗談や下ネタを聞かされる。
たとえ一度きりだとしても、性的な発言については業務と全く関連性がないのは明らかであり、違法なセクハラに該当します。
接待や会食の場での身体的接触
接待や懇親の場では、立場の差に加えてアルコールが入ることで、更にセクハラが起こりやすくなっています。例えば、次のようなケースがあります。
- 酔った取引先から身体を触られる。
- 性的な話題を強要される。
- 女性社員の性的魅力を当然のように扱われる。
- 女性だからといって盛り上げ要員にされている。
「接待だから」「場の雰囲気だから」と正当化されがちですが、たとえ接待であってもセクハラが許されることはありません。
「接待強要によるセクハラ」の解説

取引先からのセクハラ被害にあった場合の対処法

次に、取引先や顧客からセクハラ被害を受けた場合の対処法を解説します。
特に、相手が会社にとって重要な取引先や大口顧客であるほど、「会社に相談しても本気で対応してくれないのではないか」と不安で我慢する人も多いです。むしろ、取引先が相手だからこそ、自分の身は自分で守るという意識を強く持って対応してください。
とはいえ、「直ちに大事にして立場をなくしたくない」と思う人も多いことを踏まえ、段階ごとに軽い対応から解説します。
違和感を我慢せずに伝える
「取引先だから強く言えない」と感じてしまうのは無理もありません。
しかし、取引先や顧客であってもセクハラは違法であって、我慢する必要はありません。エスカレートする前に違和感を我慢せず伝えることが、対処法のスタート地点となります。
セクハラは違法であり、重要な取引先であっても決して許されません。取引先からのセクハラによって精神的苦痛やストレス、身体的な被害を受けた場合、不法行為(民法709条)に該当すれば、慰謝料請求などの損害賠償を請求できます。態様が悪質な場合、名誉毀損罪や侮辱罪、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪といった刑事責任も問題になり得ます。
したがって、違和感を覚えた時点で我慢しないこと、そして、その場で強く拒否するのが難しくても、まずは「不快である」としっかり伝えることが必要となります。
いきなり取引先に強く出るのが難しいときは、自分の違和感が法的にどう評価されるのかを知るために、弁護士の無料相談を活用してみてください。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

取引先や接待の場でも性的な配慮は不要
取引先との関係を良好に保つことは重要ですが、性的な配慮は不要です。
「円滑に取引したい」「愛想よく振る舞うべきだろうか」と考える人は少なくありません。互いに常識的な範囲ならコミュニケーションは良好な方がよいでしょうが、たとえ取引先対応や接待であっても、性的な配慮を求められるのは不適切です。
業務上の関係では、求められるのは仕事としての対応であり、成果です。性的な発言に笑って応じたり、身体的な接触を受け入れたりする必要は全くありません。「営業だから」「場の空気を壊したくない」といった理由で我慢を重ねると、取引先も増長し、かえってセクハラが悪化します。
また、勤務先においても、「女性社員の方が場が和む」「接待向きだから」といった発想があるなら、社員を性的役割で評価する考え方であり、問題ある性差別だと考えるべきです。
「職場の男女差別の例と対応方法」の解説

拒否が難しい場合は関わり方を変える
取引先からのセクハラを直接拒否するのは怖いと感じる人も多いでしょう。
勤務先にも問題があると、セクハラを拒絶して取引に支障が出たことについて、本来なら守られる被害者が、逆に責められてしまうケースもあります。
このような懸念がある場合、無理に相手と衝突せず、関わり方を見直すのも有効な対処法です。例えば、次の対応によって、セクハラが起こりにくい環境を作ることができます。
- 二人きりで会う状況は避け、男性社員に同行してもらう。
- 打ち合わせは日中に、酒食を挟まずに行う。
- 相手の魅力を褒めすぎない。
- 対面で会うときは露出度の少ない服装とする。
- 業務連絡はメールやチャットで記録に残す。
- 業務時間外の連絡や私的な誘いには応じない。
これらの対応は決して業務から逃げているわけではありません。自分の身を守りながら仕事を続けるための手段なので、遠慮をする必要はありません。軽度のセクハラなら、距離を取られたというサインに気付いた取引先が、自然とセクハラを止めてくれる可能性もあります。
早い段階で勤務先に情報共有する
取引先からのセクハラ被害は、できる限り早い段階で勤務先の会社に情報共有しましょう。
加害者が取引先であっても、業務の一環として被害を受けている以上、勤務先の会社が対応すべき問題です。適切に対処してもらえるなら、勤務先の指示に従ってセクハラ防止に努めましょう。取引先との関係悪化を避けるための我慢も、素早く対応してくれる勤務先なら「不要だったのに」という可能性もあり、一人で抱え込んではいけません。
情報共有しなければそもそも被害に気付かれず、二次被害が生じかねません。
- 取引先から嫌がらせでクレームを言われ、対応が不適切だったと評価される。
- 会社に事情を共有しておらず、後から説明が難しくなる。
- 不適切な性的関係を積極的に築いたのではないかと疑われる。
- 顧客扱いのスキルがないとして、能力不足と評価される。
- 重要な顧客の機嫌を損ねたとして問題視される。
このような誤った評価を重ねないためにも、初期の段階で共有しておくことが重要です。会社に相談しておくことで、「会社がすべき取引先対応」と「労働者個人がすべき行動」の範囲を明確にして、適切な対処を取ることができます。
「セクハラの二次被害の対策」の解説

自社や取引先の担当変更を打診する
自社側や取引先側の担当変更を打診することも、軽度のセクハラのうちなら有効です。
取引先からのセクハラは、特定の担当者同士で密接な関係を築くことによって起きているケースが多いです。そのため、担当者や体制を見直せば、問題が解消することも多いのが実情です。会社に情報共有し、協力が得られれば、次のような方法を検討することができます。
- 自社内で担当を交代してもらう。
- 上司も同席して担当してもらう。
- 取引先に対して担当者の変更を求める。
- 打ち合わせの際に必ず複数人で対応する。
この対応なら、取引自体を壊すことなく、あなたの被害を食い止めることができます。
勤務先の会社としても、被害が深刻になってから責任追及をされるより、担当変更という穏便な策を取った方が業績にも影響しないため、対応してもらえる可能性は高いです。
「セクハラの相談窓口」の解説

可能な限り証拠を保全する
勤務先の会社が適切な対処をしない場合、自衛をしなければなりません。
実際、残念ながら相手が取引先や顧客であるということで「社員が我慢すればよい」という対応を取る会社は少なくないのが実情です。
今後、悪化した場合に弁護士に相談したり、法的な措置を講じたりすることを考えると、セクハラ被害を裏付ける証拠を残しておくことが非常に重要です。取引先のセクハラは、人目に付かない場所で行われたり、「仕事の延長」と言い逃れしやすい状況で行われたりします。後から被害を訴える場合も、客観的な証拠がなければ、事実関係の立証が難しく、信用されないおそれがあります。
そのため、接待や営業の場での会話、電話やオンラインのやり取り、業務中に受けた不適切な発言などは、可能な限り録音して記録に残しておきましょう。特に、頻繁に接待の場に呼ばれたり、食事の誘いを受けたりする場合、セクハラの起こりそうな場面ではボイスレコーダーやスマートフォンの録音を準備して臨むようにしてください。
弁護士に相談して法的措置を検討する
取引先が相手で、勤務先に十分な対応をしてもらえない場合、弁護士に相談してください。
また、セクハラ加害者となった取引先が個人事業主やオーナー社長だった場合、勤務先からの注意や働きかけが行われても考えを変えず、セクハラ被害が解消されないケースもあります。
この状況では、いよいよ被害者自身が次の一手を考える必要があります。損害賠償請求などの法的手段が必要となりますが、法律知識や経験を要するため、労働者一人で進めるのは現実的ではありません。また、取引先や会社との交渉も、弁護士に任せて精神的苦痛を取り除くべきです。
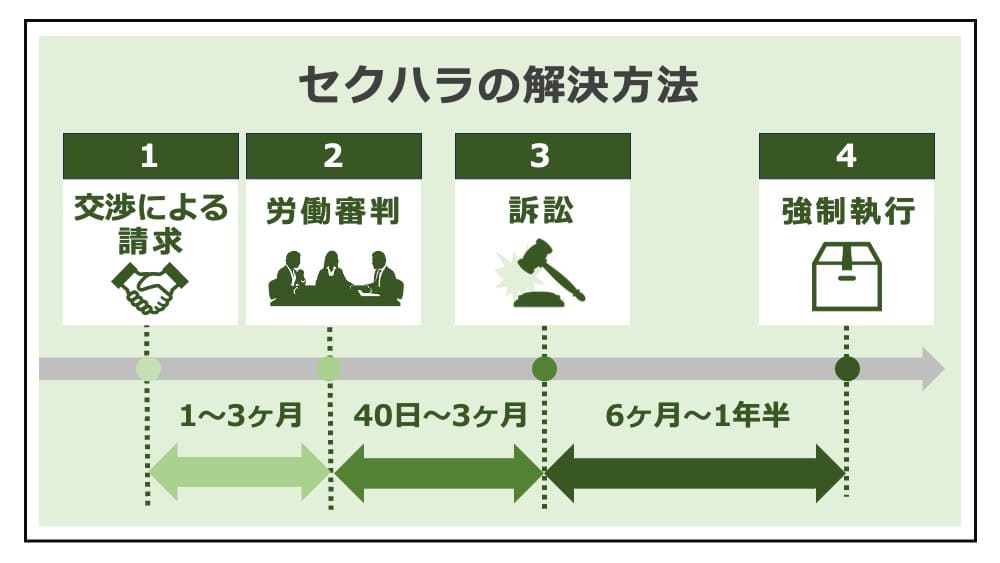
労働問題に精通した弁護士に相談すれば、状況を整理した上で、法的にどのような責任を問えるか、どのような手段で責任追及すべきかについて、具体的なアドバイスを受けることができます。弁護士への相談は、必ずしも裁判を前提とするものではなく、証拠収集の助言や後方支援なども可能なので、セクハラが起こった直後など、早期の段階で行うのがお勧めです。
「セクハラ問題に強い弁護士に相談すべき理由」の解説

取引先のセクハラの責任は誰が負うのか

最後に、取引先のセクハラ問題について、誰に責任があるのかを解説します。
取引先との間でセクハラ被害が生じると、責任の所在が分かりにくく、責任転嫁が起こりがちです。加害者本人、被害者の所属する勤務先、取引先の会社のいずれにも責任が生じ得ることについて、法的な観点から整理して解説します。
セクハラ行為をした取引先担当者本人の責任を追及する
最も基本となる責任は、セクハラ行為者である取引先担当者本人の責任です。
セクハラは、社内で起こるのが典型例ですが、同じ会社に属していなくても嫌がらせは違法であり、不法行為(民法709条)に該当します。不法行為は、①故意または過失により、②権利または法律上保護される利益の侵害があり、③損害の発生と④因果関係といった条件を満たす場合に成立し、その損害についての賠償責任を問うことができます。

セクハラは、被害者の人格や尊厳を侵害する行為であって、この要件を満たすのは明らかです。取引関係であることで会社が及び腰になっていても、法的な責任には全く影響しません。
行為の態様が悪質であれば、名誉毀損や侮辱、身体への接触を伴う場合は不同意わいせつ罪など、犯罪行為となるケースもありますが、刑事責任を問われるのも、行為を行った本人です。
勤務先にもセクハラを防止しなかった責任がある
次に、勤務先がセクハラを防止しなかった場合、その責任を追及できます。
たとえ行為者が取引先の人でも、業務中に発生したセクハラ被害を抑止する責任は勤務先にあると考えられるからです。
これは、男女雇用機会均等法で、職場におけるセクハラ防止の措置を講じる義務が課されていること、会社が従業員に対して健康で安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負うことからも明らかです。
危険を防止すべき「職場」は、オフィス内に限らず、営業先や出張先、取引先オフィスや接待の場でも、業務に関連する場所なら、その安全を確保する責任を負います。
取引先からのセクハラを放置すれば、従業員に精神的苦痛を与え、業務継続が困難になるおそれがあります。そのため、勤務先が被害を把握しながら対策を講じず、これらの義務に違反していると評価される場合、損害賠償を請求できます。
特に、取引先との関係調整は、担当者個人では限界があり、取引先に働きかける、打ち合わせ方法を見直す、担当替えをするといった対応は、勤務先の会社だからこそ取れることです。
「安全配慮義務」の解説

取引先の会社に責任を問えるケースもある
取引先からのセクハラでは、加害者を雇用する取引先会社の責任を問える場合もあります。
特に、セクハラ行為をした担当者が、取引先企業の中で高い地位、重要な権限を有している場合、会社間の関係悪化につながりやすく、ますます被害者が声を上げづらくなります。加害者個人だけでなく会社の責任を問うことで、企業としての適切な対応を迫る方法は、非常に有効です。
法的には、取引先の責任の根拠は、不法行為の使用者責任(民法715条)です。
使用者責任とは、従業員が「事業の執行」に関連して第三者に損害を与えた場合に、使用者(会社)の責任も合わせて問うことができるという考え方です。
この責任を問うにあたり、セクハラ行為が会社の事業と関連して行われたかどうかがポイントとなります。この判断は、外形的に見て事業活動の一環と言えるかどうかで決まり、必ずしも会社の明確な指示までは必要とされていません。
取引先の担当者が行う営業活動や接待は、契約の獲得や継続を目的とした、会社の事業活動そのものです。そのため、営業や接待の場で行われたセクハラは「事業の執行」に該当し、取引先の使用者責任を追及できると考えられます。
したがって、たとえ、「個人的な言動だった」「会社としては関知していない」と主張されたとしても、業務の延長線上で行われた行為であれば、取引先に警告を送ったり、責任追及をしたりするのは効果的な対策となります。
「セクハラ加害者の責任」の解説

【まとめ】取引先からのセクハラ被害

今回は、取引先からのセクハラ問題と、その対処法について解説しました。
セクハラの加害者が取引先や顧客だと、力関係のあって声を上げづらいのが現実です。違和感を抱えたまま我慢をした結果、セクハラ的な要求をエスカレートさせてしまう例は少なくありません。
しかし、加害者が社外だからという理由でセクハラに該当しないわけではありません。職場内のセクハラが違法なのと同じく、業務に関連して起きたことは、場所が社外でも使用者(会社)には労働者を守る責任があります。取引先対応中はまさに業務の一環であり、会社は安全に働ける環境を確保するため、適切な対応をする義務(安全配慮義務)があります。
勤務先が取引先に配慮して十分に動いてくれないとき、一人で抱え込まずに弁護士に相談してください。弁護士なら、利害関係に左右されない中立的な立場で状況を整理して、加害者、取引先、勤務先のそれぞれに対して責任追及をサポートすることが可能です。
- 取引先や顧客との営業・接待では、力関係からセクハラの泣き寝入りが起こる
- セクハラの具体例として、取引を条件とした性的要求や発言などがある
- 取引先の加害者だけでなく会社、勤務先にも責任が生じる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/





