退職したいと伝えたら、給料を減らされてしまうケースがあります。円満に辞めようとして、かなり早めに伝えたにもかかわらず、社長の怒りを買ってしまっては元も子もありません。
 社長
社長どうせやめるのなら、給料は払わない
 社長
社長退職で迷惑かけるのだから減給は当然
このような退職前の減給は、不当である可能性が高いです。退職後は無収入になりますが、「退職予定だから」という理由で退職前も給料を減らされては、生活が成り立たなくなります。会社に迷惑をかけないよう配慮して早く伝えるほど、退職までには期間が残り、給料を減らされる嫌がらせの被害が拡大してしまいます。引き継ぎをしたり有給消化したりといった期間にもらえる給料を減らされては損をしてしまいます。
今回は、もうすぐ退職が迫っているからと給料を減らす「退職前の減給」が違法ではないか、その対応方法もあわせ、労働問題に強い弁護士が解説します。
- もうすぐ退職するからと給料を減らされるのは、違法の疑いが強い
- 退職を理由に減給されたら、減らされた給料を請求できる
- 退職時に、結果的に給料が減ってしまう場合はあるが、労働者保護のため多くの制限あり
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
退職したいと伝えたら給料を減らされる問題とは

まず、退職したいと伝えて給料が減ってしまうケースにどのようなものがあるかを解説します。
長年勤めあげた会社ほど、給料はそれなりの金額になっているはずです。やむを得ない理由で退職するにあたって、退職直前に給料を減らされると、少しでも迷惑をかけまいと早めに退職の意向を伝えたのが、逆にあだとなってしまいます。
辞めるなら給料を下げるといわれるケース
1つ目が「辞めるなら給料を下げる」といわれるケース。
このようなことを言ってくる会社では、
- 「忙しい時期に退職して迷惑をかけた」
- 「頑張っている他の社員と比べて貢献が小さい」
などと、もっともらしい理由付けをして、さも当然のように給料を引いてきます。
しかし、裏には「退職直前の給料がもったいない」というずるい考えしかありません。責任感の強い人ほど、会社の言い分に納得してしまいがちですが、同意なく給料を減らすことはできません。労働の価値は平等であり、退職するからといって価値は下がりません。退職を理由にして、突然に給料を下げるのは違法です。
なお、給料を減らすという脅しで退職を思いとどまらせようという気持ちのある使用者もいますが、違法な在職強要となります。むしろ、違法な減給をするような会社にいつまでも残る必要はなく、さっさと退職を決めた方が身のためです。
退職を理由に降格させられるケース
2つ目が、退職を理由に降格させられるケースです。
減給と同じく、退職をするのは、会社に対する背信であるなどとして、降格を言い渡される例があります。降格されると、就業規則や賃金規程にしたがって、結果的に給料が下がってしまいます。「もうすぐ退職するから」と仕事を減らされ、その結果として給料が下がるケースもあります。
しかし、これまで問題なく働くことができていたなら、退職直前になって降格することもまた、違法の可能性が高いです。不当に仕事を減らすのはパワハラの一種ともなり、このことは、退職直前でも変わりません。
「仕事を与えないパワハラ」の解説

引き継ぎ期間の給料が減らされるケース
3つ目が、引き継ぎ期間の給料が減らされてしまうケースです。
引き継ぎはとても大切な仕事なのは当然ですが、直接売上を生むわけではありません。その結果、「価値が低い」「引き継ぎに出社しているだけ」などと言われ、退職直前の給料を下げられてしまいます。
同意なく不当に退職を早められてしまい、引き継ぎは無償でさせられる例すらあります。しかし、給料を払わずに労働を命じるのは違法であり、したがう必要はありません。業務の引き継ぎも、拘束を受けるなら立派な仕事です。
「退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説

退職後に給料が払われないケース
4つ目が、退職をした後になって、最終給与が未払いとなるケースです。
退職まではきちんと給料が払われていたとしても、油断は禁物です。悪質な会社では、退職後の給料を支払ってこない被害の相談もよくあるからです。退職後、最後の給料が払われないのは、給料を減らされたのと同じことです。払わないわけではないものの、最後の給料のみ手渡しにすることによって、取りに行きづらい労働者があきらめることを期待している会社もあります。
「最後の給料を手渡しとすることの違法性」の解説

退職を理由に給料を減らすのは違法

退職を理由に給料を減らすのは、違法であり、したがう必要はありません。退職直前に給料を減らされたとき、必ず減給を拒否するようにしてください。
給料の金額は、とても大切な労働条件。労働者の生活を支えるとても大切なお金です。そのため、労使の話し合いで、合意しなければ変更できないのが原則です。一方的に給料を下げるのは、「労働条件の不利益変更」にあたり、許されません。
例外的に、退職のタイミングでの減額が許されるケースはありますが、少なくとも上記の問題のように、退職を理由として給料を減らしてくるような卑劣なやり方は、違法だと考えてよいでしょう。
そして、これは退職を直前に控えた労働者でも、同じことです。合意なく一方的に、労働条件を労働者に不利益に変更するのは、原則として違法です。
「労働条件の不利益変更」の解説

退職を理由とする減給を争う具体的な方法
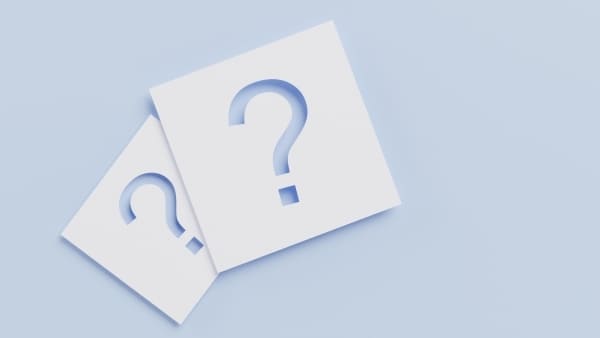
退職による減給を争う方法は、未払い賃金を請求する方法と共通します。具体的には、次の手順で進めてください。
「退職すること」を理由としてブラック企業が給料を減らしてくる、一方的な「減給」のトラブルの場面では、具体的には「給料が満額振り込まれない」という形であらわれます。このような問題は、退職した後で起こることもあります。
退職時の減給は拒否する
退職するからといって給料を減らすのは違法ですから、減給は必ず拒否してください。まだ在職中で、辞めると伝えて給料が少しでも減るなら、すぐに拒絶の意思表示をすべきです。
「減給の違法性」の解説

給料を減らされたら退職まで仕事はしない
しっかり拒否してもなお、会社が給料を払ってくれないなら、仕事をする必要はありません。例えば、引き継ぎ業務分の給料を払わないなら、出社せず、引き継ぎもストップしましょう。内容証明やメールといった証拠に残る形で、「退職までの期間は有給休暇を消化する」と伝えます。そして、有給休暇分すら払われないときには、減らされた分の給料の請求に移りましょう。
「退職前の有給消化」の解説

退職を理由に減らされた給料を請求する
次に、実際に給料が違法に減らされていたら、減った分の給料を請求します。給料を請求する方法は、次のステップで進めます。
内容証明で請求することで証拠化し、交渉で回収を試みます。
労働者保護のために簡易迅速に審理してくれる労働審判は、給料の請求でも効果を発揮します。
最後に、裁判で未払い賃金を請求する方法です。減給の総額が60万円以下なら、簡易裁判所の審理1回で解決する「少額訴訟」を利用できます。
退職時の減給という労働トラブルは、単なるお金の問題だけでなく、退職トラブルの側面もあります。「給料を下げる」という問題が派生すると、「退職させない」「退職金を払わない」といった別の問題に発展してしまうこともあります。労働審判や裁判など法的手続きなら、退職トラブルもまとめて解決できます。
「給料未払いの相談先」「未払い賃金を請求する方法」の解説


退職時に給料を減らされてもしかたないケースもある

「退職を理由に」給料を減らされれば違法です。しかし、一方で、退職時には、結果的に給料が下がってしまうケースが残念ながらあります。最後に、退職時に給料を減らされてもしかたないケースと、その対策を解説します。
これらのケースは「退職を理由に」されたのでなければ適法な例もあります。適法な減給ならば受け入れるしかなく、争うことはできません。
退職者の同意があるケース
退職する労働者の同意があれば、給料を下げることができます。労働条件の不利益な変更も、その労働者の同意があれば可能だからです。
ただし、給料はとても重要な労働条件なので、同意は「真意」からのものである必要があります。少なくとも、同意書もなく、口頭で「はい」といったにとどまるなら、同意があったとまでいえません。文句を言いづらいのをいいことに無理やり給料を下げてくるケースも、同意なしといえるでしょう。労働者側では「同意があった」と言われぬよう、黙ってやりすごすのでなく、必ず拒否の意思を示すようにしてください。
「退職合意書の強要の違法性」の解説

月の途中で退職して給料が日割りになるケース
月の途中で退職するときには、最終月の給料は日割り計算される会社もあります。このとき、労働した日数を日割りで計算して、割合的に払うのは適法です。
ただし、労働した日数分は必ずもらえます。労働した日数分にも満たない給料を「引き継ぎは仕事してないのと一緒だ」「月途中で退職するなど、1ヶ月仕事していないの同じだ」など理由をつけて減らされれば、たとえ月途中の退職でも違法なのは当然です。
会社に損害を与えて退職したケース
退職の理由が、会社に損害を与えたことにあるなら、もらえるお金が下がることもあります。
例えば、業務上のミスで懲戒処分を受け、責任をとって会社をやめる例です。「給料が減らされる」のではなく、会社の損害を請求され「給料と相殺される」と考えられます。場合によっては給料だけでなく、退職金など他にもらえるお金も減ってしまうこともあります。
ただ、たとえ損害賠償請求が可能でも「給料からの相殺」には労働者の同意が必要です。
「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

減給処分のケース
同様に、退職時に労働者の責任を追及するとき、懲戒処分を下すこともできます。まだ退職前ならば、たとえもうすぐ会社をやめるにしても、在職中は懲戒処分にできるからです。
ただし、懲戒処分としての減給処分の場合、減給額には次の制限があります。
- 1回の懲戒処分による減給は、平均賃金1日分の50%以内
- 1ヶ月の懲戒処分による減給の総額は、月額賃金の10%以内
不当な処遇を受けたおそれのあるときは、労働問題に精通した弁護士のアドバイスを受けるのが賢明です。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

今回は、退職の予定であることを理由に、残りの期間について給料を減額されるというトラブルについて解説しました。結論として、退職したいと伝えたことを理由にして給与を減らす行為は、違法の可能性が非常に高いです。
会社側からすれば、今後働き続けることのない社員の給料を、できるだけ安く抑えたいという気持ちでしょう。しかし、「どうせ辞めるなら給料を減らしてやろう」というのは、正当な理由ではありません。ブラック企業の悪質な手口に負けず、未払いの給料を請求してください。
退職直前に減給されてしまった場合、その減給が違法なら、減らされた分の給料は未払いとなり、未払い賃金請求が可能です。労働審判や訴訟といった裁判手続きで請求するにあたり、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- もうすぐ退職するからと給料を減らされるのは、違法の疑いが強い
- 退職を理由に減給されたら、減らされた給料を請求できる
- 退職時に、結果的に給料が減ってしまう場合はあるが、労働者保護のため多くの制限あり
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【退職とは】
【退職時の注意点】
【退職できないとき】
【退職金について】





