LINE(ライン)をコミュニケーションツールとして利用する人は多いでしょう。私生活だけでなく、社内のやりとりもLINEを使う例が増えています。
会社をやめるとき、退職の意思は、面と向かっては伝えづらいものです。LINEで伝えることが許されるなら、退職のハードルを下げられるのではないでしょうか。しかし「退職の意思をLINEで伝えるのは非常識」「対面で説明すべき」といった価値観も根強く残ります。
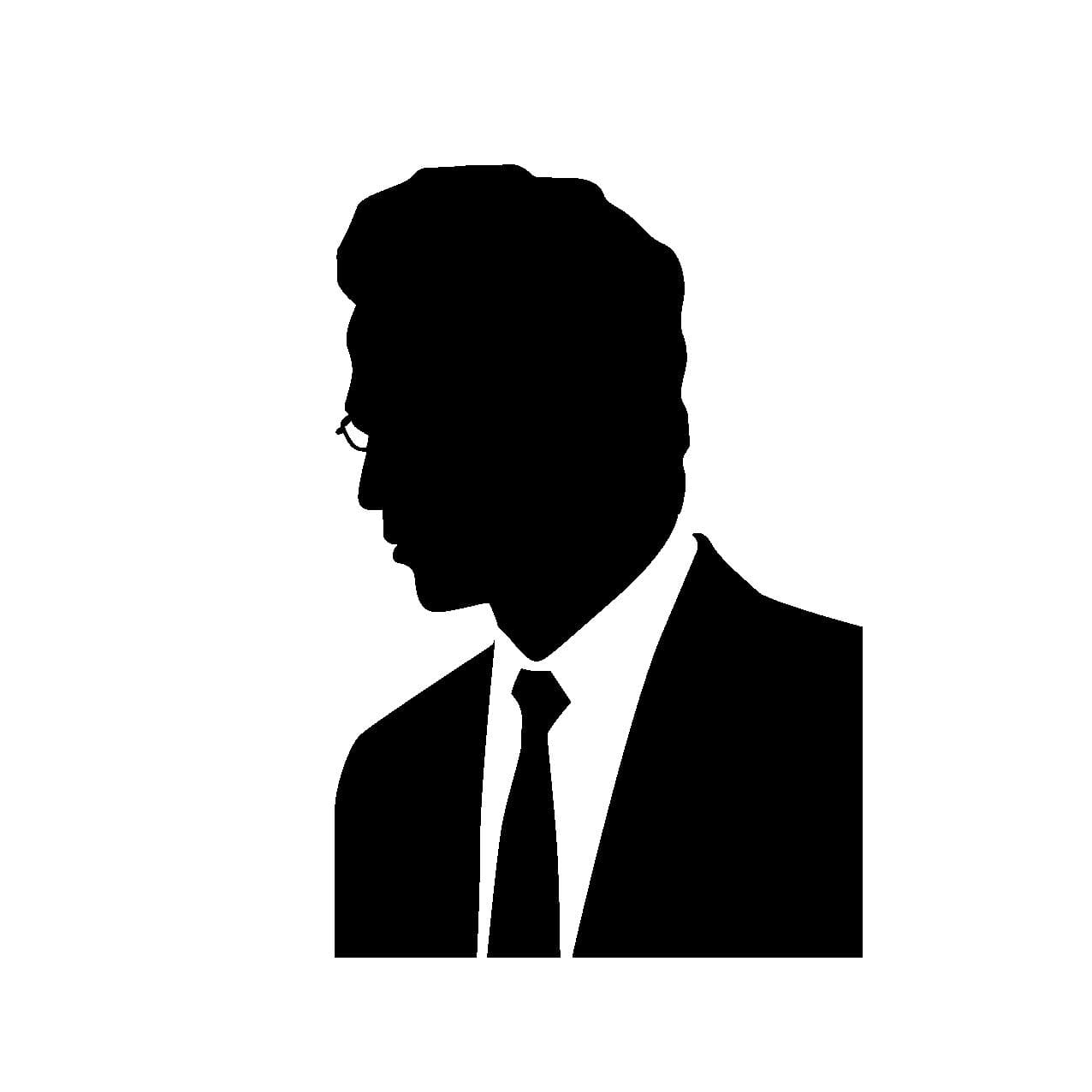 相談者
相談者LINEで退職したいと言ったら出社して謝罪しろといわれた
 相談者
相談者LINEだけで退職するなら、損害賠償を請求するといわれた
ワンマン社長ならなおさら、対面して直接「退職したい」とは言いづらいです。「仕事を辞めたい」と伝える機会に、更にパワハラを受けてしまう危険もあります。
今回は、LINEで退職の意思を伝えるのが有効か、法的観点から、労働問題に強い弁護士が解説します。やむを得ず、LINEで退職を伝えるしかないときにも、できるだけストレスなく、かつ、非常識だと批判されないよう、適切な伝え方も、あわせて紹介します。
- 退職の意思は、LINEで伝えても法的に有効
- 退職時にパワハラや違法な引き止めをする会社からは、LINEで速やかに退職する
- LINEで退職を伝えるときは、軽く見られないよう証拠を保存する努力が必要
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
退職をLINEで伝えるのは、法的に有効

結論からいえば、退職をLINEで伝えるのは、法的に有効な方法です。そのため、「会社をやめたい」「仕事をやめたい」と感じたら、社内の連絡をLINEでしているのであれば、まずはすみやかにLINEで退職の旨を伝えるようにしてください。
初めに、LINEで退職の意思表示を伝えてよい理由について解説します。
退職の意思の伝え方は自由
法律上、退職の意思の伝え方は、自由です。つまり、意思表示の方法に、法律上、決まったルールがあるわけではありません。
退職の意思もまた、どのように伝えてもよく、会社にきちんと伝わりさえすれば、意思表示として有効となるのが原則です。「退職の自由」があるので、「LINEでしか伝えられないなら辞めさせない」というのは違法な扱いです。社長や上司のLINEにトークで直接伝える方法はもちろん、業務連絡のLINEグループがある会社では、そのLINEグループ内で退職の意思を伝えるのも有効です。
「会社がやめさせてくれない」という労働者の相談で、弁護士が退職代行をするときにも、社長が電話や書面、メールなどの連絡を受け付けてくれない(もしくは、できない事情がある)といった場合は、LINEで会社を辞める意思を伝えるケースもあります。
「会社の辞め方」の解説

パワハラの危険があるとLINEで伝えるしかない場合もある
退職の意思を、どうしてもLINEで伝えざるを得ないケースの典型例は、対面で退職を伝えようとすると、パワハラされる危険がある場合です。LINEでの退職に適したケースは、次のような会社をイメージするとわかりやすいでしょう。
- 面と向かってやめたいと伝えると、暴力・暴言などパワハラされる
- 退職を思いとどまらせたいあまり、在職強要される
- 退職届を出しても、受けとってもらえない
すぐに退職を伝えなければならず、書面では間に合わないケースもあります。リモートワークが普及した会社では特に、直接の説明が必要となると、退職日が相当先になってしまう可能性もあります(例:社長が出社してこない場合など)。このようなとき、LINEによる退職の意思表示でも、会社に到達しているかぎり、法的には有効です。
どうしても書面や対面で退職を伝えるハードルが高いなら、LINEによる退職の意思表示を活用しましょう。なお、退職時にパワハラの危険があるときは、録音を取っておくなどの証拠収集の準備をしておいてください。


退職をLINEで伝えるメリット・デメリット

次に、LINEで退職を伝えることのメリット・デメリットについてそれぞれ解説します。
LINEで退職を伝えるメリット
LINEで退職を伝える方法の、労働者側のメリットは次の通りです。メリットは多く、退職の決断が付いたなら、LINEで伝えるのは非常に有効な方法です。
手軽に迅速に伝えられる
LINEは、即時にメッセージを送信し、社長や上司に対して、すぐに退職の意思を伝えることができます。対面で話す時間がないときや、緊急で伝えたいときに便利です。
心理的な負担が軽減できる
退職の意思を伝えるのは、心理的なプレッシャーの大きいことが多いでしょう。パワハラを受けているなど、会社側に不適切な対応があって辞めづらいときにはなおさらです。LINEなら、直接対面することを避けられるので、感情的なやり取りをなくし、精神的なストレスを緩和できます。
証拠が残る
手軽ではありながら、LINEは文章が記録されるので、証拠を残すことができます。後から、退職の意思を伝えたかどうかについてのトラブルを回避することができます。LINEで退職を伝えたことを証拠化するには、メッセージの送信日時がわかるように、前後の文脈も含めてスクリーンショットを取り、保存するのが適切です。
「退職したらやることの順番」の解説

LINEで退職を伝えるデメリット
LINEで退職を伝えることには、デメリットもあります。LINEによる退職の意思表示について、次のアンケート結果のように、「ありえない退職のしかた」だという価値観を持つ人もいます。
Q. ありえないと思う退職届の出し方を教えてください。
1位 メールやLINE 39.7%
2位 SNS経由 17.0%
3位 家族が届ける 10.7%
マイナビウーマン調べ:男性168名、女性414名(2014年4月調査)
LINEで「会社をやめたい」と伝えることのデメリットは、対面で伝えたり、退職届・退職願などの書面で伝えたりすれば回避できます。大切なのは、デメリットをよく理解し、LINEでするときは特に、退職の意思表示の伝え方に注意しなければならないという点です。
礼儀やマナーに欠ける対応だと言われやすい
LINEは、私生活でよく用いられる、カジュアルなコミュニケーションだと認識されています。そのため「ビジネスの場で使用するのは不適切だ」と考える人がいます。上記のアンケートでわかる通り、「退職する」という重要な場面に、LINEを使うのは「礼儀がない」「マナーを知らない」「非常識だ」といったように、不快に思わせてしまうデメリットがあります。
ただ、現在では、LINEを社内や顧客とのやり取りに活用する企業も多いです。LINEを甘くみて、書面による伝え方を重視するのは、主に中高年の上司などによる古い価値観であり、法的には退職の意思表示として有効です。
会社が反発して退職を認めてくれない
LINEによる退職の意思表示が軽視されたり、メッセージだけでは意図が正確に伝わらず、誤解が生じてしまったりして、感情的な対立が悪化することがあります。その結果、手段がLINEであったことが原因で、会社の反発を招き、退職を認めてもらえない可能性があります。
とはいえ、労働者には退職の自由があり、会社の承諾がなかったとしても、意思表示から2週間を経過すれば、会社を辞めることができます(民法627条1項)。
証拠の保存に工夫が必要となる
LINEのメッセージは、非表示にしたり削除したりすることができます。プライベートの携帯でLINEをしていると、せっかく退職の意思表示を伝えても、そのメッセージを消してしまったり、どこに保存したかわからなくなってしまったりして、証拠が保存できていない事態に陥ることがあります。アプリ頼りだと、誤作動や不具合にも弱い欠点があります。
「退職届を内容証明で出すべきケース」の解説

退職を伝えるときに送るLINEの例文
では、退職をLINEで伝えるメリット・デメリットを考慮したうえで、できるだけトラブルになりづらいよう、退職を伝えるときに送るLINEの例文を紹介します。
LINEは、軽くみられ、退職の意思を甘くみられるリスクがあるので、LINEで伝えるにしても、退職届を出すのと同じくらい堅い文章で出すのがおすすめです。
お疲れ様です。
突然の連絡、失礼いたします。○○部のXXXXです。
今回社長に折り入ってLINEしたのは、退職したい私の強い意思を伝えるためです。私は、営業職として20XX年X月に入社しましたが、私の希望する仕事はありませんでした。このままでは会社に貢献できないと考え、仕事をやめようと思った次第です。
ついては、本日付で退職の意思表示をします。退職日を本年X月X日とし、最終出社日は本年X月X日、その間は、残った有給休暇10日の消化に充当します。最終月の給料と退職金については、給与口座に振り込んでください。
この度は、大変お世話になりました。
上記は、あくまでテンプレートなので、事情にあわせて修正・追記してください。LINEのアプリ上だとかなりの長文になるので、違和感を覚えるかもしれません。しかし、退職を伝えるのに必要なことを正確に説明しようとすれば、LINEで伝えるにせよ、ある程度長い文章が必要です。有給休暇の消化、退職金の請求といった、退職時に伝えるべきことも、あわせてLINEで送りましょう。
「退職届の書き方と出し方」の解説

LINEで退職の意思表示をするときの注意

LINEでの退職の意思表示は有効ではあるものの、デメリットもあると解説しました。そのデメリットやリスクを解消するために、注意すべきポイントがあります。
デメリットを解消する基本的な心構えとして、どうしてもLINEでしか伝えられない場面で使うべきであって、「手軽だ」「簡単だ」という安易な気持ちで使わないことが大切です。
退職を伝えたLINEを証拠に残す
LINEで退職の意思表示を伝えるとき、書面で伝える場合に比べ、証拠として不完全な点があります。LINEの履歴は、クラウド上ではなく、スマホ端末そのものに保存されています。証拠を保存しておかないと、水没して壊れたり、紛失したりすると、退職の証拠がなくなってしまいます。
LINEだからといって退職の証拠にならないわけではないものの、証拠の残し方には独特な注意があります。LINEを消さないよう注意するのは当然、必ず画面キャプチャーも保存してください。スクリーンショットで証拠保存するとき、次のポイントも注意してください。
- 「誰に退職を伝えたか」がわかるよう、相手のLINEアカウントもスクショする
- 「いつ退職を伝えたか」がわかるよう、トークの日付が入った画面をスクショする
- 会話の文脈がわかるよう、前後を広めにとってスクショする
- 画面キャプチャーが何枚かにわかれるとき、少しずつかぶらせて保存する
裁判所でも、証拠は書面で提出するのが原則となっています。そのため、退職を伝えたLINEを証拠にしたいなら、印刷して提出するしかありません。
退職をLINEで伝えざるを得ないとき、パワハラがある違法な会社のことも多く、退職をめぐるトラブルが拡大し、労働審判や訴訟などの裁判が必要となるケースもあります。裁判で争うことを見据えて、証拠の準備は入念にしておかなければなりません。
「裁判で勝つ方法」の解説

LINEの誤作動に注意する
LINEで退職の意思表示を会社に送るとき、よく考えて送りましょう。退職届を出すときには、よく文章を練り、考え抜くでしょうが、LINEは1クリックで簡単に送れてしまいます。
途中作成の文章や、誤字脱字を修正しない文章を送らないよう、慎重にチェックしてください。LINEの誤作動にも、注意を要します。相手のLINEが誤作動したり、非表示、ブロックされていたりなどの可能性もあるので、「既読」になったか必ず確認しましょう。社長だけに送ったLINEがグループLINEに投稿され、退職を全社員に知られたという失敗もあります。
退職の意思はできるだけ堅く伝える
いくらLINEでの退職の意思表示が有効だとはいえ、書面ほど堅くは伝わりません。「会社をやめたい」という言葉は、できるだけ堅く伝わるほうが、会社に真剣に受け止めてもらえ、違法な引き止めやパワハラに遭いにくいという面があります。
このデメリットの解消のため、LINEで退職を伝えざるをえないとしても、堅い文面で丁寧に伝えましょう。間違っても、スタンプや絵文字、「!」、「笑」などを使えば、本気で受け止めてもらえません(詳しくは「退職を伝えるときに送るLINEの例文」参照)。
熟考し、良い文章にするには、LINEアプリ上で文章を練るのでなく、手書きやパソコンで文章を考えてからLINEに打ち込むのがおすすめです。パソコンで打ち込んだ文章をPDFにしてLINEで送れば、より堅く伝わります。
「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

業務上の連絡手段で伝える
LINEで退職の意思表示をするのがやむを得ないケースでも、会社の業務上の連絡ツールがLINEではないときは、再考が必要なこともあります。上司や社長のLINEを知っていても、プライベートの連絡手段にすぎないなら、LINEでの連絡は不適切だからです。業務上の連絡手段ではない、プライベートのLINEで退職を伝えることには多くのデメリットがあります。
- 「退職の相談」のLINEだと思われ、軽くみられる
- LINEで退職を伝えられたことを、会社に正式に報告してもらえない
- LINEが非表示・ブロックされていて見てもらえなかった
- プライベート携帯をあまりみておらず、退職したいと伝わるのが遅れた
このとき、業務上の連絡ツールで伝えるようにしてください。対面や電話で退職を伝えるのが難しくても、例えばメール、チャットなど、業務で使っている連絡手段のなかには、ハードルの低いものもあるはずです。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

会社がLINEによる退職を認めてくれないときの対応

最後に、会社がLINEによる退職の意思表示を認めていない場合、注意が必要です。念のため、就業規則における退職手続きのルールも確認しておいてください。
裁判例(横浜地裁昭和38年9月30日判決)では、会社の就業規則で「退職の意思表示は書面で行わなければならない」と定められていたケースで、この定めを有効と判断した例があります。
「被用者が退職するに際し、その時期、事由を明確にして、使用者に前後措置を講ぜしめて企業運営上無用の支障混乱を避けるとともに、他方、被用者が退職という雇用関係上もっとも重大な意思表示をするに際しては、これを慎重に考慮せしめ、その意思表示をする以上はこれに疑義を残さぬため、退職にさいしてはその旨を書面に記して提出すべきものとして、その意思表示を明確かつ決定的なものとし、この雇用関係上もっとも重要な法律行為に紛争を生ぜしめないようにするとともに書面による退職の申出がない限り退職者として取り扱われないことを保証した趣旨であると考えねばならない」
横浜地裁昭和38年9月30日判決
ただし、この裁判例はずいぶん前のものであり、現在も参考になるとはかぎりません。裁判例にいう、企業運営の支障や、重大な退職の意思における労働者側の慎重さといった点は、LINEで伝えたからといって失われるものではありません。
少なくとも、LINE以外の方法で伝えるよう強要したり、その際にパワハラや違法な引き止めをしたり、といった会社であれば、適切な方法でLINEを送る限り、LINEでの退職も許されるといってよいでしょう。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

今回は、LINEで退職の意思を伝える方法と、そのデメリット、対策について解説しました。
「面と向かって退職したいとは伝えづらい」「退職届を直接出すと引き止められ、パワハラにあいそう」といった不安のあるブラック企業勤務の方は、ぜひ参考にしてください。
LINEで「仕事を辞めたい」と伝えることは、法的な問題は全くありません。LINEでする退職の意思表示も、有効であるのは当然であり、対面で伝えづらいなら、LINEでも構いません。ただ、「軽く見られやすい」といったLINEによるコミュニケーションのデメリットを最小限におさえるため、LINEでの伝え方(伝える文章)には細心の注意が必要です。
なお、会社をやめるなら、LINEのみだったとしても必ず伝えてからやめましょう。バックレは「非常識」を超えて「迷惑」ですし、最悪は、損害賠償のリスクもあります。
- 退職の意思は、LINEで伝えても法的に有効
- 退職時にパワハラや違法な引き止めをする会社からは、LINEで速やかに退職する
- LINEで退職を伝えるときは、軽く見られないよう証拠を保存する努力が必要
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【退職とは】
【退職時の注意点】
【退職できないとき】
【退職金について】






