会社では、多くの行事、社内行事やイベントが開催されます。
社内の行事ごとは、社員の一体感を高めるのに重要な役目を果たします。
しかし、行きたくもない社内行事、イベントに、内心嫌々参加している方も多いはず。
会社が社内行事を大切に思うほど、労働者にとって参加が強制されるのを意味します。
とはいえ、今後の人間関係、社内での出世を考えると、本音はいえないでしょう。
「イベントには参加したくない」と拒絶すれば、パワハラを受けるおそれもあります。
一方で、社内行事やイベントへの参加の強制は、違法となるケースが少なくありません。
少なくとも社内行事に参加した時間は「労働時間」であり、残業代が請求できます。
今回は、会社から参加を強要された社内行事に関する対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 社内行事への参加を強制し、残業代を払わないのは違法で、パワハラにも当たりうる
- 社内行事が、強制参加ならば「労働時間」であり、残業代が発生する
- 社内行事が適法な業務命令だと、断ると処分されるおそれがあり、断り方に注意を要する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【残業代とは】
【労働時間とは】
【残業の証拠】
【残業代の相談窓口】
【残業代請求の方法】
社内行事への参加の強制は違法なパワハラ

まず、会社が労働者に、社内行事へ参加するよう強制するのは、違法なパワハラの可能性あり。
強制参加にするほど、労働者にとって不快な社内行事はすべきではありません。
よく強制参加にされがちな社内行事、イベントごとには次の例があります。
- 季節ごとの行事
初詣、節分、花見、納涼会、ハロウィン、クリスマス会、会社の祭りなど - 季節ごとの飲み会
新年会、キックオフ、決算会、忘年会、社内パーティなど - 社員の懇親、親睦を目的としたイベント
歓送迎会、親睦会、懇親会、表彰式、社内の部活動、社内の委員会など - 社員総会
社内行事の強制参加トラブルが難しいのは、労使の意図に大きな差があるから。
労働者としては、「本音は嫌だけど、従わざるをえない」気持ちでしょう。
一方で、会社側からすれば、「むしろ社員のためにサービスしている」という思いのことも。
飲み会の費用を会社負担とするなど、福利厚生の一環だという気持ちのこともあります。
このギャップが埋まらなければ、「社内行事への参加強制」という問題の解決は、困難を極めます。
しかし、そもそも、参加の強制をする権利があるのでしょうか。
権利や根拠なく、強制参加とさせられているなら、違法なパワハラにあたりかねません。
業務命令で強制参加にできるか
そもそも、社内行事への参加を強制することができるのでしょうか。
労働者は、会社と労働契約を結んでいます。
労働契約では、会社は労働者に、一定の命令をする権利があります。
これを、法律用語で「業務命令権」といいます。
業務命令権は、その名のとおり「業務」を命じる権利。
働くよう命じるのは可能ですが、社内行事、イベントがこれに含まれるかは争いあるでしょう。
ただ少なくとも、業務命令によって参加を強制するなら、それは「仕事」ということ。
つまり、社内行事やイベントなど、一見は飲み会でも、仕事の一環であり、給料ないし残業代が発生します。
業務時間内の社内行事のケース
業務時間内の社内行事に対して、参加を強制されたケースを解説します。
例えば、社内で業務時間中にするケータリングパーティ形式の懇親会など。
労働契約の性質である、会社の業務命令権は、業務時間内の労働者の行動に及びます。
業務時間内は、仕事をすべき時間。
給料が払われる限り、会社は命令によって、労働者の行動をコントロールできます。
したがって、業務時間内の社内行事なら、参加を強制されれば従わなければなりません。
そして、給料も、通常どおり払われます。
(業務時間内でも、社内行事への参加の時間は給料が控除された、というのなら違法です)
業務時間外の社内行事のケース
次に、業務時間外の社内行事に対して、参加を強制されたケース。
例えば、業務が終了した後でされる飲み会などです。
業務時間外の社内行事でも、参加を強制することがまったくできないわけではありません。
ただ、適法にするには、「業務として」行う必要あり。
つまり、業務時間外といえど、強制参加の社内行事やイベントは「残業」に当たります。
したがって、残業命令を適法にできる場合でないと、業務時間外の社内行事は強制できません。
残業は、次の要件を満たさなければ違法です。
- 36協定を締結している
- 就業規則ないし雇用契約書に、残業命令の根拠がある
- 36協定に定めた限度時間を超えない
- 労働基準法における計算方法どおりの残業代が払われている
以上の適法に残業させる要件を満たさなければ、残業はさせられません。
そのような場合、業務時間外の社内行事、イベントへの強制参加は、違法であり、従う必要がありません。
違法に強制参加させられそうなとき、違法な残業の断り方を参考にしてください。

会社の行事にも残業代は払われる

次に、「社内行事に残業代が払われるのか」という疑問に回答します。
この問題は、社内行事への参加が、強制かどうか、という点とも関連します。
社内行事への参加が強制されるなら、それは会社の命令ということ。
その参加については残業時間となり、残業代が払われないなら労働基準法違反で、違法です。
社内行事は「労働時間」にあたる
残業代が支払われるべき時間とは、法律ないし裁判例で「労働時間」と認められる時間です。
「労働時間」とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されます。
「労働時間」の定義は、裁判例で次のとおり判断されました(最高裁平成12年3月9日判決)。
労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない。
最高裁平成12年3月9日判決
この「労働時間」が、労働基準法に定められた「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間の枠を超えたとき、残業代を請求することができます。
参加したくもない社内行事、イベントを強制されれば、「指揮監督下」に置かれたといえます。
指揮監督下にないならば、参加したくない行事など、すぐ帰宅すればよいからです。
したがって、社内行事やイベントの時間も含め、1日の労働時間が8時間を超えれば、残業代がもらえます。
労働時間の定義は、次に詳しく解説しています。
「強制参加」には直接・間接の2つがある
参加強制をされた社内行事は、「労働時間」であり、残業代を請求できると説明しました。
すると、どんな場合に「参加を強制された」といえるかを検討しなければなりません。
この点、「強制参加」には、直接的なもの、間接的なものの2種類があります。
直接的に参加を強制されるのは、会社から「絶対に参加するように」と命じられるケース。
これに対し、次のような間接的な参加強制でも、「労働時間」には当たります。
なお、「労働時間」となるのは、社内行事やイベントの当日だけとは限りません。
例えば、飲み会の幹事や、社内総会の実行委員会に指名されるケース。
社内行事より前に準備したり、居残り残業したりする必要があれば、その時間もまた残業代が生じます。
社内行事は残業代請求できる
「労働時間」が、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えれば、残業代がもらえます。
参加強制された社内行事、イベントは「労働時間」なので、長時間になれば残業代を請求できるでしょう。
なお、社内行事の二次会など、自発的な参加となれば「労働時間」ではなく、残業でもありません。
残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次に解説します。

会社の行事に残業代が払われない時の対応
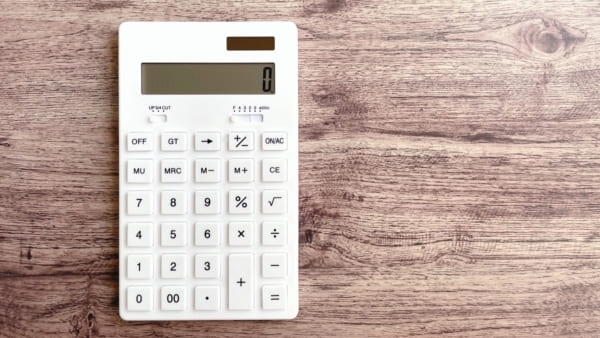
社内行事、イベントに参加を強制されれば、残業代が請求できると説明しました。
しかし、悪質な会社には、長時間労働となっても、残業代を一切払わない会社もあります。
適切な残業代を払わない会社で、我慢してサービス残業を続けるのはお勧めできません。
「自発的に社内行事に参加している」と評価されてしまえば、残業代の請求はできないからです。
残業代が払われなければ、即座に異議を述べ、違法を指摘しなければなりません。
ここでは、実際に社内行事やイベントに参加させられた際の、残業代請求の方法を解説します。
「強制参加」の証拠を集める
社内行事やイベントに要した時間に、残業代を請求するには、「強制参加」だと証明しなければなりません。
この証明は、労働者が事前に準備しなければ難しいケースもあります。
証拠として活用できるのは、次のような資料です。
- 参加を強制するという社長や上司からのメール
- 社内行事、イベントの案内、パンフレット
- 社内行事への不参加を理由にされた不利益な処分
内容証明で社内行事の残業代を求める
残業代の生じる社内行事の強制があったら、即座に残業代を請求します。
請求は、まずは内容証明を送付し、交渉することからスタートです。
交渉で解決できれば、会社に残ったまま、円満に残業代をもらえます。
今後の扱いとしても、社内行事やイベントを強要されるパワハラは減らしてくれるでしょう。
会社の「やってあげている」という思いが強かった場合、誤解が解けるかもしれません。
残業代請求することは「社内行事は嫌だ」という率直な思いを伝える意味もあります。
残業代の請求書の書き方、テンプレートは、次に解説します。
労働審判・訴訟で社内行事の残業代を請求する
交渉で解決できない場合、社内行事への参加強制の残業代を請求するため、労働審判を行います。
ただ、労働審判を行う場合には、退職を前提として考える方が多いでしょう。
社内行事への不満が大きく、会社に残る必要もないと考えることもあります。
それならば裁判所の手続きを利用し、徹底的に残業代を請求しましょう。
話し合い(任意交渉)でも労働審判でも残業代トラブルの解決にいたらない場合には、最後は裁判による解決を検討します。
労働審判で解決できないとき、裁判に移行することもあります。
社内行事を参加強制され、心身が疲弊するなら、もはやブラック企業に残るメリットもないでしょう。
強く残業代を要求した上で、退職することも検討しましょう。
労働問題の解決方法は、次に解説します。

社内行事に参加したくない時、拒否できる?
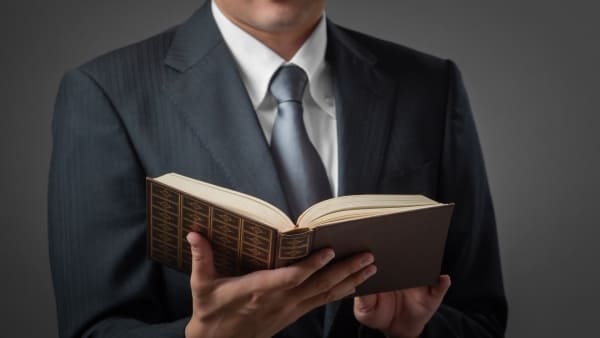
最後に、どうしても社内行事に参加したくないときの対応を解説します。
社内行事、イベントを、労働者側で拒否することができるケースもあります。
ただし、拒否のしかたに注意し、問題が拡大しないように対応しましょう。
残業代を払っても許されない社内行事
給料、残業代を払えば、どんな社内行事でも強要できるかというと、そうでもありません。
お金だけでは解決できない問題もあります。
そもそも開催の許されないイベントなら、参加命令に従う必要はなく、拒否すればよいでしょう。
例えば、次のケースは、残業代を払っても許されない社内行事といえます。
- 社内行事が多すぎて、心身の健康を崩してしまう
- 社内行事の時間が長すぎて、プライベートがない
- イベントで飲まされ、体調が悪化してしまった
- 社内の行事が、個人の宗教、政治、信念を侵害している
なお、慎重に判断しないと、業務命令違反の責任を追及されるおそれがあります。
適法な業務命令に従わないと、注意指導され、評価が下がることも。
最悪は、懲戒処分や解雇といった重大なリスクもあるため注意してください。
社内行事の断り方
ただ、注意したいのは、会社が正しく対応し、適切な給料ないし残業代を払って、社内行事やイベントに強制的に参加させようとするとき、断ることにはリスクもあるという点。
適切な業務命令なら、従わない労働者に不利益な扱いをしても仕方ありません。
すると、このリスクを減らすためにも、できるだけ対立を深めず、異議を伝えたほうがよいでしょう。
社内行事、イベントへ参加を強制されながら、残業代が払われないと、断るのには勇気がいります。
例えば、できるだけ穏便な伝え方は、次のようなもの。
- 健康状態を理由にする
「お酒が飲めない」「タバコを吸う場所が苦手」「体調が悪い」 - 家庭の事情を理由にする
「幼い子どもの世話が必要」「家族の介護が必要」「妻との門限がある」
まとめ

今回は、社内行事、イベントへの参加を強制された場合の対応について解説しました。
参加強制が当然のように行われると、雰囲気や流れにまかせて従う方もいるでしょう。
社内の人間関係が悪化し、居心地が悪くなるのをおそれ、嫌々参加する方も多いはずです。
しかし、残業代が払われていなければ、損しています。
業務時間外に行われ、参加が強制されるなら、いかに親睦、懇親といっても、仕事そのもの。
社内行事やイベントに参加している時間には、残業代が払われるべきです。
残業代がもらえないなら「自由参加」であり、プライベートの飲み会と同じく、拒否できます。
違法な命令を拒否したからといって、それを理由にした不利益な処遇も許されません。
- 社内行事への参加を強制し、残業代を払わないのは違法で、パワハラにも当たりうる
- 社内行事が、強制参加ならば「労働時間」であり、残業代が発生する
- 社内行事が適法な業務命令だと、断ると処分されるおそれがあり、断り方に注意を要する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【残業代とは】
【労働時間とは】
【残業の証拠】
【残業代の相談窓口】
【残業代請求の方法】






