※本解説は、2020年時点の現状に合わせた解説となっております。
令和5年3月13日以降、マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となる旨を政府が発表しており、また、同年5月8日以降、新型コロナウイルスは5類感染症へと移行しました。
したがって現在は、「マスクをつけない」ことの問題性は、本解説記載よりも著しく低下していると考えられます。
本解説の内容は、社会の情勢に合わせて今後変更を予定しているため、現時点では、2020年当時の状況を知るための参考資料とお考えください。
なお、マスク着用の有無に限らず、社内における社員間の距離が近すぎることは、軋轢を生む原因となることが多いため、そのような場合に安全配慮義務違反やハラスメントの問題が生じうるかを検討する際の参考にしていただけます。
感染症防止のため、マスクの着用が職場でも浸透しています。
しかし、それでもなお、マスクをしない人のいる職場もあります。
常にノーマスクで過ごす人はさすがに少ないでしょう。
しかし、ちょっとした会話ならマスクせず話しかけたり、いつもアゴマスクだったり。
職場の飲み会に参加せねばならず、マスクなしにしゃべりかけられ不愉快に思う例もあります。
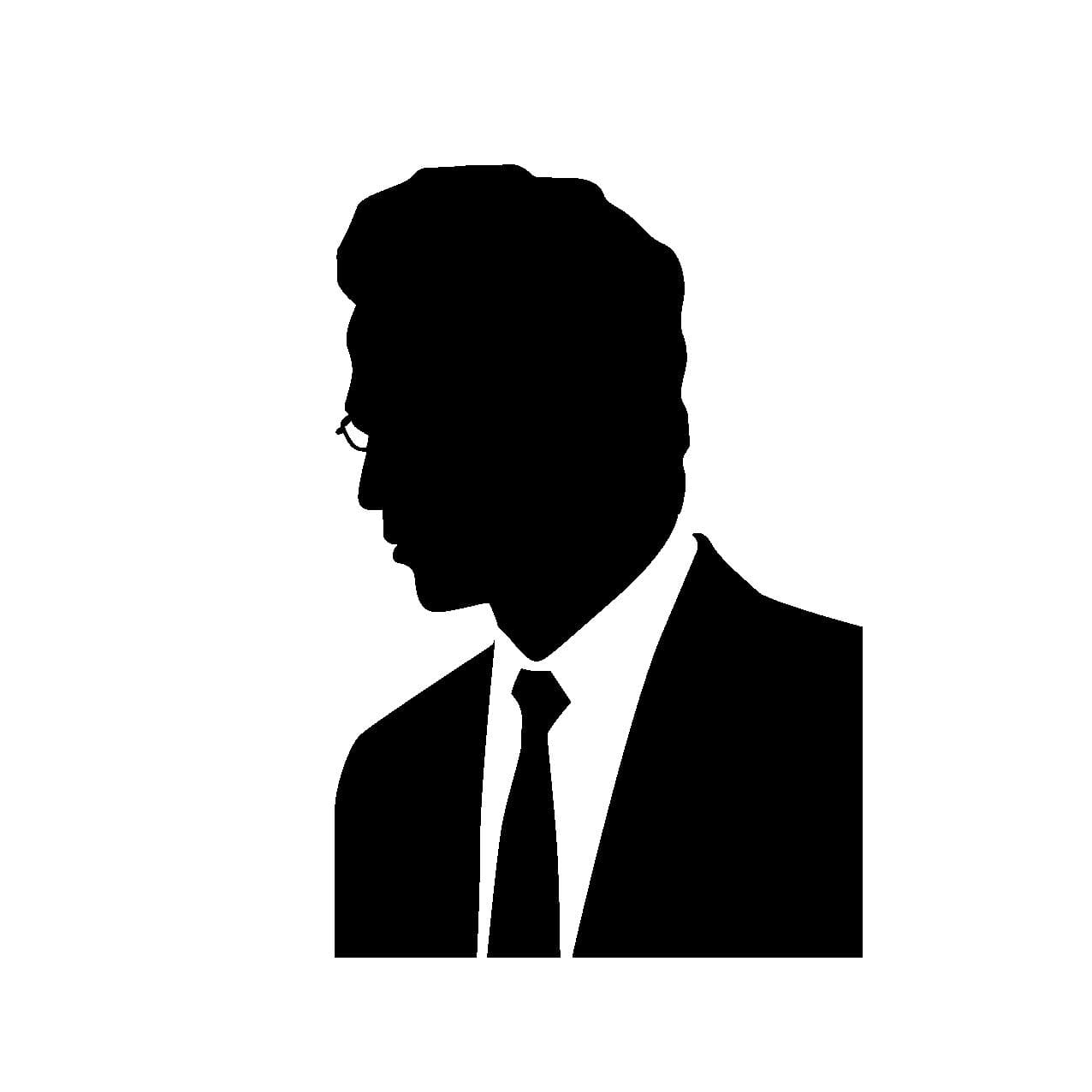 相談者
相談者会社が対策してくれなくて怖い
 相談者
相談者社長が原因となっているのでは
こんな相談もあります。
会社は、社員の健康を守る義務があります(安全配慮義務)。
そのため、感染の危険があるような事態で、予防策を打たずに働かせるのは違法です。
今回は、マスクを着用しない人への対応と、会社の責任について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 職場の「マスクしない人」問題は、ハラスメント問題と似た、法律問題になる
- 職場の安全を守らないのは、会社の責任
- 職場にマスクしない人がいて危険なとき、出社を拒否できる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【労災申請と労災認定】
【労災と休職】
【過労死】
【さまざまなケースの労災】
【労災の責任】
職場の「マスクしない人」問題は、安全配慮義務違反という法律問題になる

会社は労働者に、安全に働いてもらう義務があります(安全配慮義務)。
労働者にとって、職場は人生の大半を過ごすとても重要な場所。
快適な職場でなければ、心身の健康を害してしまいます。
労働契約法5条にも、次のとおり定めがあります。
労働契約法5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法(e−Gov法令検索)
労働者の病気を防止が大切なのは、風邪やインフルエンザ、うつ病などはもとより、新型コロナも同じこと。
現在の情勢を考えれば、最低限の対策は、安全配慮義務の内容だといってよいでしょう。
- マスク着用
- 咳エチケット
- 手洗い・うがい
- アルコール消毒
- 窓開け・換気
したがって、職場のマスク問題は、法的には安全配慮義務違反の問題の一環。
マスクを着用しない人を放置しておけば、他の社員の健康を危機にさらします。
マスクをつける、つけない問題は、個人の価値観によっても変化するため、会社が統一的にルールを定め、社内に浸透させていかなければなりません。
特に、職種によっては法律上の安全配慮義務は、さらに高いレベルで要求されます。
人との接触機会が多く、マスクを着用する必要性が高いと考えられるからです。
- 飲食店の従業員
- 接客業
- 医療従事者
マスクしない人のいる職場での適切な対応

次に、マスクをしない人のいる職場で、どんな対応が適切かを解説します。
以上のように、マスク着用は、他の社員の安全を守る行為。
そのため、会社が安全配慮義務の一環として、徹底して教育せねばなりません。
しかし、なかには、マスクしない人のいる職場も珍しくありません。
マスクしない人と距離をとる
マスクしない人が職場にいるとき、距離をとるようにしましょう。
これは、物理的に距離をとるのはもちろん、精神的にも、かかわっていては疲弊してしまいます。
マスクしない問題点を会社に理解してもらい、席替えをしてもらう方法も有効です。
マスクするよう会社に注意指導してもらう
まず、マスクしない人には、会社から注意指導をしてもらいましょう。
考え方や価値観は人それぞれのため、直接労働者同士で指摘をすると、トラブルのもとです。
あくまで職場のマスク問題は、医学的な問題だけではありません。
- 職場の人間関係を円滑に進める
- 他の社員に不快感を与えない
職場の人間関係についての法的問題であり、ハラスメント問題に近い考え方。
会社は、安全配慮義務の観点から、マスクしない人に注意指導しなければなりません。
現在の情勢なら、特別の理由がないかぎり、マスクするよう業務命令できると考えられます。
危険な出社はとりやめる(欠勤する)
それでもなお、マスクしない人が反抗的なとき、職場の危険はなくなりません。
こんなとき、危険のある出社はとりやめることができます。
つまり、欠勤してよいということです。
業種や会社によっては、テレワークにしてもらえないかお願いするのもよいでしょう。
会社が、安全配慮義務を果たさないために出社にリスクがあるときは、「出社できないのは会社の責任」ということができ、会社に行かなくても責められるいわれはありません。
出社するよう命じられても、違法な業務命令には従う必要がありません。
安全配慮がなされず、危険な会社に出社を要しないのは、ハラスメント問題と同様。
つまり「会社にいくと暴力を振るわれる」、「長時間労働を強要され、健康被害が出ている」といったとき、会社の責任によって出社できないのと同じ法律問題です。
このとき、会社が原因で出社できないなら、その期間の給料は請求できます。
詳しくは、うつ病で出社できないときの給料についての解説をご覧ください。
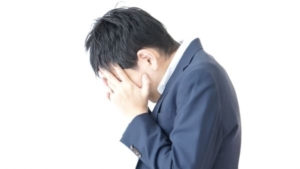
弁護士から警告書を送る
職場にハラスメント相談窓口があるときは、マスクしない人を通報し、相談してもよいでしょう。
しかし、ブラックな会社や、そもそも社長が原因だと、対応してくれない可能性があります。
労働者自身が言っても危機感を持たない会社には、弁護士から警告書を発してもらうのが有効です。
弁護士名義の警告書は、次のような法律知識に基づく正しい指摘をし、強いプレッシャーになります。
- 安全配慮義務の法的根拠を示す
- 義務を果たすための具体的な改善策を提示する
- 義務違反のとき責任追及をすると示す
弁護士からの警告書は、内容証明で送ることにより、証拠化できます。
会社の対策が不十分で、後にトラブル化するときに備え、証拠を準備しておきましょう。
弁護士に任せれば、職場の労災問題をスピーディに解決できます。

会社の対策が不十分なとき、労災になる

ここまで会社にはたらきかけても、対策が不十分なとき、会社の責任を問いましょう。
具体的には、対策が不十分で起こった病気について、安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求するとともに、労災申請をするようにします。
「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」(厚生労働省・2020年4月)の通達でもわかるとおり、コロナは労災になりえます。
その特殊性から、従来の労災認定より、感染経路の特定はゆるやかに考えるべきとも示されました。
つまり、これまでどおりのやり方なら「業務が原因かどうかは不明だから労災ではない」とされた症状でも、労災認定を受けられる可能性があります。
医療従事者や、海外出張の業務命令を受けた人だと、特に労災認定の可能性が高まります。
労働者は、会社の働く場所を選べませんし、生活のため、そう簡単には退職できません。
そのため、会社が対策を万全にしなければ、安全配慮義務違反の責任があるのは明らかです。
マスクしない人の主張にも配慮し、話し合いを重視する
一方で、どうしてもマスクしたくないという人もいます。
このとき、偏った一方的な対応をするのではなく、互いの立場を理解し、話し合うのが大切。
円満な職場を作る努力も必要です。
- 貧困で、マスクを買うお金がない
- 肌荒れがひどく、マスクができない
- 猛暑の作業で、マスクすると熱中症になる
他の社員と距離をとり一時的にマスクをはずしたりするのが許されることもあります。
そのため、ほんの少しマスクをしなかったからと、過剰に反応すべきでないケースも。
なかには、マスクをしてもらうために、会社の費用で用意してくれる、配慮ある会社もあります。
まとめ

今回は、昨今、法律上もよく問題となる、職場でのマスク問題について解説しました。
問題への意識の高さ、危機感の大きさは人それぞれですが、職場で円滑にすごすためにも、常識的な対応をしなければなりません。
マスクしない人がいる問題のある職場では、会社に注意してもらうのが適切。
労働者個人の判断にまかせるのではなく、職場の安全は会社が守らねばなりません。
社長がマスクしていないなど、対策してくれなそうな会社は、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 職場の「マスクしない人」問題は、ハラスメント問題と似た、法律問題になる
- 職場の安全を守らないのは、会社の責任
- 職場にマスクしない人がいて危険なとき、出社を拒否できる
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【労災申請と労災認定】
【労災と休職】
【過労死】
【さまざまなケースの労災】
【労災の責任】






