突然に転勤を打診されたとき、「どうしても受け入れられない」と迷うことがあるでしょう。家庭の事情や子供への影響、労働条件の悪化など、転勤を断りたい理由は人それぞれですが、転勤命令を拒否するのは容易ではなく、リスクが伴います。
あなた自身はよくても、転勤による家族への影響は計り知れません。「転勤族」だと、深い友人を作りづらかったりストレスを感じやすくなったりと、子の成長の支障になるのでは、という懸念もあります。家族あっての人生ですから、単身赴任は気が進まない人も多いのではないでしょうか。
今回は、転勤を断ることができるか、転勤拒否の正当な理由と、拒否する際に考慮すべきリスクや断り方について解説します。正当な理由があれば転勤を拒否することができます。子供の難病などが転勤を断る理由となることは裁判例でも認められています。
- 転勤を拒否する正当な理由があるなら、転勤を断ることができる
- 子供の病気、親の介護などの家庭の事情は、転勤拒否の正当な理由になり得る
- ただし、その不利益が小さいとき、転勤拒否が解雇につながるリスクがある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
転勤を拒否できる場合とは

まず、転勤を拒否することができる場合とはどのようなケースか、解説します。
不利益の大きい転勤を命じられると、拒否したいと考える労動者も多いでしょう。現在の勤務先で長く働いていた人ほど、現状を変更せざるを得ない転勤の不利益は大きいもの。会社は様々な理由を付けて転勤させようとしますが、従わなくてよい場合もあります。
転勤を命じる権利がない場合
大前提として、会社が従業員に転勤を命じるには「転勤を命じる権利」が必要です。
転勤を命じる権利は、労働契約によって会社に与えられるので、契約上の根拠がなければ命令権は存在しないことになります。命令する権利がないなら、命令そのものが許されず、労動者としても従う必要はありません(なお、命令権がなくても、同意があれば転勤させることができるので、労動者は断固として転勤命令を断る必要があります)。
転勤命令の根拠は、就業規則や雇用契約書に従って判断する必要があるので、あらかじめ、労働契約にどのような定めがあるか、規程を確認しておいてください。
次の場合、転勤命令をする労働契約上の根拠は存在しないと考えられます。
転勤条項が存在しない場合
労働契約で、「転勤を命じることができる」「労動者は転勤に応じる義務がある」というように転勤条項が明記されている場合、転勤命令の根拠規定となります。逆に、転勤条項が存在しないなら転勤を命じることはできず、転勤を断ることが許されます。
ただし、転勤条項があっても、どのような命令でも無制限に許されるわけではありません。
勤務地の指定があり転勤が制限されている場合
労働契約に勤務地の指定があり、転勤が制限される場合は、定められた範囲内の場所でしか働かせることができません。そのため、その範囲を超える転勤命令は拒否することができます。
なお、雇用契約書に勤務地が書かれていても、あくまで最初の勤務地を示すに過ぎず、必ずしも転勤を制限する趣旨とは限りません。勤務地が指定されていても「会社の指示により勤務地を変更する場合がある」などと記載される場合は転勤が予定されています。したがって、転勤を拒否したいなら、入社時に、当初の場所以外に転勤しないことを雇用契約書に明記させる必要があります。
「雇用契約書がないことの違法性」の解説

転勤命令に合理性がない場合
転勤命令の正当性は、その命令についての業務上の必要性と、労動者に与える不利益のバランスによって決定されます。そのため、労動者の私生活に多大な影響を与える転勤であるにもかかわらず、業務上の必要性が低い命令は、不当であると判断されることがあります。
拒否する正当な理由がある場合
転勤を拒否する正当な理由がある場合にも、転勤を断ることができます。雇用される労動者は、使用者の業務命令に従う必要がありますが、「どのような場合でも転勤に応じなければならない」というのは酷であり、一定の制限があります。
正当な理由となるのは、労働者の不利益が、耐え難いほど大きい場合です。「交通費がかかる」「日常生活が負担だ」「住み慣れた地を離れたくない」といった程度の理由は正当な理由とは認められない一方で、次章「転勤を拒否できる正当な理由とはどのようなものか」に解説の通り、子供の病気や親の介護のなどといった家族の事情は、転勤拒否の正当な理由として認められるケースがあります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

転勤を拒否できる正当な理由とはどのようなものか

会社からの転勤命令に対して、労働者が拒否できる正当な理由はいくつか存在します。
特に、正当な理由として主張されるのが、家族の事情です。自分のことだけなら我慢できても、家族への支障は我慢できないことでしょう。「仕事と家族はどちらが大切か」という質問に正解はありません。仕事のために家族を犠牲にしなければならないのは酷であり、家庭の事情は、転勤を拒否できる正当な理由となるケースが少なくありません。
以下では、どのような場合に、正当な理由によって転勤拒否が認められるかについて、裁判例の考え方の基本を解説した上で、具体例を紹介していきます。
正当な理由についての裁判例の考え方
転勤のトラブルを、会社との交渉で解決できないとき、裁判所で最終判断が下されます。そのため、「正当な理由があり、転勤を拒否できる」と判断するに至った裁判例の理解が大切です。裁判例において、転勤の違法性については次のステップで判断されます。
- 業務上の必要性があるか
- 不当な動機・目的で命じられていないか
- 労働者に著しい不利益を負わせるものではないか
このなかで、転勤拒否の正当な理由となるかどうかは、その事情が「業務上の必要性」と比較して「著しい不利益」かどうか、というバランスが考慮されます。また、「結婚を報告したら単身赴任を命じられた」など、家庭の事情が起こったのと近接したタイミングで命じられた転勤は、業務上の必要性がなかったり、嫌がらせ的な意図で命じられていたりする疑いがあります。
「左遷の特徴と対処法」の解説

正当な理由となる具体例
転勤命令を拒否することのできる正当な理由について、具体例は次の通りです。
家庭の事情
家庭の状況によっては、転勤を受け入れると労動者の不利益が大きすぎることがあります。次の場合、転勤拒否の正当性が認められる可能性があります。
- 家族の介護
高齢の家族の介護を要する場合で、自分以外に介護を担当するのが難しい状況だと、転勤を拒否できることがあります。 - 子供の教育
子供が学校に通っており、転勤すると転校が必要となるとき、転勤を拒否できることがある。転校が精神的な負担となる事情があるとか、受験を控えた時期であるといった理由は、転勤拒否の正当性を基礎づけるのに役立ちます。
健康の問題(本人及び家族)
本人や家族の健康の問題も、転勤を拒否できる理由になることがあります。
- 本人の健康問題
転勤の対象となる本人の持病や、特定の医療機関で治療する必要があるといった事情で、転勤すると治療が困難となる場合、正当な理由と認められる可能性があります。 - 家族の健康問題
配偶者や子供が深刻な病気や障害を抱えている場合には、転勤による影響が非常に大きく、拒否することが認められる場合があります。
ただ、病気などの健康の問題が、転勤を拒否する正当な理由となるには、その不利益が相当大きい必要があります。この判断では、次の事情が総合的に考慮されます。
- どのような病気か
病名、治療の必要性、完治することができるか、など - 病状が重大かどうか
治療期間はどれくらいか、入院・看護が必要かどうか、など - 転勤する人以外に、他の看護者がいるか
妻が仕事をしているか、両親の協力が得られるか、など - 転勤先で治療することができるか
特別な専門医が必要な難病でないかどうか
育児介護休業法26条は、次の通り、異動をさせるときには子の養育や家族の介護の状況に配慮する必要があると定めており、会社側の配慮が不足している転勤は、同法違反となります。
育児介護休業法26条
事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
育児介護休業法(e-Gov法令検索)
企業側の配慮の不足(転勤先の職場環境や労働条件など)
転勤先の職場環境が著しく劣悪な場合にも、転勤を拒否する正当な理由となります。
労働条件が現在よりも悪化したり、待遇が下がったりする場合に、その扱いが違法であるときは転勤を断るべきです。著しい不利益があって拒否する正当な理由があるかどうかは、労動者側の事情だけでなく、会社側の配慮の程度によっても変わります。
例えば、次のケースでは、転勤を拒否すべきと考えられます。
- 転勤に伴って給料が大幅に減らされる場合
(単身赴任となる、生活費の負担が増大するのに給料が全く増額しない) - 転勤先にハラスメントや長時間労働などの労働問題があると分かっている場合
- 海外の危険地帯に転勤させられる場合
- 突然に転勤を命じられて準備の時間が全くない場合
- 帰郷するための旅費の支払いが全て自己負担である場合
「転勤を理由に退職できる?」の解説

転勤拒否の正当な理由について判断した裁判例
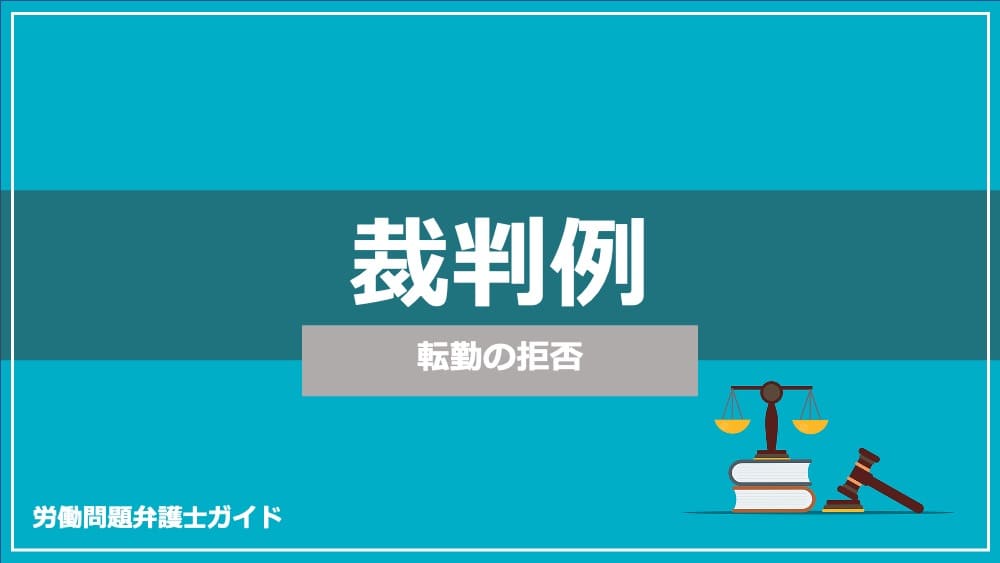
以下では、転勤拒否の正当な理由があるかどうか、争われた裁判例を紹介します。
ケンウッド事件
初めに紹介する判例が、ケンウッド事件(最高裁平成12年1月28日判決)です。本事案は、東京都目黒区の職場から、八王子へ転勤するよう命じられたケースです。
通勤時間が1時間ほど長くなり、子供の送迎に支障が生じると主張して転勤を拒否しましたが、裁判所は、子供の送迎への支障は「著しい不利益」とはいえないと判断し、転勤拒否に正当な理由があるとは認めませんでした。
北海道コカコーラボトリング事件
次に紹介するのが、北海道コカコーラボトリング事件(札幌地裁平成9年7月23日判決)です。本事案では、子供の病気を理由だけでなく、両親の面倒を見ていたことも主張されました。裁判所は、病気の子供2人と、両親の世話もしていた労働者に対する、単身赴任を要する転勤は「著しい不利益」にあたると判断し、転勤命令を違法、無効だと判断しました。
明治図書出版事件
次の裁判例は、明治図書出版事件(東京地方裁判所平成14年12月27日決定)です。
裁判所は、妻と共働きの労働者に、東京から大阪への転勤を命じた事案について、違法だと判断しました。本事案でも、転勤を拒否する理由は、子供の病気でした。子供が、重度のアトピーで、治療を要するという理由は「著しい不利益」として考慮されました。
前述の育児介護休業法における配慮の必要性が説かれ、会社が十分な説明を事前にしていない点もまた、労働者にとって有利な事情になりました。
日本レストランシステム事件
最後に紹介する裁判例が、日本レストランシステム事件(大阪高裁平成17年1月25日判決)です。本事案では、心臓病の子供がいる労働者を、関西から東京へ異動するよう命じたケースで、裁判所は、現地採用であったことなどを理由に転勤命令は違法、無効だと判断しました。
「裁判で勝つ方法」の解説

転勤を断るための適切な方法
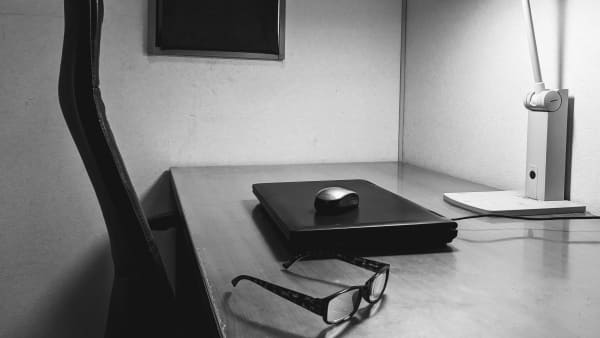
次に、転勤を断るための方法について、手順を解説します。
ここまでの説明を参考に、正当な理由があって断れる命令だと判断できても、転勤命令の断り方は、慎重に進めなければなりません。また、必ずしも正当な理由があるとまでは言い切れない場合も、丁寧に説明を尽くし、会社を納得させれば、転勤せずに済むこともあります。
拒否の意思は早めに伝える
転勤命令が出された際に、断る可能性があるなら、会社には速やかに事情を伝えるべきです。仮に転勤を取りやめるにせよ事前の調整は必要であり、直前に拒否されても配慮できないからです。企業側に時間的な余裕を与えることが、自身の状況をよく考慮してもらうのに大切です。
また、家族のことといったセンシティブな理由だと、感情的になってしまう人もいますが、冷静に状況を説明し、転勤を受け入れられないことを伝えてください。
「会社のプライベート干渉の違法性」の解説

具体的な理由を伝えて交渉する
転勤を拒否する理由はしっかりと具体的に説明するようにしてください。単に拒否するのでなく、本解説を参考に、正当な理由であると認められた裁判例を引用したり、診断書や家庭の状況を証明できる書類をあわせて提出したりして、説得力を持たせることが肝要です。
転勤を断る理由ごとに、例文を示しておきます。
「現在、両親の介護を私一人で行っており、転勤すると親の介護をする人がいなくなってしまいます。転勤先に大きな病院がなく介護体制が整っていないため、一緒に連れていくのも困難であり、転勤を受け入れることはできない状況です。両親の健康状態や介護に必要なサポートを考えると、現住所から離れることができません。」
「長男が現在、高校進学を控えており、受験の準備が重要な時期です。転校することが大きな負担となり、子供の学業に支障をきたす可能性があるため、転勤を辞退させていただきたいと考えています。」
「子供が持病を抱えており、転勤先では専門的な医療が受けられない可能性が高いため、転勤を受け入れることが難しい状況です。仕事も大切にしたくはありますが、家族の健康状態を最優先に考えたいと考えております。」
「会社に診断書を出せと言われたら」の解説

交渉の余地を残す
転勤を完全に拒否するのではなく、代替案を示しながら柔軟に交渉すれば、より円滑に話を進めることができる場合があります。次章に解説する通り、完全に転勤を拒否してしまうと、解雇をはじめとした大きな不利益を被るリスクも否めません。
「しばらくの間は転勤が難しいが、家庭の事情が解消したら従うことができる」といったように譲歩を示したり、他の勤務地や労働条件の変更を申し出たりする手が有効です。
「労働条件の不利益変更」の解説

転勤を拒否するリスクと、解雇された時の対応
以上の通り、ブラック企業が、強行に転勤を命令してきても、断ることができます。
家族の事情、育児や介護などは、人生にとって非常に重要なものであり、たとえ仕事とはいえ、家庭を守ることにはかないません。
一方で、企業にとっても秩序を守るために、転勤命令の重要性は相当高いと考えられています。そのため、正当な理由がないのに転勤を拒否すると、解雇されるリスクがあります。とはいえ、解雇は法律によって厳しく制限されており、正当な解雇理由がなければ無効となります。解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合には、違法な不当解雇として無効になるからです(労働契約法16条)。

最終的な判断は、裁判所がするので、裁判例をよく理解しなければなりません。転勤を断り、懲戒解雇されるケースは少なくありません。そして、実際に争われた裁判例でも、そのような転勤拒否を理由とした解雇を有効であると判断したものもあるため、細心の注意を要します。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

まとめ

今回は、納得のいかない転勤の拒否について解説しました。
正当な理由があれば労働者は転勤を断ることができます。子供の病気や親の介護など、転勤による家族への影響は多大であり、拒否する正当な理由として認められる例も少なくありません。
しかし、転勤拒否は、労動者の人生にとって重要な選択であるものの、慎重な対応が求められます。正当な理由がある場合でも、円満に働き続けたいなら、会社とのコミュニケーションを密に取り、交渉しなければなりません。一方で、正当な理由がないのに転勤を拒否すると、低い評価を受けたり、最悪は、解雇をされてしまうリスクもあります。
転勤を拒否することで生じるリスクの大きさを考えると、自身で焦って判断してしまうのではなく、拒否の意思を伝える前に、弁護士に相談するのがおすすめです。
- 転勤を拒否する正当な理由があるなら、転勤を断ることができる
- 子供の病気、親の介護などの家庭の事情は、転勤拒否の正当な理由になり得る
- ただし、その不利益が小さいとき、転勤拒否が解雇につながるリスクがある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/






