新卒の就活生、転職したい中途の方は、内定をとるため全力で励んでいるでしょう。しかし、やる気を無に帰すのが、就職差別です。
就活で「不採用」と通知されると、全人格を否定されたと感じて辛い気持ちになります。就職差別のある会社は、あなたの適性・能力ではなく、性別や出身地など努力ではどうにもならない事情で、採用において差別をしてきます。
「社風に合わなかった」「求める能力が足りなかった」など、努力で改善できる問題ならまだしも、就職差別を不採用の理由にされるのは違法と言わざるを得ません。不採用になった労働者としても、納得のいかないことでしょう。
今回は、就活生を苦しめる就職差別の問題と、採用において違法な差別を受けたときの対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 就職差別は、採用の差別のうち、判断基準とすべきでない要素による違法な行為
- 就職差別を禁止する法律はたくさんあり、違法なのは明らか
- 自分の努力ではどうにもならない理由で不採用にされたら、違法な就職差別の可能性あり
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
就職差別とは
就職差別とは、採用・内定といった労働のスタート地点で起こる、違法な差別です。一般には「採用差別」「就活差別」とも呼びます。
就職差別は、労働者の適性・能力と関係ない事情で採否が決められることで起こります。
就活シーンでは、会社の「採用の自由」が際立ちます。つまり、「誰を採用するか(もしくは、採用しないか)」「どんな労働条件で入社させるのか」といった選択権が、会社側にあるという意味です。
採用における「生殺与奪」を握られたに等しい状況です。必然的に、採用される側の労働者は、弱い立場であり、虐げられやすくなります。このような場面で起こりやすい労働問題が、就職差別です。
会社の「採用の自由」といえど、無制約ではありません。例えば、社会的なマイノリティを排除する基準を許せば、違法な差別を認めるのにつながり、少数派の人権を侵害してしまいます。
そのため「就職差別は禁止される」という点で、採用の自由といえど一定の制限を受けるのです。つまり、採用の自由があっても、不当な差別は違法であり、許されません。
就職差別は法律で禁止されている

就職差別を禁止する法律には、次のものがあります。
採用の自由が基本にありますが、その例外として、就職差別は許されません。採用の場面で起こりがちなさまざまな差別を禁止する法律があることからもわかります。
憲法
憲法は、日本で最も基本となる法律です。労働者側に職業選択の自由(憲法22条1項)が認められる反面、会社側には採用の自由があります。憲法は思想信条の自由(憲法19条)と法の下の平等(憲法14条)を定めているので、就職差別においても思想信条を理由とする差別は憲法違反です。
労働基準法
労働基準法3条でも、憲法と同様に、信条による差別の禁止が定められています。憲法の基本的なルールを確認し、賃金その他の労働条件についての差別が禁止されることを特に示した条項です。また、労働基準法4条では、男女差別の禁止が謳われています。
労働基準法3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労働基準法4条(男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
労働組合法
労働組合法は、労働組合の権利保障を定める法律です。採用の場面でも、組合員なのを理由とした就職差別は禁止されています。組合加入に関する差別は、不利益取扱の不当労働行為(労働組合法7条1号)にあたり違法です。
「労働組合がない会社での相談先」の解説

男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法は、正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」、略して「均等法」とも呼びます。この法律は、労働のあらゆる面で性別を理由とする差別を禁じています。募集、採用における性差別を禁止する条項は、次の通りです。
男女雇用機会均等法5条
事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)
職業安定法
職業安定法は、業務の目的の達成にとって必要でない個人情報の収集を禁止しています。この定めは、就職差別の禁止と共に、労働者の個人情報を保護する意味もあります。
労働施策総合推進法
労働施策総合推進法は、元は「雇用対策法」という名称でしたが、改正によって名称が変更されました。就職差別との関係では、同法9条が、募集、採用における年齢差別の禁止を定めています。
労働施策総合推進法9条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
労働施策総合推進法(e−Gov法令検索)
ただし、定年に関する制限、労働基準法の制限、特定の年齢が相当少ないときなどは、例外的に年齢による差別が許される場合があります。
障害者雇用促進法
障害者雇用促進法は、障害者の雇用の安定と、活躍を目指して作られた法律です。募集、採用の場面における障害者差別を、次の条項で禁止しています。
障害者雇用促進法34条
事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
障害者雇用促進法
障害者に関する労働問題は、採用段階だけでなく、入社後も起こる可能性があります。
「障害者雇用のトラブル事例と解決策」の解説

厚生労働省の定めるルール
法律ではありませんが、厚生労働省は、採用選考について行政のルールを発表しています。厚生労働省は、ハローワークを管轄し、就活・採用においても企業を監督する役目を担います。基本的人権の尊重のため、応募者の適性・能力のみを基準に採用選考しなければならないと定めています。具体的には、次の禁止事項が「公正な採用選考の基本」として決められています。
<a.本人に責任のない事項の把握>
・本籍・出生地に関すること
(注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)・家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
(注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します)・住宅状況に関すること
(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)・生活環境・家庭環境などに関すること
<b.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握>
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること
・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
<c.採用選考の方法>
・身元調査などの実施
(注:「現住所の略図」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)・合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
公正な採用選考の基本(厚生労働省)
「圧迫面接の違法性」の解説

違法な就職差別の具体例

次に、違法な就職差別として禁止されるのがどのような行為なのか、具体例で解説します。気付かないうちに就職差別の被害に遭わないよう、事前に理解しておいてください。
採用の自由といえど、会社経営の面からみた合理性がなければなりません。したがって、「業務の目的の達成」という観点から、採用判断をする必要があります。本人の適性・能力と関係な情報を収集し、採用の判断基準にするのは、就職差別の典型例です。
就職差別は違法であり、その元となる事情を調査することもまた、同様に違法です。業務上必要不可欠であっても、収集目的を本人に示す必要があります(平成11.11.7労働省告示141号)。
性別を理由とする就職差別(男女差別)
性別を理由として採用において差別するのは、違法な就職差別です。「採用するかどうか」の点での差別だけでなく、採用時の条件が男女で異なっていたり、女性だからといって就活セクハラをしたりといった行為も禁止されています。
- 女性は採用しない
例:「男性限定」など - 男女で、採用するときの基準が違う
例:「女性は運転免許を要する」「女性は未婚者のみ」など - 募集で男女別に人数制限する
例:「男性3人、女性1人」「女性は1名限定」など - 募集で男女別に年齢制限する
例:「女性は30才以上」など - 男女いずれかを表す名称で募集する
例:「〜レディ」「〜ウーマン」「ホテルマン」など - 女性に限定して特別な質問をする
例:「結婚する予定があるかどうか」「妊娠・出産しても働く気があるか」など
ブラック企業では、結婚による寿退社、妊娠・出産による育休・産休の取得などに敏感であり、性別を理由とした就職差別が起こりやすい環境にあります。
なお、男女の均等が難しい業種など、どうしても性別を限定する必要のある場合には除外規定があり、区別した扱いが一部で認められていますが、あくまで限定的なものと考えるべきです。例えば、芸能に関する仕事、警備業、危険な仕事といった限られた職種では、片方の性別を優遇することが認められる場合があります(「芸術・芸能の分野における表現の真実性等の養成から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務」「守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務」「宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上、そのほかの業務の性質上、男女のいずれかのみに従事させる必要性のある職務」)。
男尊女卑が根強く残る、古い考えの会社ほど、入社後も男女差別が起こりがちです。
「職場の男女差別」の解説

出身地を理由とする就職差別
出身地を理由に採否を決めるのも、就職差別の1つであり、違法です。採用面接で出身地を質問するのも、聞いた側は雑談くらいの気持ちでも、禁止だと言わざるを得ません。「同郷だった」などと盛り上がって出身地がわかってしまっても、採用の判断基準にすれば違法です。
次のような出身地差別は、特に違法性が強いです。
- 部落の出身者を不採用にする
- 同和だといって差別する
- 在日だといって差別する
いずれも、本人の適性・能力と関係ありません。どの地域の出身でも、能力には影響しませんし、出身地は努力で変えられません。出身地を理由とする就職差別は、社会的マイノリティを排除する危険な行為なのです。
家族・家柄を理由とする就職差別
出身地と同じく、家族や家柄も生まれもってのもので、努力しても変更はできません。したがって、家族・家柄を理由とする就職差別も違法です。
- 先祖の家柄が悪いといって不採用にする
- 先祖の出身地で採用を決める
- 実家が資産家かどうかを採用基準にする
- 変わった名前や、キラキラネームによる差別
思想信条・宗教を理由とする就職差別
思想信条や、信仰する宗教は、本人次第で変えることはできます。しかし、信教の自由は憲法に定められた基本的な人権であり、採用に配慮して変更する必要はないものです。そのため、思想信条・宗教を理由とした就職差別も許されません。
- 特定の宗教を信仰している人を採用しない
- 特定の団体への寄付や布教活動への協力を入社の条件とする
- 尊敬している人物で採用を決める
業務に無関係な健康状態を理由とする就職差別
業務遂行が不可能な健康状態のとき、不採用の理由となります。しかし、以下の病気は業務に関係なく、これらを理由とすれば違法な就職差別です。
- HIV(エイズ)、B型肝炎の患者を採用しない
- うつ病・適応障害になったことがあるか質問する
内定をもらえたのに、健康診断を受けたら不採用を告げられたケースでは、健康状態を理由にした違法な就職差別を疑うべき例もあります。
HIV抗体検査(警視庁警察学校)事件(東京地裁平成15年5月28日判決)は、本人の同意なく行ったHIV検査を違法とし、東京地裁平成15年6月20日判決でも、B型肝炎検査を同意なくして不採用にした事案で、プライバシー侵害にあたり違法だと判断しました。
「うつ病休職は再就職に不利か」の解説
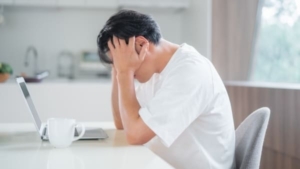
違法な就職差別を受けたときの対応

最後に、採用の場面で、残念ながら就職差別されてしまったとき、労働者側の対応を解説します。
就職差別をしてくる企業が思いのほか多いのは、企業側もその違法性に気付いていないからです。古い体質な会社ほど固定観念があり、差別を押しつける傾向があります。大企業や有名企業だからといって油断してはいけません。
不採用の理由が違法でないか、確認する
まず、就職差別を疑うような被害にあったとき、不採用の理由を確認してください。就職差別の責任を追及するとき、「差別があること」、すなわち「不採用の理由が違法なこと」は、労働者側で証明しなければなりません。
会社は、不採用の理由の開示を拒むケースがほとんどですが、就職差別が疑われるなら、ためらってはいけません。「違法なのではないか」と疑念が生まれる根拠となった面接官の発言、採用選考時のできごとを具体的に指摘して、不採用理由を開示するよう強く求めてください。
労働審判、訴訟といった裁判手続きで争うことを検討しているなら、理由の開示は内容証明で通知し、証拠に残るようにしてください。
採用の強制は難しい
就職差別で不採用となっていたとわかったとき、納得いかないでしょう。そのような不当な扱いを受けたとき、内定や採用を認めてほしいと強く思う方もいます。
しかし、差別的な扱いが違法だとしても、内定、採用を強制することまではできません。なぜなら、最終的に雇用するかは「契約」の問題で、そこには採用の自由が存在するからです。採用の自由は、就活シーンにおける根幹であり、その自由を侵害して採用を強制するのは難しいのです。
慰謝料を請求する
一方で、就職差別するような会社にはもう入社したくないという方も多いです。このとき、採用において差別されたことで負った精神的苦痛については慰謝料を請求することができます。
就職差別は違法であり、不法行為(民法709条)にあたります。精神的苦痛以外にも、「他の会社の内定を断ってしまった」などの実損が生じているなら、あわせて損害賠償請求できます。

なお、単に不採用となるだけでなく、一度はもらえた内定が、就職差別によって取り消されたなら、内定取消への責任追及もしなければなりません。
「内定取り消しの違法性」の解説

まとめ

今回は、違法であり許されない、就職差別について解説しました。採用時に、努力ではどうにもならない事情で差別するのは、法律上許されないこと。採用で差別を受けてしまったら、その違法性について会社の責任を追及できます。
就職差別が理由で、採用を拒否されたときは、採用の強制まではできないものの、「差別されたこと」について、慰謝料など損害賠償を請求できます。「就職差別するブラック企業に入社しなくてよかった」と切り替えて、被害回復に努めましょう。
とはいえ、会社がどんな採用基準で、どんな理由で不採用にしたか、外部からの判断は難しいもの。労働者がひとりで就職差別を立証するのはハードルが高いこともあります。差別なのではないかと疑問を感じる方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- 就職差別は、採用の差別のうち、判断基準とすべきでない要素による違法な行為
- 就職差別を禁止する法律はたくさんあり、違法なのは明らか
- 自分の努力ではどうにもならない理由で不採用にされたら、違法な就職差別の可能性あり
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/






