今回は、有給休暇を強制的に取得させられることの違法性について、労使問題に強い弁護士が解説します。
有給休暇は、労働者の権利で、どんな理由でも問わず使えるのが原則。
逆に、有給休暇を残しておきたければ「使わない」という選択肢もアリです。
しかし、病気やケガで労働者が休まざるをえないとき、有給が勝手に使われることがあります。
これが、有給休暇を強制的に取得させられてしまうトラブル。
使いたくないのに有給休暇を消化させられてしまえば、違法です。
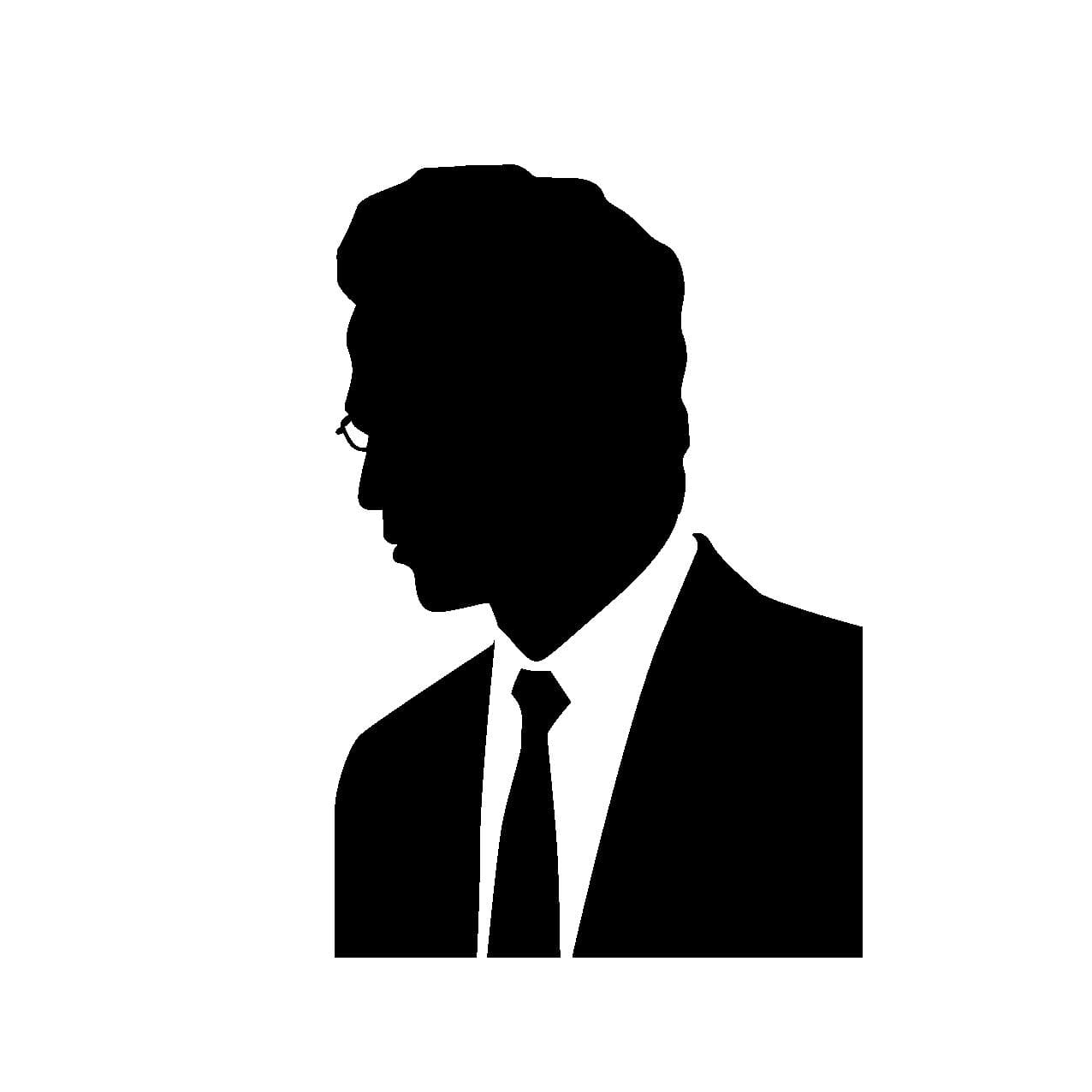 相談者
相談者勝手に有給を使われたが、結局無駄に過ごしただけだった
 相談者
相談者病気で休んでも給料が減らないと思ったら有給扱いだった
こんな相談は、特に、コロナ禍で急増しています。
病気にかかって会社を休むしかないとき、どうせ出社できないなら、会社としてはここで有給休暇を消化してしまえば、労働者が好きなときに休むのを妨害できるからです。
有給休暇は、とりたいときにとるべきもの。
勤続の功労への恩恵ですから、休みたいときに有給休暇がとれないと、意味がありません。
- 有給休暇は労働者の権利なので、いつとるか、とらないかは労働者の判断
- 労働者の意思に反して、有給休暇の取得を強制するのは、違法
- 勝手に有給休暇を消化させられたら、異議を述べ、未払いとなる給料を請求する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
★ 有給休暇の労働問題まとめ
【有給休暇のとり方】
【退職時】
【有給休暇の違法な扱い】
【休暇の基礎知識】
有給休暇の取得を強制するのは違法

有給休暇とは、労働基準法で定められた、労働者の心身の疲労を回復するために休暇をとる権利であり、かつ、その休暇には給料を払ってもらえるものです。
有給休暇は、一定の期間、継続して働いてくれたことに対する恩恵です。
そのため、有給休暇を取得できる日数は、勤続年数ごとに次のように定められます。
(下記は、正社員の例ですが、アルバイトや契約社員なども、労働時間に応じて有給休暇をもらえます。)
| 継続勤務年数 | 労働日 |
|---|---|
| 6ヶ月経過 | 10日 |
| 1年6ヶ月経過 | 11日 |
| 2年6ヶ月経過 | 12日 |
| 3年6ヶ月経過 | 14日 |
| 4年6ヶ月経過 | 16日 |
| 5年6ヶ月経過 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
有給休暇の取得は、法律上の権利ですから、権利を行使するかどうかも権利者が自由に決められます。
どんな理由でも取得できる反面、労働者は、有給休暇を取得しないという選択もできます。
したがって、会社が労働者に、有給休暇の取得を強制するのは違法です。
また、労働者の同意なく、勝手に有給扱いとして、残日数を消化するのも同じく違法です。
有給休暇は、どんな理由で取得するかは問われません(年休自由利用の原則)。
つまり、どんな理由でも、有給休暇をとるのを会社にさまたげられることはなく、むしろ、理由を聞かれること自体がそもそも違法の疑いが高いです。
有給休暇をうまくとる方法については、次の解説をご覧ください。

有給休暇の強制取得トラブルは、コロナ休みに有給をあてるケースだけでなく、平時も起こります。
例えば、ゴールデンウィーク(GW)や夏季休暇など大型連休に有給休暇をくっつけ、連休を延長するよう強制する場面です。
会社側の都合としては、
- どうせ中日に出てきても仕事がない
- 工場が止まってしまうから休んでもらうしかない
- 連休には客足が遠のく業種だ
といった思いがあるかもしれませんが、労働者が希望しない有給休暇をとらせるのは、労働者の意思を無視した違法な扱いです。
有給休暇を勝手に消化されてしまう例
次に、有給休暇を強制的に取得されてしまうという問題をイメージしてもらいやすくするため、どんなケースで問題となるのか、例をあげて解説します。
いずれの例も違法であり、有給休暇とすることを断ってよいケースです。
欠勤日を有給休暇にされるケース
1つ目のケースは、病気などで欠勤した日を、勝手に有給休暇の取得だと扱われる場合です。
このケースでは、「有給休暇にしといたから」と伝えられる場合もあれば、休んだのに給料が払われていて、勝手に有給休暇の残日数が減らされている場合もあります。
病気で休まざるをえないのはしかたないですが、有給休暇を使うかは労働者の自由。
有給休暇を使わなければ欠勤となり、欠勤控除により給料が減る可能性があります。
これはノーワークノーペイの原則の当然の帰結で、働いていない分の給料はもらえません。
その分、有給休暇をとらされなければ、後日休みたい日に、給料をもらいながら休める権利があります。
出勤日を有給休暇にされるケース
2つ目のケースが、出勤日なのに休みとされ、かつ、有給休暇と扱われる例です。
例えば、業務の閑散期に、シフトを減らされ、その分だけ有給休暇を減らされるといったケースです。
本来は出勤日なのであれば、給料をもらえるのは当然のこと。
有給休暇をとらなくても給料をもらって働けたわけですから、勝手に有給休暇を消化されてしまえば労働者にとって一方的に不利だといえます。
会社都合の休みを有給休暇にされるケース
3つ目のケースが、会社都合の休みを、勝手に有給休暇にされてしまう例です。
会社都合の休みとは、公休や、会社側の理由による休業があります。
例えば、工場が稼働しないために休みにせざるをえないといった会社側の理由であれば、本来、休業にしても平均賃金の6割分の給料をもらえます。
このとき確かに休業ならば、有給休暇を取得すれば6割ではなく全額の給料がもらえますが、取得するかどうかは労働者の判断にまかされています。
勝手に有給休暇をとらされたときの対応方法

次に、有給休暇をとらされてしまったとき、どんな対応をしたらよいか解説します。
勝手に有給休暇をとらされ、残日数を消化されてしまったとき、労働者側で有給休暇を勝手に使われるデメリットがあるのはあきらかですから、徹底した対応が必要となります。
有給休暇を使わないと意思表示する
まず、欠勤した日を有給にすると通告されたときなど、勝手に取得を強制されてトラブルになるのがあきらかなときは、「自分は有給休暇を使うつもりはない」という意思表示を明確にしておきましょう。
有給休暇を使うかどうかは、労働者の判断ですが、意思を明示しておかないと、「黙っていたのは、同意したということだ」といわれるおそれがあるからです。
このとき、将来の紛争に備えるため、書面やメールなど、証拠に残しておいてください。
有給休暇を減らさないよう警告する
次に、今後も会社で働き続けるときには、将来有給休暇をとりたいタイミングが来るでしょうから、有給休暇を減らさないよう、警告しておきましょう。
この段階で弁護士に依頼すれば、弁護士名義の内容証明を送って違法性を指摘し、プレッシャーをかけることができます。
未払いの給料を請求する
最後に、それでもなお、有給休暇を強制的に取得した扱いにしたい会社は、あなたの将来の休みに対して、給料を払ってくれないことが予想されます。
「すでに、あのとき有給休暇を消化してしまっているから、あなたの次の休みは有給ではない」というわけ。
このとき、有給休暇を強制するのは違法ですから、まだ有給休暇を使っていないならばもらえるはずの給料を請求するようにしてください。
未払い給料の請求は、まず内容証明で請求書を送って交渉し、解決できないときは、労働審判、裁判へ移行します。
給料を請求する具体的な方法は、次の解説をご覧ください。

有給休暇を勝手に使われるデメリット

有給休暇を勝手に使われると、労働者側にデメリットがあります。
なぜ、会社は、本来自由なはずの有給休暇を、強制的に取得させようとするのか、それは、会社にとってそのほうが都合がよいからであり、逆にいえば、労働者にとっては不利益が大きいことこの上ありません。
近年のコロナ禍では、「収束したら旅行にいこう」と有給休暇をためる人も多いです。
勝手に有給休暇をとらされてしまえば、その願いはかないません。
また、コロナによる休みを有給休暇にされてしまえば、外に出られるはずもなく有効活用もできません。
残しておいた有給休暇が勝手に消化される
有給休暇は、労働基準法によって、勤続年数が1年経過するごとに付与されます。
そして、有給休暇の時効は2年とされています。
有給休暇は、1年ごとに新たな権利をもらえて、すぐに使わなくても2年間はためておけるのです。
有給休暇の性質から、長期の連休をとって有意義に使いたい人ほど、有給休暇を使わずためる選択をします。
有給休暇を強制的に取得させられると、せっかく残しておいた大切な有給休暇が、勝手に消化されてしまいます。
有給休暇を十分に活用できない
有給休暇は、希望のタイミングでとってはじめて意味があります。
会社に無理やりとらされた、望まないタイミングの有給休暇は、十分に活用できないおそれがあります。
病気やケガで、いずれにせよ休まなければならない日や、その理由が業務にあるような労災なのに、有給休暇を使わされてしまっても、自由に外に出かけて楽しむことなどできません。
有給休暇をとって旅行や観光にいくはずが、自宅で過ごさざるをえないタイミングでとらされれば、利用目的が事実上制限されているのと同じことです。
例外的に、有給休暇の取得を強制されるケースと、その際の注意点

有給休暇は、労働基準法に定められた労働者の権利ですが、逆に、会社が労働者に、有給休暇を強制的に取得させられる場面もあります。
それが、法律に定められた、次のケースです。
時季変更権の行使
会社は、労働基準法により、時季変更権という権利を行使できます。
時季変更権とは、労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営」を妨げるとき、権利行使によってその時季を変更できるというものです(労働基準法39条5項ただし書)。
なお、権利である有給休暇のタイミングを変更するという時季変更権は、限定的に考えられており、対象となる労働者が事業の運営に必要であり、かつ、代替要員を確保するのが困難であることが条件とされています。
そのため、時季変更権があるからといって、いつでも有給休暇のタイミングを変更したり、勝手に決めた日に休ませたりできるわけではありません。
計画年休
計画年休とは、あらかじめ労使協定で有給休暇をとれる日を決めておき、計画的に付与する制度です。
本来、できるだけ計画的に有給休暇を調整し、しっかりと休みがとれるようにするための制度ですが、その反面、会社が有給休暇をとらせる日を決めることができます。
ただし、計画年休の場合、労使協定が必要となります。
また、計画年休を導入するとしても、労働者が自由に使える有給休暇を、年5日は残しておかなければなりません(年5日を超える有給休暇について、計画年休を適用できます)。
年5日の有給休暇をとらせる義務
有給休暇の取得率を向上させることをねらいとして、2019年4月より、会社が労働者に対して年5日の有給休暇をとらせることが義務付けられました。
具体的には、年10日以上の有給休暇を付与されている労働者には、年5日は必ずとらせなければならず、5日とれなそうな場合には、労働者に希望を聞き、時季を指定して取得させなければなりません。
ただし、こちらの義務についても、すでに年5日の有給休暇を取得済みであったり、取得日が決まっていたりする労働者にまで、有給休暇を勝手にとらせてよい理由にはなりません。
まとめ

今回は、会社が労働者に対して、有給休暇を強制的に取得させてしまう問題点について解説しました。
コロナの流行により、労働者がどうしても休まざるをえないという状況が増加したため、近年は特にこのようなトラブルが社会問題化しています。
有給休暇は、法律によって認められた労働者の権利。
労働者が自由に取得日を決められて当然です。
労働者側の利益を考えると、病気やケガによって休まざるをえないとき、有給休暇を減らしてしまうのではなく、別の方法によって対応したほうが得なケースがほとんどです。
そのため、会社が有給休暇を強制的に取得させることは、労働者の意思に反しているといわざるをえず、多くのケースで違法となるおそれが強いです。
- 有給休暇は労働者の権利なので、いつとるか、とらないかは労働者の判断
- 労働者の意思に反して、有給休暇の取得を強制するのは、違法
- 勝手に有給休暇を消化させられたら、異議を述べ、未払いとなる給料を請求する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
★ 有給休暇の労働問題まとめ
【有給休暇のとり方】
【退職時】
【有給休暇の違法な扱い】
【休暇の基礎知識】






