退職後に気になるのが、「退職金はいつもらえるの?」という点でしょう。
退職金の支給時期は、法律で明確に定められているわけではなく、会社ごとの就業規則や退職金規程に従います。退職の仕方や社内の手続き状況によっては、受取りのタイミングが遅れることもあります。住宅ローン返済や生活資金、転職の準備など、退職金の充当先を予定している人は特に、支給タイミングが分からないと不安になってしまいます。
今回は、退職金がいつもらえるのか、一般的なタイミングと、受け取りが遅れている場合の確認方法、法的な対応策について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 退職金の支給日は、企業ごとに退職金規程などに定められている
- 退職金が振り込まれないときは、弁護士に相談し、内容証明で請求する
- 退職金の時効は5年なので、受け取れないまま放置しないよう注意する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
退職金とは

退職金とは、従業員が退職する際に会社から支給される金銭のことです。
退職金の目的は、長年の勤務に対する慰労や功労への報酬であると同時に、退職後の生活支援の性格を有します。法律上、会社に退職金を支払う義務はなく、制度の導入は会社の判断に委ねられます。そのため、退職金が支払われるかどうかは、その企業の就業規則や退職金規程に制度として定められているかどうかがポイントとなります。
退職金の支給対象は、会社の規程によって異なりますが、正社員が主となります(契約社員やバイト、再雇用の嘱託社員などに退職金を支給する企業もあります)。支給条件は、勤続年数や退職理由でも異なり、自己都合退職よりも会社都合退職の方が有利な条件で支給されることが多いです。また、懲戒解雇の場合は、退職金を不支給または減額としている例もあります。
退職金の形式は、一時金や年金があり、企業によっては確定拠出年金(企業型DC)、中退共といった外部制度を活用する例もあります。
「退職金の性質」の解説

退職金はいつもらえる?支給時期は?

次に、退職金はいつもらえるのか、支給時期について解説します。
退職金の支給時期は、法律で一律に定められてはおらず、企業や制度によって異なります。一般には、退職後1ヶ月〜2ヶ月程度ですが、事前に会社に確認しておくことがお勧めです。
支払条件は労働契約で定められている
退職金をいつ支払うかは、法律に定めがなく、各企業の退職金規程や就業規則で決まります。これら規程類は、労使間の労働契約の内容となります。
例えば「退職日から1ヶ月以内に支払う」「翌月の給与支給日に合わせて支払う」といったルールが設けられています。退職金も、給与と同じサイクルで払うために、、月末締め・翌月末払いなどのスケジュールを定める会社もあります。
「就業規則と雇用契約書が違う時」の解説

振込は退職後1〜2ヶ月後が通常
退職金の振込は、退職後1ヶ月〜2ヶ月以内に行われるのが一般的です。
会社側が退職日をコントロールできる解雇などの会社都合退職、あらかじめ予定された定年退職などの場合、準備して比較的早く払われるケースもあります。また、解雇についてトラブルとなり、解決金や割増退職金の合意をするケースは、退職の合意時に支払うことも多いです。会社によっては退職金を賞与や最終給与と合わせて支払うケースもあります。
このように、支払時期については様々な事情が絡むので、総務や人事の担当者に直接確認するのが最も確実です。
退職後だと会社と連絡を取りづらいでしょうから、退職届提出のタイミングや、退職前の面談などの際に、退職金の支給時期を確認しておくと安心です。
「懲戒解雇の場合にも退職金は請求できる?」の解説

退職金の振込までに時間がかかるケース
決算や人事異動など、社内業務が立て込む時期だと、時間がかかるケースもあります。場合によっては退職金の支給に3ヶ月以上かかる例も見受けられます。特に、中小企業では手続きが属人化しており、想定以上に遅延することがあります。
退職金の支給に時間がかかるのは、例えば以下のような場合です。
- 手続きの混雑などにより処理が滞る。
- 書類不備や退職手続きの遅れがある。
- 稟議や承認フローに時間がかかる(社内処理の遅延)。
- 支払いサイクルに合わせる必要がある。
- 経理処理のタイミングが合わない
- 人事異動の時期や担当者不在、人手不足などの社内事情がある。
複数の要因が重なると、振り込みにますます時間がかかります。退職金はまとまった金額になるため、将来の生活設計にも直結します。安心して退職後を迎えるには、支給日を事前に人事や総務に確認し、入金遅れも見越して準備することが大切です。
「会社を退職したらやること」の解説

公務員の退職手当の支払時期
公務員の退職金を、「退職手当」と呼びます。
国家公務員・地方公務員のいずれも、法律や規則で支給基準が定められ、民間企業とは違って支給条件や計算方法が統一されています。支給のフローも定型化されており、支給時期が大幅に変わるようなことは少ないです。
公務員の場合、退職後1ヶ月以内に支給されるのが一般的で、支給の流れは次の通りです。
- 退職者による必要書類の提出(退職申請書や退職手当請求書など)
- 各部署での承認・計算
- 最終確認・振込手続き
ただし、書類に不備がある場合は、支払いが遅れるケースもあります。
制度ごとの退職金の支払時期の違い
退職金の支払時期は、制度によっても異なります。代表的な4つの制度を紹介します。
退職一時金制度の場合
退職一時金制度では、退職金が一括支給されるのが特徴です。
支給までの目安は退職後1ヶ月〜2ヶ月で、社内の手続きが完了次第振り込まれます。勤続年数や給与額をもとに計算され、長く働いた人ほど退職金が高くなる傾向があります。
ただし、昨今は、退職金額を見直したり制度そのものを廃止したり、下記の確定給付型年金(DB)、確定拠出型年金(企業型DC)に移行したりする企業も増加しました。退職を検討する際は、自社の採用する制度をよく理解しておきましょう。
確定給付企業年金(DB)の場合
確定給付企業年金制度(DB)は、企業があらかじめ給付額を約束する年金制度で、一時金か年金形式かを選択できます。支給は年金機関(信託会社や保険会社)を通じて行われるため、振込タイミングは企業や制度設計によって異なります。企業ごとに支給手続きのフローや承認期間が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の場合
企業型確定拠出年金(企業型DC)では、退職者自身が移管や受給の手続きを行う必要があります。退職後にiDeCoや他の年金口座へ資産を移すことが多く、その手続き完了後に年金形式での受給が可能です。ただし、原則として受給開始は60歳以降となるため、退職時点で受け取れるものではありません。
なお、運用期間が10年未満だと、60歳で受け取ることができず、支給開始年齢が先延ばしとなる点には注意を要します。
中小企業退職金共済(中退共)の場合
中退共制度では、企業が中退共に毎月掛金を支払って積立し、退職時に共済事務局から本人に直接支給されます。企業が共済事務所へ請求手続きをした後、約4週間で本人に振り込まれます。支給前に「退職金等振込通知書」が本人宛に送付されます。
ただし、共済契約者である会社の申請が遅れると、受給が遅延するおそれがあるので、会社との連携が欠かせません。
「中退共の退職金がもらえないとき」の解説

退職金がなかなか振り込まれない場合の対処法
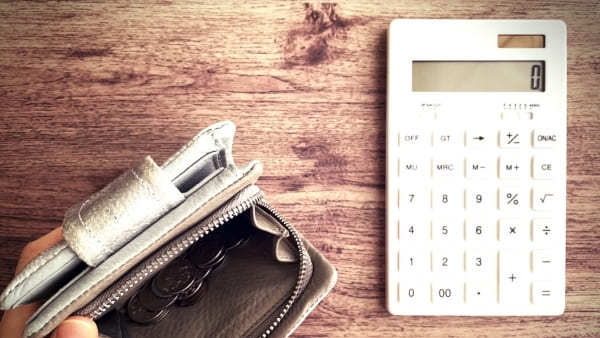
次に、退職金がなかなか振り込まれない場合の対処法を解説します。
退職の支給時期、振込タイミングが会社ごとに異なるとはいえ、あまりに支給が遅い場合は、不当な扱いを受けているおそれがあります。退職後しばらく経っても支払われないなら、適切な対処を速やかに講じなければなりません。
就業規則や退職金規程を確認する
まず、在籍していた会社の就業規則や退職金規程を確認しましょう。
退職後に慌てないためにも、退職を決断する前に、規程をしっかり精査しておくのが理想です。以下の情報を必ずチェックしてください。
- 退職金の支払時期や条件
- 支給対象者
- 不支給となる場合(懲戒解雇など)
よく調べると「勤続年数◯年以上」といった限定があったり、不支給条項が記載されていたりするケースもあります。規程に沿った対応でない場合は、会社に説明を求める根拠となります。
「退職金を請求する方法」の解説

経理や人事の担当者に問い合わせる
退職金が振り込まれない場合、経理や人事、総務などの担当者に直接問い合わせ、「いつ振り込まれるのか」と具体的に質問してください。やり取りを証拠に残すために、メールや書面など、記録に残る方法を選ぶべきです。
担当者が不在だったり、異動や退職していたりする場合は、部署の代表番号や代表メールに連絡し、現在の担当者を確認しましょう。退職後にトラブルに巻き込まれるケースもあるため、会社と連絡を取れるようにしておくと安心です。
「裁判に勝つ方法」の解説

支払いを拒否されたら弁護士に相談
問い合わせの結果、「退職金は出さない」と言われた場合は、規程を再確認します。
就業規則や退職金規程で本来受け取れるはずなのに、「退職金は支払わない」と言われた場合、支払い拒否は不当な可能性があります。会社に退職金を払わない理由を確認した上で、正当な理由がなければ、労働審判や訴訟といった法的手続きで請求可能です。
会社が応じない場合は、弁護士に相談するのが有効です。
弁護士に依頼すれば、会社との交渉を代行してもらえます。また、必要な証拠収集や裁判のサポートも受けられます。感情的な対立を避けたい場合や、会社の対応が不誠実な場合は、専門家に任せることで精神的な負担を軽減できます。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

内容証明で退職金を請求する
会社が退職金の支払いに応じない場合、内容証明で請求しましょう。
内容証明は「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったのか」を日本郵便が証明してくれる制度です。時効を中断する効果があるほか、裁判でも有力な証拠となります。弁護士名義で送れば、会社に強いプレッシャーを与え、支払いを促すことができます。
内容証明に記載すべき主な項目は、次の通りです。
- 自身の氏名・住所・退職日
- 請求する退職金の額(または根拠となる規程)
- 支払期限(例:「◯月◯日までに支払うよう求めます」)
- 支払われない場合の対応(法的措置も検討する旨)
例えば、次の書式を参考にしてください。
通知書
◯◯株式会社
代表取締役 ◯◯◯◯殿
私は、貴社にて20XX年XX月XX日に入社し、20XX年XX月XX日をもって勤続◯年◯か月で退職いたしました。しかしながら、現在に至るまで、退職金規程◯条に基づく退職金◯◯万円の支給を受けておりません。
つきましては、本書面到着から2週間以内に、私の給与振込口座宛に、上記退職金を速やかに支給するよう強く求めます。期限までに支払いが確認できない場合、労働審判や訴訟など、法的措置を検討せざるを得ないので、あらかじめご承知おきください。
【作成日・氏名】
内容証明を送っても対応されない場合は、労働基準監督署への相談のほか、労働審判や民事訴訟の申立てといった方法に進みます。
厚生労働省が設置している総合労働相談コーナーや各都道府県の労働局では、退職金を含む賃金未払い問題の相談が無料で行えます。労使間のあっせん制度など、弁護士に依頼する前段階の調整方法としても活用可能です。
「労働基準監督署への通報」の解説

退職金を受け取る際のポイント

最後に、退職金を受け取る際のポイントを解説します。
退職金を受け取る際は、税金や時効などの注意点が存在します。退職金の時効は5年なので、金額が大きいケースほど注意深く行動し、「支給額が少ないのでは?」といった疑問は、早めに弁護士に相談しておきましょう。
退職金の税金に注意する
退職金は、「退職所得控除」という大きな税制優遇措置が適用されます。
退職所得控除は、勤続年数に応じて一定額を控除し、税負担を軽減するものであり、長年勤務してきたことへの配慮を目的としています。具体的な計算方法は、以下の通りです(参照:国税庁タックスアンサーNo.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得))
| 勤続年数 | 計算方法 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円) |
| 21年以上 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
例えば、勤続25年なら、1,150万円(= 800万円 + 70万円 × 5年)の控除となります。この控除額を退職金から差し引いた残りの金額に対して、所得税や住民税が課税されます。
退職所得は分離課税の対象なので、給与所得や事業所得とは合算されず、別に税率が適用されます。多くの会社は退職金の支給時に源泉徴収をするので、原則として確定申告は不要です。ただし、受け取り方法によって課税の扱いが変わる点に注意が必要です(一時金で受け取れば退職所得控除が適用されますが、企業年金などの年金形式だと「雑所得」として通常の所得と合算され、税負担が重くなることがあります)。
退職金の時効に注意する
退職金には消滅時効があり、その請求権は5年間で時効により消滅します(労働基準法115条)。時効の起算点は、退職金を請求できる状態になった日、つまり、退職日や規程上の支給日です。この期間を過ぎると、正当な権利であっても実現できなくなるので注意が必要です。
時効の進行を中断するには、催告(請求)や裁判手続きの開始の方法が必要です。
具体的には、会社に内容証明で請求書を送付することで時効の進行を6ヶ月間止めることができ、その間に労働審判や訴訟などの正式な法的手続きを進めます。退職金を請求せず放置すると、権利が消滅し、後から受け取れなくなってしまいます。「そのうち振り込まれるだろう」と待っているだけでは、退職金請求権を失うリスクがあるのです。
「残業代請求の時効は3年」の解説

退職金について弁護士に相談すべきケース
退職金の支給が遅れたり、未払いが続いていたりする場合、弁護士への相談が有効です。
例えば、以下のケースでは、弁護士への相談を検討してください。
- 退職後2ヶ月〜3ヶ月経っても支給されない。
- 支払額が明らかに少ない。
- 支給額について労使の争いがある。
- 退職金の時効が迫っている。
- 懲戒解雇など、退職の理由に争いがある。
- 退職金が高額で、複数の制度が絡んでいる。
これらのケースは、会社側との交渉が必要であったり、裁判などに発展したりする可能性があるので、自力で対応するのはリスクが高いです。弁護士に相談すれば、法律や制度の知識をもとに、請求手続きをサポートしてもらうことが可能です。
「労働問題に強い弁護士」の解説

まとめ

今回は、退職金がいつもらえるのか、という疑問に回答しました。
退職金の支給時期は、法律で一律に定められているわけではなく、各企業の就業規則や退職金規程に基づいて決まるのが実情です。一般的には、退職後1か月以内に振り込まれるケースが多いものの、社内の手続きや承認フローの都合で遅れることもあります。
まずは、勤務先の就業規則や退職金制度を確認して、不明点は人事や総務の担当者に問い合わせましょう。それでも明らかに支払いが遅延していたり、納得できる説明が得られなかったりする場合は、法的手段を視野に入れることも重要です。
退職金はあなたの長年の勤労に対する正当な権利です。安心して新たなキャリアを歩むためにも、正しい法律知識に基づいて対処してください。
- 退職金の支給日は、企業ごとに退職金規程などに定められている
- 退職金が振り込まれないときは、弁護士に相談し、内容証明で請求する
- 退職金の時効は5年なので、受け取れないまま放置しないよう注意する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/





